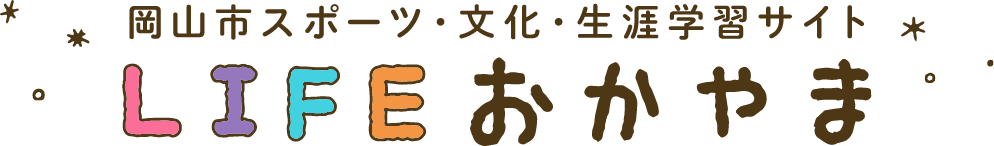
令和6年8月から9月の間に、社会教育実習や インターンシップとして、県内の大学生を受け 入れました。大学生の感想を紹介します。
岡輝公民館 ノートルダム清心女子大学 Mさん
実習では、地域課題と向き合う市民の方や職員からお話を伺う機会も多く、様々なメッセージを受け取ることができました。
「自分がいなくても活動が継続していくよう、住民の自主性を育てることが重要だ」という職員さんの話が心に残っています。
社会教育士は住民同士、地域同士をつなぐことで課題解決を目指す存在であると認識していましたが、実際に地域活動の現場を覗いていく中で、住民自身に力がなければ、根本的な課題解決は目指せないと気づかされました。
これから社会に出て社会教育に携わる際には、今回学んだことを活かし、地域の方々の力を信じて向き合い続けていこうと思います。
北公民館 岡山県立大学 Kさん
公民館はあらゆる用途で使われる施設のイメージでしたが実際には子ども食堂や子ども会の集まりぐらいしか使ったことがなく、多機能と実感したことはありませんでした。
公民館が子どもと親が遊びに来る場であったり、学生が自習しに来る場であったり、高齢者向けの講座が開かれる場であったり、地域の人たちにとってあらゆる用途で使われていることを実感しました。
日頃、チラシで講座の募集を見ていて、人数は本当に集まるのか疑問でしたが、「介護予防教室」では25 人という想定以上の方々の参加があり驚きました。
ほぼ毎月参加されている方々が多く、自分で思っている以上にそういった講座や教室が地域の人たちにとって親しまれているのだとわかる貴重な経験でした。
南公民館 就実大学 K さん
講座の見学や参加者との懇談の時間なども設けていただき、私にとって非常に貴重な経験となりました。
持続可能な地域づくりに向けてどのような取り組みをすればいいのかを常に考え、行動している職員の方々が特に印象的でした。
公民館のミッションは「共生のまちづくりの拠点となること」であり、館長さんからは、「そのためにはESDの取り組みが大事で、単発の行事だけでなく、長期的なビジョンを立てて、地域の人たちや行政、利害関係者が一緒に考えてゴールを目指すこと」と教えていただきました。
私は子どもの貧困について関心があったため、子ども食堂の方に、始めたきっかけや公民館との関わりなどを教えていただき、同時に、知識でしか知らなかった問題を現実として実感することができました。
まずは地域住民の“いま”を知っていくことが重要であると感じました。
