概要
岡山理科大学附属高等学校科学部は、平成24年度に発足し、自然観察を基盤として野外での調査や研究を積極的に行っています。
平成25年度からは身近な用水での水質調査や生き物調査など、水に関する活動について重点的に取り組みを始めました。
旭川合同用水での水質調査
本校の身近な用水である旭川合同用水において、年間を通して水質調査を行っています。
旭川合同用水は、岡山市玉柏から牟佐間の旭川合同堰から取水し、西川用水へ合流後、児島湾へ流下します。旭川から取水直後であるため、きれいな水が流れていると考えられますが、コンクリート護岸が多く、生活排水が流入している地点もあるため、水質悪化も懸念されます。岡山市南部を潤す農業用水の源を清浄に保ちたいとの考えから、この用水の排水等の影響を調査しています。これまでの調査からは、多くの地点で水質は良好ですが、夏場に水質が悪化しやすい地点があることが分かっています。

旭川合同用水での水質調査
百間川での水質調査
また、百間川でも水質調査を行っています。
百間川は、岡山市中区今在家の辺りで旭川から分流し、児島湾へ流下しています。川幅は約180m(百間)あり、旭川本流が増水しても氾濫しないようにするための人工放水路として、江戸時代に岡山藩士津田永忠により整備されました。分流部にはホタル池、せせらぎ広場といった親水空間がある一方で、市街地付近では周辺地域から排水が流れ込み、水質の悪化につながっています。旭川本流から毎秒1トンの浄化用水を導入していますが、河口水門は干潮時に合わせて水門を開くため、普段は水が滞留している状態です。近年護岸整備が急速に進んでいるため、環境への影響が懸念されます。

百間川での水質調査
これまでの調査から、浄化用水が流下する際に、市街地からの排水の影響を強く受けていることが分かっています。市街地付近では下水道の整備が遅れているため、岡山市下水道河川局とも連携しながら、祇園大樋から流下した用水が市街地を抜ける際にどのように排水の影響を受けているか調査を行い、岡山市民に水質改善を呼びかけていきたいと考えています。
水生生物の調査
旭川流域の河川などで、水生昆虫を中心とした水生生物の調査をしています。

水生昆虫採集の様子

川に入ってフィールドワーク
水生昆虫は、長期間水中で過ごしていることから、水環境を理解する上で重要な要素とされています。

環境の指標となる水生昆虫
これまでの理化学的な水質調査だけでなく、水生生物を利用した調査を行うことで、旭川流域の水環境の現状について、広く知見を得ることができます。高校生が実際に野外に出て行う調査研究は未だ多くありません。このようなフィールドワークを通して、自然探求の面白さを感じてもらいたいと思っています。
岡山理科大学附属高等学校 宮内伸弥先生

平成24年度から岡山理科大学附属高等学校に赴任。科学部の顧問として、生徒とともに野外活動に積極的に取り組んでいます。生徒は、水生生物の採集や観察などを通して生物多様性について考える、水辺の学習などの補助員をつとめることもあります。参加者や地域の人と交流し、地域を応援していきたいと考えています。
次の執筆者さんからのメッセージ!
岡山県立大学デザイン学部 教授 森下眞行さん
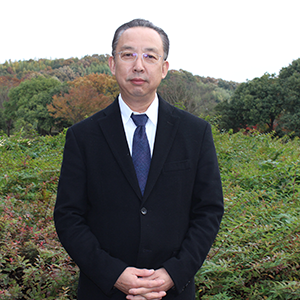
最近、真庭市の第2次環境基本計画への提言書作成に関わり、環境市民会議にゼミ学生と一緒に参加しました。参加した真庭市民の多くは、岡山市の水源となる旭川の水質を将来に渡っていかに保全するかを真剣に考えて行動しています。旭川の上流と下流でこのような活動が行われていることを、恐らく一部の人しか知らないのではないかと思います。岡山理科大学付属高等学校科学部さん、宮内先生、これからも地道ではありますが、旭川の調査研究を続けていただくと同時に、旭川流域に住む市民が「水」について考える場を作りましょう。
ご注意ください
- 情報の正確性や内容等に関して、岡山市及び本ウェブサイトの管理・運営者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 免責事項をご確認のうえ、情報の利用はご自身の判断で行ってください。
