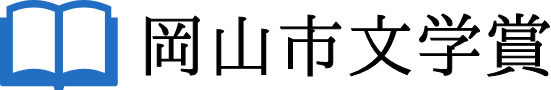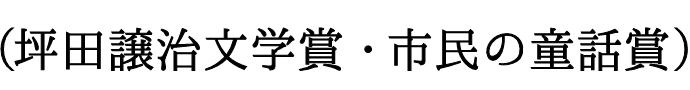ケイちゃんとかきのたね
そのとき、ケイちゃんは小学四年生でした。町のほうから、この村にひっこしてきて、小さな工場の寄宿舎に住んでいました。住んでいたといっても、工場で働いていたおとうさんおかあさんといたのです。
工場というのは、石油ランプのしんをつくる工場で、そこで働いている人は、五、六十人ぐらいでした。みんな近くの村から、朝々、そこへあつまってきました。朝は六時に、そこのポー(汽笛)が鳴りました。ポウウーとつづけて、五分ぐらい鳴るのでした。晩にもそれは、六時に鳴りました。朝はそれで工場がはじまり、晩はそれで工場のおしまいになるのです。
ところで、その工場の寄宿舎というのは、村の西のはしっこにありました。工場は東のはしっこでしたから、ポーが鳴って五分ぐらいしなければ、おとうさんもおかあさんも、ケイちゃんのいる寄宿舎に帰ってきませんでした。いや、五分ではたりません。きっと仕事場のあとかたづけがあるのでしょうか。どうしても十分以上、ときには三十分もかかりました。
ケイちゃんが学校から帰るのは、たいてい三時ごろなので、帰ると、まず戸だなにおいてあるふかしいもを食べます。それから、つくえのひき出しに入れてある十ばかりのかきのたねを出してながめます。これは、かきを食べたあと、おはじきをしようと、のこしておいたものなのです。それをいまは、ちょっとちがった気持ちで見るようになりました。
それというのが、一人でそんなことをしているうち、かならず、おかあさんが早く帰ってくればいいなあと思いだすのです。たなの上のめざましどけいを見ると、たいてい二時間も三時間も待たなければなりません。
それでも、ケイちゃんは、まどのそばへいって、背のびをして、工場の方をながめます。そして、ポウウー――と、一人でポーのまねをしてみるのでした。心の中では、おかあさあんとよんでみたりもするのでした。
ところで、そんなことをしていたある日のこと、ケイちゃんは、かきのたねを手にのせて、ふと思いつきました。
「早く、芽を出せ、かきのたね、出さんとはさみでちょんぎるぞ。」
さるかに合戦でかにがいった、このことばです。
ケイちゃんは、かきの実が食べたいからではありません。その寄宿舎のまどの外に、一本、高く四方に枝を張った大がきの木があったらなあと、思ったからなんです。
そこで、その夜でしょうか。ケイちゃんは、おかあさんにいいました。
「おかあさん、むかしはよかったなあ。」
「どうして。」
おかあさんが聞きました。
「だってさ。かにが、かきのたねにいったでしょう? 早く芽を出せ、かきのたね。すると、これを聞いたかきのたねが、もうすぐ芽を出した。ね、そこで、かにがまたいうでしょう? 早く木になれ、かきのたね。ならんと、はさみでちょんぎるぞ。」
おかあさんがいいました。
「それは話だからね。じっさいはそうはいきません。」
「そうかねえ。話のようにはいかないのか。つまんないねえ。」
そのあくる日です。学校の帰りに、ケイちゃんが、石さんにいいました。
「石さん、ぼくのいる、あの工場の寄宿舎な。あれ知ってるか?」
「知ってるとも。こっちゃ、この村の生まれだもの。生まれたときから知ってら。」
石さんがいいました。
「そうか。そんなに早くから知ってるんなら、村のこと、もうなんでもかでも知ってるね。」
「そうさ。知ってるとも、知らないことなんか一つもない。」
「そうか、じゃ、ぼくのいる寄宿舎の前にある畑、知ってるね。」
「知ってるとも。かきの木のある畑だろう。」
「そう、その畑のかきの木だよ。あれ、さるかに合戦のかにが、たねをまいたかきの木か。」
「ばか、さるかになんて、あれは話だよ。じっさいにかにが、かきのたねなんかまくものかい。あの畑はな、おれんちの畑なんだよ。そして、かきの木は、ぼくのおじいさんが、まだ子どものとき、親類からなえをもらってきて植えて、大きくしたかきなんだ。御所がきっていうんだとさ。秋になると、それこそ枝いっぱいにたくさんの実がなって、それが、まっかにうれるんだ。うまいぞう。そうだ。もうすぐ熟柿が食べられる。思い出しても、つばきが口のうちにたまるな。」
石さんはそういって、ゴクリとつばきをのみました。
「ふうん。そうかあ。そうなのかあ。」
ケイちゃんはもう、すっかり感心しました。すると、石さんはいよいよとくいになって、
「ほんとだよ、ほんとだよ。」
そういいながら、いっそう、かきの木のじまんをはじめました。
「夏になるとな、あの木のみきや枝に、それこそ何十と、せみがやってきてとまるんだ。そして、ジャージャーいったり、ジージー鳴いたり、それはにぎやかなんだ。ひくいところにいるのは、手づかみでとれるけれど、高いところにいるの、どうしても、さおがいるな。さおの先に、くもあみをつけてな。それで、ぱっとおさえるんだ。もちあみだと、いっそううまくいくけれど、あれは町へいかないと、売ってないだろう。」
そういってから、石さんはちょっと考え、また語りだしました。
「そうだ、ケイちゃん、とんぼ知ってるかい。やんまだよ。おにやん、とらやん。こんなに大きくて、つかまえると、頭をまわして、かみつくんだ。血が出るほどかみつくんだ。」
「ふうん。」
ケイちゃんは感心するばかりです。ケイちゃんは、もっと話したいことがあったのですが、わかれ道にきたもので、
「さよなら、さよなら、またあした。」
そんなことをいって、家に帰りました。しかし、いいたかったことがいえなかったもので、あくる日の帰り道、ケイちゃんは、それを石さんにいいました。
「ね、石さん、きのう話した畑のかきの木な。あれにいっぺんのぼらせてくれないか。」
「そりゃのぼらせてやってもいいが、かきの木というやつ、とてものぼりにくいんだよ。ケイちゃん、どんな木でもいいが、木にのぼったことあるのかい。」
考えてみると、町そだちのケイちゃんです。木になんか、いっぺんものぼったことはありません。そこで、
「さあ――。」
と、首をかしげてしまいました。
「まつの木はどうだい。」
「さあ。」
「すぎの木はどうだい。」
「ううん。」
「だめ、だめ。それじゃのぼれっこないよ。」
そんなことをいってるうちに、二人はもう、そのかきの木の見えるところにきました。
「おう、そうだ。あれを見ろ。あれがそのかきの木だ。どうだい。あれにのぼれるかい。」
石さんが、むこうを指さしていいました。いっしょに、なにやらかにやら、がやがやいってきた子ども連中も、そこでとまって、かきの木の方を見ました。
すると、セキさんがいいました。
「あれか、あれなんか、わけないよ。ぱっぱっと手につばきをつけてな。まず、木に――」
こんなことをいって、ぱっぱっやったのですが、とにかく百メートルもない、そこに、そのかきの木があるのですから、セキさん、
「うん、のぼるまねより、あそこにその木があるんだから、おれがいま、のぼってみせてやらあ。一つ二つと、そうだ。三つもかぞえるうち、ちゃあんと、あの木の枝のところへとりついてみせてやる。」
そういうと、もう、とっととかけだしていました。みんなも、あとについてかけました。もとより、セキさんが、かきのところに一番につきました。すると、本のつつみを木の根もとにほうり投げ、さっきいったとおり、ぱっぱっと手につばきをつけました。それから、ぞうりをぬいではだしになり、そして、かきの木のみきにだきついたのです。
そのあいだにみんなも、木のところにかけつけ、
「さあ、いちっにいのさん。かぞえるぞう。」
大きい声で、そういうものもありました。しかし、かきの木というものは、まつの木などとちがって、木のはだがつるつるしていました。のぼりにくいのでした。セキさんは、大いばりしたてまえ、一、二の三でのぼりたいのですが、そういきません。それに、枝のあるところまで、三メートルもあるのです。ううん、ううんとうなりながら、手に足に力を入れました。まわりをとりまいた連中も、かきの木ののぼりにくいことはよく知っていますから、声をそろえて応援しました。
「それっ、そこだ、力を入れろ。一、二、三。も一つ、一、二、三。」
この声といっしょにセキさんは、木をはさんでいる両足に力を入れて、からだを上に送ったもので、とにかくいちばん下の枝をつかまえました。そうなると、あとは平気です。それを力に上へのぼりついて、その枝にまたがりました。
「やれ、やれ――。」
これは、セキさんがいったのではありません。かわりに石さんがいったもので、みんな、わっとわらいました。そこでセキさん、
「まったく、思ったより難儀な木だなあ、この、かきの木。」
そういって、あらためて、自分の大息をつきました。
「ところで、どうだい。セキさんじまんのコッケコーロー、木の上だから、ひとつ、じょうずにやってみろよ。」
石さんにいわれると、ちょっと、首をかしげましたが、セキさん、
「しかたがない。ひとつやってみるか。」
そういうと、えへんなんて、せきをして、あごをつき出して、首をのばしました。そして、
「コッケ、コウーロウー、コッケ、コウーロウー。コッケ、コッケ、コケコッコ、コケイコッコ、コケコッコ。バタバタバタ、バタバタ。これは、にわとりの羽の音。」
そういって、木の上から、そこらへんをとくいそうに、すました顔をして見まわしました。石さんが、ひとり、うまい、うまいといってやりました。あとのみんなは、はははとわらったばかりでした。すると、
「さあ、ケイちゃん、のぼってみるかい。」
石さんがいいました。しかし、セキさんののぼりぐあいを見たもので、ケイちゃんは気がすすみません。
「ううーん。」
と、首をかしげました。それで、この日の木のぼりはおわりとなり、みんな、家に帰りました。セキさんも、木からすべりおりて、コッケコーロー、コッケコーローと、にわとりのまねをしながら、とくいそうに、家に帰っていきました。
ところが、そのあくる日です。ケイちゃんが、石さんにいいました。
「ね、石さん、あの畑のかきの木な。あれにぼく、やっぱりのぼりたいんだ。のぼらせてくれないか。」
「それは、いつでものぼらせてやるよ。しかしケイちゃん、のぼれないんじゃないかな。」
「うん、それだよ。きょうからぼく、毎日、学校の帰りに、あそこでけいこしてみる。かな棒のしり上がりよりやさしいんじゃないか?」
「そうさ、しり上がりからみれば、むずかしさはその半分の半分くらいだ。おれなんか、しり上がりはできないけれど、かきのぼりなら、いつでも、何回でも、どこまででものぼれる。」
「そうかあ。それなら、ぼく、きょうから毎日けいこしてみる。それでね、そのけいこのあいだ、毎日せんべい一まいずつ、石さんにやるよ。」
「ええっ。」
これには石さん、おどろきました。
「せんべい一まいもくれるの。どうしてくれるんだい。」
「だって、かきの木にのぼらせてくれるもの。」
「へええ、しかし、ずいぶんくれるんだねえ。」
そのころ、村の子どもが、せんべいをもらって食べるのは、一年に一度か二度です。春と秋のお祭りのときだけです。それを、木のぼりのけいこのたびに、毎日一まいもくれるというのです。だから、これを聞くと、いっしょに学校から帰っていたセキさんも、タカさんも、キクさんも、びっくりして、
「へえ、せんべい一まいも出すの。」
そういいあいました。すると、石さんが力をこめて、いうのでした。
「しかしケイちゃん、せんべい一まい、ほんとうにくれるの。」
「うん、ほんとうにやる。」
これも力をこめてこたえました。そこで石さんが、セキさんたちにいいました。
「な、きみたちもてつだえよ。せんべいを四人でわけよう。」
「うん、それがいい。そりゃ、うまい考えだ。」
四人はねあがって、わあわあよろこびました。
それで、すぐもう、木のぼりけいことなりました。まず、石さんとセキさんが、家から小さいはしごを持ってきました。二メートルばかりですから、子どもでもらくらくはこんでこられました。それに、六メートルもある、ふといなわもとってきました。
これで石さんは、木にのぼって、そのなわを上の横枝にかけました。ケイちゃんをなわにぶらさげて、上にひっぱりあげようというのです。これは、いつか会社にやってきた、ほりぬき井戸の職人がやっていたまねなんです。
「エンヤコウラ、そうら引けえ、ドッコイ、コウラア。」
こんなかけ声をかけて、かきの木のみきにだきついたケイちゃんを、四人は、つなをひっぱって引きあげました。もう、わけなしです。
そして、これを二、三回やると、せんべい一まいです。ほんとうにケイちゃんが、家に帰って持ってきました。これを四人に分けると、ひとり分は、そのころの一銭銅貨一まいぐらいになりました。しかし、石さんに分けてもらって、
「うめええ。」
なんて、やぎの子の鳴き声のような声を出して、ふざけるものもいました。二、三日、そんなことがつづきましたが、すぐケイちゃんも、ひとりでのぼれるようになりました。
すると、晩六時ごろになると、ケイちゃんは、その木のまたのところにのぼって、工場の方をながめました。しかも、それが毎日のことです。
どうしてだったでしょう。
おかあさんが帰ってくるのを、そうして待っていたのです。学校から帰って、ひとりで、家の中で待つのが、なんともさびしくてならなかったのです。それで、そうして木のぼりのけいこをして、木のまたにまたがって、おかあさんを待つようになりましたが、やはり、せんべいが一まいもあるもので、ときどき、石さんをさそいました。そして、せんべいを半分やって、そこで、なにやかや話をしながら、おかあさんを待ちました。歌なんかも、いっしょにうたいました。
ところが、おとうさんがこれを聞いて、ケイちゃんをかわいそうに思いました。それで、自分が工場のかじや場で働いているもので、そこをケイちゃんのたまり場にしてくれました。
そこには、ふいご場といって、火をおこして、鉄を焼く場所もあり、やすりといって、金物をけずる道具もありました。そこで、ケイちゃんは、学校から帰ると、ふいごのところで火にあたったり、やすりで、小刀をつくったりさせてもらいました。
そうして二、三時間して、おとうさんおかあさんとつれだって、いっしょに家に帰りました。それでも、春や夏にはときどき、かきの木にのぼって、とんぼやせみをとって、歌をうたいながら、おかあさんを待ちました。