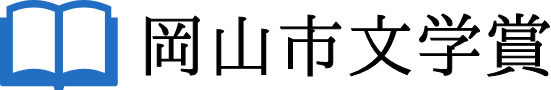猛獣狩
今日は日曜なのにお父さんもお母さんも用事があって出て行かれました。善太と三平とそして女中の竹やばかりが御留守番です。それでも午前中は善太も三平も学校のおさらいをしておとなしく留守番をしました。午後になると、少し退屈になって来ました。それでどうしようかと、二人とも机に向いたまま、首を傾げて考えて見ました。何だか、とほうもない面白いことがありそうです。
「まず屋根にのぼると――。」
善太はこんなことを考えました。
「きっと竹やが――坊ちゃん、いけません――って言うに違いない。だから、こっそり裏の物干を伝って登って行く。そして屋根のてっぺんから、三平ちゃん早く早くって大声でどなる。三平はビックリして外に飛び出す。然し僕がどこにいるかわからないから、そこら中をさがし廻る。――兄ちゃん、どこどこ、どこにいるの。――僕は黙っている。すると三平が家の中かと思って、中に入る。そこでまた、三平ちゃーんって、どなってやる。面白いぞう。」
ここ迄考えると、善太はついニコニコしてしまいました。
「どうしたの、兄ちゃん。」
それで三平がたずねました。
「ウン、いいことがあるんだ。」
「なに。」
「いいこと。」
「言ってよ。」
「とっても、いいことなんだ。」
「言ってよう。」
「もう、いいいいことなんだ。」
「言ってようッたら――。」
「ウン。」
善太は考えて見ました。然しこんなにいいことを、ただで言うて法はありません。
「ウン、言ってやる。だけど、その代りキャラメルを二つくれるんだぞ。」
「ウン。」
「ほんとだぞ。ウソなしだぞ。」
「ウン、ほんとうのほんとう。」
だけど、気がついて見ますと、三平はキヤラメルを持ていないんです。どんなにほんとうだって出せっこあリません。それで時計を見ますと、もう一時過ぎです。おやっを買いなさいと言って、お母さんから二人とも十銭ずつ貰っております。少し早いけれども、そうです。一時間半しか早くありません。もうそろそろキャラメル買ってもいい時間です。
「じゃ、こうしよう。」
それで善太が言いました。
「竹やにキャラメル買って来て貰おう。そしてそのうち二つぶ僕にくれるさ。そうしたら僕がいいいいことを教えてやるよ。」
「ウンウン。」
三平は大賛成です。それで二人は十銭ずつ出して、竹やにお使いを頼みました。ところで、竹やが出て行くと、もう三平が言いました。
「いいこと教えて。」
「あれ、もう言うのかい。」
「そうさあ。」
「ふーん、そうかあ。」
善太はそう言いましたものの、言おうとして考えて見ますと、どうしたのでしょう。さっきあんなに面白かったことが、もうちっとも面白くありません。キャラメル二つどころか、一つにだってなりそうにありません。きっと三平が苦情を言いだすにちがいありません。そこで考え直して見ました。と、どうでしょう。とってもいい考えが浮びました。
「ウン、三平ちゃん、いいことだぞ。二人でね、探検旅行をやるんだ。」
「探検?」
「そうさあ。いいか、猛獣映画っての見たろう。アフリカの原始林を猛獣を生捕りにして廻って歩く商人てのがいたじゃないか。」
「ウン。いた、いた。」
「あれをやるんだ。」
「あれをう。」
三平にはまだ分らないようです。善太にだって、まだ詳しい考えはつきません。で、
「いいから。待ってろよ。キャラメルを食べてから教えてあげる。」
そう言ってるところへ竹やが帰って来ました。
「ハイ、キャラメルです。」
竹やのこう言う顔を見ると、善太はまたいいことを思いつきました。
「あのね、三平ちゃん、茶の間は動物園。いいかい、竹やは土人の猛獣使い。そこへ僕達がたくさん猛獣を捕って来てあずかって貰うんだね、いいだろう。そこでキャラメルを二つお出しよ。」
「二つう。」
三平はちょっと惜しい気がいたしました。
「だってさ。猛獣使いにだって、何かやらなけりゃ働きゃしないよ。」
三平のキャラメルを受けとると、善太も二つぶのキャラメルを出しました。そして四つにして、茶の間へ持っていきました。
「ねえや、キャラメルあげよう。」
「あれ、私に下さいますの。」
「そうさ。その代り猛獣使いになるんだぞう。」
「猛獣使いですって、ホホホホ。」
「いいから、いいから。」
善太は一人でこうきめて、さっさと縁側の方へいきました。そこから一本のコウモリ傘を持て来ました。それをひろげて、すわって縫ものをしている竹やの上に冠せかけました。
「ね、土人が天幕を張ってるところなんだよ。とっちゃいけないよ。」
「へいへい。」
竹やはコウモリの下で縮こまって縫ものをつづけました。そこで、いよいよ猛獣狩りに取りかかることになりました。
まず三平は物さしを腰にさしました。これは刀です。帯を輪にして、片手に下げました。これは投げ縄です、次に座敷で座布団を二ところに重ね、その上に毛布をかけました。これが猛獣わなで、ここに猛獣を追い込む仕かけです。
「さ、三平ちゃん、ここに待っているんだよ。僕が猛獣を追い出して来るからね。」
善太は長柄のほうきを持ち、腰には三尺のはたきをさしました。
「猛獣出ろうッ。」
善太は奥の間へ駈けこんで、部屋中を見廻しましたが、猛獣など一匹もおりません。
「いないぞッ。チェッ。」
そこで押入れを開けて、中へほうきを押しこみ、カタカタとその辺を突きまくりました。
「いないなあ。ライオンが五六匹いてくれるといいんだがなあ。」
今度は茶の間を通って、台どころへ駆けこみました。が、駆けこむとたんに「や、いたぞうッ。」と、大声を出しました。ちょうどそこの上げ板の上に、家の三毛猫が眠っていました。
「こりゃ豹だ。ジャガーって言うんだ。大猛獣、ジャガー。」
こう言うと、善太は長柄のほうきを槍のように前に構え、「こらッ。こらッ。」と声をかけました。そして猫が目をさましたところを、さっとほうきを突き出しました。ビックリした猫は、そのときちょうど開いていた勝手口から身軽にピョンと一とびすると、それなり外へ走り出てしまいました。
「しまったあ。」
善太はわざと大きな声を出しました。
「三平ちゃん大変だあ。豹が逃げたんだあ。」
この声に三平もビックリして飛んで来ました。
「え、え、何が逃げたの。」
「豹だ。豹だ。家の猫豹だ。」
「ウン、猫豹、家の三毛猫だね。」
「そうだ。そうだ。」
二人はそこでドサドサと下駄をはき、外に飛び出して行きました。ところが猫豹は勝手口から四五メートルのところで、檜の根元に登りつくような姿をして、しきりに爪をといでおります。
「や、こいつ木登りするな。」
善太はほうきを構えましたが、三平は、
「待って、待って。」と投げ縄を両手に持ち、腰をかがめて近づいて行きました。猫は何をせられるのか分らず、爪をとぎ終ると、平気な様子であっちへいきかけました。そこを三平は飛びついて、
「えーい。どんなもんだい。」と投げ縄を持ったまま、両手で背中を押さえこみました。すぐ座敷へ抱いて来ましたが、どうもそんな捕え方では面白くありません。そこで、わなの前に、猫を置きました。そうして、その尻を善太がはたきで叩きました。
「ソラッ。わなへ飛び込めッ。」
然し猫はビックリして、縁側の方へ逃げ出しました。
「や、大変だ。大変だ。」と、また飛びかかって、それを捕え、今度は毛布の入口に猫の首を入れ、そこで尻を叩きました。そして猫が驚いて駆けこむところを、それッと三平に声をかけ、二人で毛布の下に押さえこみました。いよいよ大豹を生捕ったのです。
「押えてろ。逃がすな。」
そんなことを言い言い、善太は毛布の一方をそっと上げました。そして猫豹の片足を捕えると、
「ソラ放せ。」と、毛布の下から引出して、それから帯をもって、猫豹の身体をグルグル巻きにしました。
「ね、三平ちゃん、これなら大丈夫だね。」
そう言って、二人でこれを茶の間へ抱えて行きました。
「ね。竹や、番してるんだよ。逃がしちゃいけないよ。とっても苦心して生捕ったんだから。」
そう言って、帯の端を竹やの側のタンスの環に結びつけました。
さて、豹を捕えました。が、このつぎ何を生捕りにいたしましょう。象がいるといいのですが、どこを尋ねても、そんなものはいそうにありません。
「ね、三平ちゃん、こんどは何をつかまえようか。」
「トカゲはどう。一メートルもある大トカゲ。」
「ウン、それがいい。庭の石の上でよくねてる、あの紫色の大トカゲだ。」
善太は勇み立って、跳上りました。だけどこれを聞くと竹やが泣くような声を出しました。
「いけませんよ、坊ちゃん、この部屋なんかにトカゲを持ちこんだりなさったら、お母さまに言いつけますよ。」
「いいやい。竹やは土人の猛獣使いじゃないか。猛獣使いがそんなことを言うってことあるかい。」
善太は、もう腰にさしているハタキを抜いて、竹やを切りでもするように前に構えました。
「いいえ、猛獣使いでもお母さまに言いつけます。」
「だって、土人だろう。土人は日本語なんか言えないんだよ。」
「いいえ、土人でも言います。」
「じゃ、もう土人じゃないよ。土人でなかったら、猛獣使いでもないよ。」
「え、え、そんなものでなくったって、ちょっとも構いません。」
「じゃ、竹やはゴリラだ。」
「え、え、ゴリラでもよござんす。」
「ゴリラなら、トカゲなんか食べるんだぞ。やあい、竹やはトカゲを食べるんだって。トカゲ食べの大ゴリラだって。恐いや恐いや。逃げろ逃げろ。」
こんなことを言って、とうとう二人は茶の間から逃げ出してしまいました。座敷に来てみますと、何だか大変面白いことになって来たような気がします。だって、豹を捕えた上に、今は茶の間にゴリラさえ生捕りになっております。
それで善太が言いました。
「三平ちゃん、さ、トカゲ捕って来よう。」
これを聞くと、竹やがまた茶の間から言いました。
「坊ちゃん、ほんとにトカゲいけませんよ。竹やはゴリラですから、ちょっとも恐かありませんけれど、畳の下などに逃げこんで、夜になると坊ちゃんの床の中などにはいり込みますよ。」
こう言って、竹やは、
「ああ恐い恐い。」とつけ足しましたが、聞いて見ると、どうやらこれもほんとうのようです。
善太も少し恐くなりました。然し善太は言いました。
「恐くなんかないやい。」
「じゃ捕ってらっしゃいませ、何匹でも捕ってらっしゃいませ。」
「捕って来るとも。五十匹も百匹もとって来るんだ。ね。三平ちゃん行こう。網と籠を持って行こう。大トカゲ捕って来て、焼いてゴリラに食べさせてやろう。」
そんなことを言いながら、二人はお父さんが釣りに使う網と籠をぶら下げてお庭へ跣足で下りて行きました。
「大トカゲおれい――。」
「いないかな、一メートルの鬼トカゲ。」
が、ありがたいことに、今日に限っておりません。と、側で草の中を覗いていた三平が、
「あッいたいたッ。」と言ったので、善太は驚いて飛びのきました。
「えッ、ほんとにいるの。」
「ウウン、蟹だよ。小チャな蟹だよ。」
「どこどこ。」
草の中を覗きますと、何のこと、五センチもない手の中に入りそうな蟹が、草の根元で泡をふいています。
「何だい、こんな小蟹。」
そう言うと、草を分けて、
「ホラッ。」と、手で押さえつけました。そしてちょうど甲羅を上から指でつまみますと、
「とったとった、とったぁ。」と、家の中に駆けこみました。茶の間へ行きますと竹やが顔色をかえて立上りました。
「ほんとですか坊ちゃん。」
「ウウン、蟹だよ。蟹だよ。これは豹にやるんだ。」
そう言って、くくられて眠っている猫の鼻先につきつけました。それで眼をさました猫はビックリしたらしく、眼をパチクリやりながら、ソロソロと後退りをしました。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763