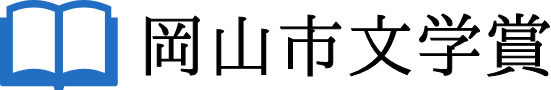「一匹の鮒」論― 一枚の葉が起こす影響について ―
(初収録単行本 『青山一族』1937(昭和12)年6月 版画荘)
(収録本 『坪田譲治全集 第2巻』 新潮社)
ノートルダム清心女子大学 大学院 博士前期課程 1年 大岡愛梨沙
坪田譲治の小説「一匹の鮒」という作品について、特にこの作品の最後の場面における象徴性に重点を置き、信心という視点から考察を深めていきたい。
まず、作品全体の流れを押さえておきたい。本作は「昔の話」として語りはじめられており、江戸時代を舞台としていると考えられる。主人公は現在の鳥取県にあたる、因幡の城下に住む扇屋久兵衛という人物である。この話は、主人公が子供を思う視点が重要であると考えられる。それでは、場面ごとにあらすじを紹介し、筆者の考察を加えていきたい。
ある秋の日、久兵衛は七歳の子供の宗助を連れて町はずれの神社にお詣りに行くところから物語は始まる。宗助は絵本を見ながら歩き、久兵衛との距離が出来ると彼の後を追って走るという動きをしていた。久兵衛はそのような動きをする宗助を気懸りに思うが、宗助がとうとう転んだことによって腹立たしさも覚える。この時、宗助の下駄の鼻緒が切れてしまったにもかかわらず、久兵衛はわざと知らぬ顔をする。久兵衛は、自分にしっかりついて来ない宗助に苛立ちを感じるあまり、宗助が申し訳なさそうな表情を浮かべているにもかかわらず、置いて歩き始める。しばらくしても宗助が後を追ってこないため、久兵衛は癇癪を起こして引き返す。すると、「お父さん――」という声を最後に宗助の姿が見えなくなる。
これは、久兵衛と宗助が鳥取の城下で暮らしているときの場面である。この場面で、久兵衛には、宗助以外に「身内のものが一人もなかった」と記されている箇所から、宗助には母親がいないことが分かるため、久兵衛は宗助の父親的な要素だけでなく、母親的な要素も持ちながら宗助に接していかなければならないことが推測される。久兵衛は、買い与えた絵本に宗助が気を取られてしまって歩く速度が遅いことに不満を持つ箇所から、宗助には自分の目の届く範囲で行動してほしいと思っており、危険なことが起こった場合にはすぐに助けたいという愛情があると考えられる。その一方で、久兵衛が心配していることを宗助に気付いてもらえず、しっかりついてこないことに不満を感じているのだと考察される。しかし、久兵衛は宗助を置いていくわけではなく、何度も振り返っては宗助が追いつくのを待っているため、宗助を大切に思っている感情が通じないことに対する不満はあるが、それでも守ってやれるのは自分しかおらず、見ていないところで転んで痛い思いをしたり、誰かに連れ去られたら宗助がつらい思いをするから避けたいという感情があるのだと考えられる。その後、久兵衛は宗助がついに転んだことで腹を立てて宗助を置いていってしまう箇所から、宗助の安全を考える思いも伝わっておらず、心配していた通りに宗助が転んで痛い思いをしてしまったため、あれほど注意していたのに、言うことを聞かずに勝手な行動をした宗助に対して父性的な愛情から怒りの感情が起こり、しつけの意味合いを込めて置き去りにしたと考察される。
宗助は転んで下駄の鼻緒を切った際、久兵衛に対して「すまないというような哀れな表情」を浮かべているが、久兵衛は怒りによって感情が昂ぶっているため、宗助の表情から反省しているのだということを読み取って許すという母性的な愛情を与えることが出来なかったのだと推察される。久兵衛は一度宗助を置き去りにするが、宗助に呼ばれたような気がして振り向いて探そうとすることから、腹が立って置き去りにして視界に子供が入っていなくても、意識は子供である宗助に常に向いており、宗助に危機が迫って自分に助けを求めるようなことがあればすぐに駆けつけて助けようと、視界には捉えられない宗助を聴覚で捉えようと注意を傾けており、宗助の身を守ろうと配慮していると考察される。
久兵衛が、宗助と思われる声を最後に見失ってしまうとき、柿の枝に残った最後の「一枚の葉」が「ヒラヒラと動いて」いる様子が描写されるが、この葉の「ヒラヒラ」と動く様子は、久兵衛の後を注意力が散漫な様子でついてくる宗助の危うい足取りを想起させる。また、たった一枚だけ残っている葉がさみしさを彷彿とさせ、宗助とはぐれてしまった久兵衛の心情を表現しているようにも考えられる。
次に、宗助が姿を消した後の場面へと目を向けたい。久兵衛は、宗助がいなくなって間もないころは鳥取の町の中にいるように思っていたため、自身の店で昼寝をしている際に、その夢の中で鳥取の町にいる宗助の姿を見た。しかし、久兵衛には旅に出て行く宗助の姿が幻のように心に映りだした。そのため、久兵衛は出雲や播磨にも人を使わせて宗助を探す。久兵衛の夢の中では、宗助はいつも苦しい思いをしていた。ある日、久兵衛は見た夢について語る。その夢では巡礼が登場し、彼が久兵衛に「諸国を遍歴なさりませ」、そうすれば仏様の力で宗助に会えると言ったとのことであった。
この場面で、久兵衛が宗助の夢を見ている理由について考えると、宗助は子供であるために動ける範囲が狭いと予測しており、まだ鳥取の町の中にいると考えていたことによると推測される。また、このような夢を見たのは、久兵衛が宗助のことを大切に思っており、宗助に再会したいという感情が大きかったからだと推察される。
しかし、久兵衛の願いに反して、鳥取の城下周辺では宗助に再会出来ないため、宗助がほかの土地に移動しているのだと考えるようになる箇所から、久兵衛は宗助が死んでいる可能性や、もう会えない可能性について考えることが苦しかったのだと考察される。久兵衛は、宗助に生きていてほしいという思いから宗助が旅に出る夢を見るようになるが、見る夢の中で、宗助は「荒くれ男に追い立てられ」て「大きな荷物を負って」苦しそうに旅をしていたり、「虐められて」いるため、生きていたならば旅の道中で恐怖を味わっていたり、孤独を感じているのではないかという、宗助の精神面が危険にさらされてはいないかという心配が起こり始めていると考えられる。
久兵衛が鳥取の城下外にも宗助を探させる理由は、宗助が生きていたならその苦しみから一刻も早く救ってやりたいという感情があるからだと考察される。さらに、久兵衛が「巡礼」の夢を見る理由は、宗助を心配しているのに見つからないため、諸国を遍歴して自身が徳を積むことで神仏の恵みによって宗助に会えるという思いが浮かび上がったためだと考えられる。
次に、久兵衛が巡礼に会う夢を信じて諸国を旅する場面に進むと、久兵衛はこの夢を信じ、宗助がいなくなってから半年ほどして旅に出ている。山陰道を但馬、因幡、出雲、石見の順にまわった後、山陽道を長門、周防、安芸、備後、備中、備前、播磨と進み、中国地方を一周する。そして三年目の秋半ばに四国の讃岐の国志度に渡る。久兵衛は志度で夢を見ており、その夢の中では、昔の夢とは違って宗助は苦しんでおらず、他国の海辺に落ち着いている。夢から覚めた久兵衛は夢の中での宗助の様子を見て、心が落ち着いた状態で旅が出来るようになる。久兵衛は、海の近くの一つの丘にたどり着くと、それが志度で見た夢の中で宗助が座っている場所に似た景色であったため、この村に宗助がいると考えて喜ぶ。しかし、実際には宗助はおらず、落胆する。
この場面を考察すると、久兵衛は自身の見た夢を信じて旅に出るが、道中で子供を見るとすべて宗助なのではないかと思うところから、久兵衛が一刻も早く宗助を見つけたいと焦っている様子が窺える。また、「チラリと角を曲って隠れる姿」に「殊に心をひかれ」るという点から、鳥取で宗助を見失ったときの情景が久兵衛の中に強く印象づけられており、視覚で捉えられている一瞬を逃すともう会えないのではないかという恐怖心があることが推測される。久兵衛の旅が三年目の秋半ばになる頃には見る夢にも変化が出ており、宗助が以前のように「苦しい放浪の旅をしなくな」り、「貧しい乍らも、兎に角生きて暮らしをつづけ」るようになる。久兵衛は、宗助が貧しくても生きており、つらい思いをしていないのだと考えられるようになって安心したため、自分が旅を続けていれば、いつかは宗助に会えるような気持ちになったのだと考察される。
また、夢に変化が起こった理由として、久兵衛が宗助の歩いたと考えられる土地を、宗助を追う形で旅の追体験をすることで、道中で見る景色の中の自然の雄大さや人々の優しさに触れることで安心し、宗助も同様に安全に旅を行ってどこかで生活が出来ていると考えられるようになったのだと考察される。久兵衛は、志度で見た夢の景色に似た土地を目指して旅を続けた結果たどり着き、宗助についに会えるのだと期待に胸を膨らませる。久兵衛は夢に出てきた土地に至るまでの道中で、「石の地蔵様」と「小さな観音」を見ており、地蔵は「街道の埃にまみれて、誰もこれを顧みる人が無かったので、石ころのよう」であったと描写されており、観音は「小さ」く「苔むし」ていると描写されていることから、久兵衛にとって「地蔵様」も「観音」も視界の隅で捉えてはいるが、特に気に留めるほどの存在ではないと考えていると推察される。久兵衛は村を訪ねるが、宗助はいないということを聞かされ、宗助に会えるものと思い込んでいたのに実際には会えなかったという事実に喪失感を抱いていると考えられる。
次に、久兵衛が宗助に会えなかった以降の動きについての場面を見てみたい。久兵衛は因幡の店にいたときに見た夢が仏様からのお告げだと思い、それを信じて旅をしてきたにもかかわらず、宗助に会うという目的を達成するための手がかりが無くなった。久兵衛は夢で見た景色と同じ樫の木の丘に戻ってきて食事をとっていないことを思い出してぼんやりと弁当を食べ、食べ終わった入れ物に残った飯粒を洗い流そうと近くにある小川に行くと、一匹の鮒が久兵衛の洗い流した飯粒を食べに来たのを見つける。久兵衛が、飯粒を食べている鮒を見ていると、一枚の木の葉が流れてきたことに鮒が驚いて、久兵衛の前から姿を消す。久兵衛はその鮒を見失ったと思うが、すぐに鮒が戻ってきて飯粒を食べ始めたため、その様子が可愛らしくて微笑を浮かべる。その際久兵衛の心の中で、木の葉一枚が起こす小さな影響によってでさえ、鮒を見失う可能性があるのだという考えが起こった。久兵衛は、木の葉と鮒の関係を通して、この世のどんなに小さなことでも、それが起こるまでには数え切れない沢山の原因があることに気がついた。そして、今この小鮒に会うということは、「千載一遇」とでもいうべきものなのだと感じて、懐から数珠を取り出して鮒に向かって手を合わせた。久兵衛が手を合わせていると、小鮒から金色の光が差し始め、その金の小鮒を中心として周囲に円く五色の光が散って、光は天にまで達した。久兵衛はその光に包まれて、立ち尽くしていた。
この場面の考察を行うと、久兵衛は宗助に会えなかったことで茫然自失に陥るが、ふと昼食を食べていなかったことに気がつく。しかし、「ぼんやりと」食べる様子から、自身の旅の意味について考え続けていることで食事に集中できずにいると考えられる。久兵衛は弁当箱を洗いに小川に行った際に一匹の鮒と出会うが、自身の旅によって得たのは鮒一匹との出会いであったのかと思い、「絶望のために笑」うことから、約三年もかけた旅とは易しいものではなく、宗助を見つけて再び共に生活したいという強い思いがあったからこそ出来た挑戦であったため、自身の旅の成果が鮒一匹であるということは、自身の苦労に見合っていないと考えていると推察される。しかし、そのように思う一方で久兵衛は、鮒との出会いについて旅の成果であると感じていると考えられる。その出会いが木の葉の影響によって引き裂かれかねない状況になったことで、自分が得た唯一の大切なものを失うことに繋がるため悲しいという感情と、そのような小さな出来事でさえ、大きな影響を及ぼす可能性があって大切な人との別れに繋がるということに世の中の無常を感じたと推察される。そして、久兵衛は鮒との出会いの重要性を認識した直後に、「考えが突然異」る。出会いと別れについて、この一匹の小鮒にめぐり合うためには、まずは三年の旅が必要なことであり、そして宗助がいなくなっていなければ旅に出ることはなかったのでこの鮒と会うことはなかったはずなので、自身の過去が一つでも違っていたら、また鮒も同様に鮒の過去に少しでも異なる点があれば、小川で弁当箱を洗っているところへ来ることもなければ、その飯粒を食べることもなかったため、自身と小鮒が出会うということは、とても奇跡的で尊いことなのだと、出会いに関する考えが変わったと考察される。
それでは、一枚の葉にはどのような意味があるのだろうか。鮒との出会いについて考えた後、久兵衛は、木の葉による影響についても考えており、木の葉が落ちるのが早すぎても遅すぎても、または木の葉が虫や風のような他の要因に阻害されて小川に落ちなかったとしても、自分と鮒の出会いは無かったかも知れないと感じることによって「この世のどんなに小さなことでも、それが起こる迄には数え切れない沢山の原因のあることが解った」という結論に至ったのだと考えられる。そして、宗助がいると考えていた村に至るまでに見た「石の地蔵様」と「小さな観音」の存在感は小さく、久兵衛の目にはっきりと認識はされていないけれども、久兵衛はそれらの神仏的なまなざしが存在し、自分を見守ってくれていることを無意識的に感じて、視界の隅に捉えていたのだと考察される。
この場面に登場する「石の地蔵様」と「小さな観音」にはどのような意味が託されているのだろうか。「石の地蔵様」とは地蔵菩薩を指しており、別名「クシティ・ガルヴァ」という。「クシティは「大地」、ガルヴァはさまざまなものを産み出す「母胎・子宮」のことで、(中略)民間信仰として子どもの守護や、旅人の道案内をする道祖神的な性格が与えられ」(注1)たとされているため、地蔵菩薩には母性的なまなざしで人間を見守る要素があるのだと推察される。また、「観音」は観音菩薩を指しており、「「観察することに自在な」という意味」(注2)があるとされている。「観察することに自在」とは、観音菩薩に万物を見守る要素があることを指しているのだと考えられる。これらのことから、どちらも久兵衛を見守るまなざしがある菩薩として描かれているのだと推測される。
久兵衛は最後の場面で、果たしてどういうことに気がついていっただろうか。久兵衛が少し落ち着いた様子でいるのは、「仏様のお告げとばかり信じて」旅をしてきたのだ、と旅の動機を振り返って、自身が神仏的な大いなる存在を無意識的に認識して夢を見たということを思い返すことで再認識したと推察される。また、村に到着する前に「お地蔵様」と「観音」を見ることによって、無意識的に自身が道中ずっと神聖で大きな存在に見守られている中で旅をしてきたということに気がついたと考えられる。この二つの出来事から、巡礼を行うことによって久兵衛の心に大いなる存在とつながっているという意識が芽生え、心が深まったのだと推察される。
以上のことから、久兵衛は旅をすることで、自分が大いなる存在からのまなざしを受けて、その加護の元生きているということに気がつき、小鮒との出会いを通じて、世の中の運命のような大きな流れの中で起こる一つの出会いとは「千載一遇」とでも言うべきであり、沢山の運命の連続の結果起こる奇跡的な事柄だということに気がついたと考えられる。そして、出会いに対する別れとは、たった一枚の木の葉が引き起こすような小さな現象によってでも起こり得る出来事なのだということに気がついたのだと推察される。また、久兵衛が宗助と別れる場面でも一枚の葉の描写があるが、その時にはその葉について全く気に留めていないことから、この一枚の葉に対する価値観の変化は、久兵衛が巡礼をおこなったことで得た重要な視点であるといえるだろう。
ここで最後の場面で五色の光が描かれている象徴的な意味について探りたい。出会いの重要性に気づいた久兵衛が、数珠を取り出して「鮒に向かって手を合わせる」に至る心境は、宗助を求めて巡礼を行うことを通して、自分の周りで起こっている全ての出来事が自分の出会いと別れ、そして運命を作っており、それらの現象は神仏的な存在によるまなざしのおかげで起こっていることに気づいて尊さを感じ、そのことに気づかせてくれた鮒に有り難みを感じているためであると推察される。また、数珠は「ブッダや菩薩を礼拝する時に手にかける小さい珠をつないだ輪」(注3)であるので、久兵衛が数珠を取り出して鮒に手を合わせようとする心境は、菩薩に祈る思いに近く、小鮒に大いなる存在のはたらきを感じたことによると考えられる。久兵衛が手を合わせると、小鮒が金色に光ったように見えており、「金の小鮒を中心として、周囲に円く五色の光が散って、光は天に迄達し」たという描写から、小鮒が金色に光っているように感じた理由は、久兵衛にとって小鮒が自分の周りの全ての現象に大いなる存在のはたらきがあることに気付かせてくれたきっかけとなったことで尊さを感じて、かけがえのない存在として認識されたことによるのではないだろうか。
それでは、「五色の光」とは何を表しているのだろう。五色は「五正色・五大色ともいう。青・黄・赤・白・黒の基本色」(注4)であるとされているため、久兵衛の周囲で、仏教における青・黄・赤・白・黒の五色の光が散っていると感じたのだと推察される。久兵衛は、旅のはじめは宗助を見つけることが目的であり、宗助に会うことが救済であった。しかし旅を通して鮒に会うことで大いなる存在のはたらきに気がつき、大いなる存在によるはたらきだけでなく、まなざしも受けていることを知り、この五色の光が感じられたことで精神的に救済されたと考えられる。「円く」散るという表現は、仏教における円に「完全なこと」(注5)という意味があるため、久兵衛が大いなる存在とのつながりを認識することによって心が満たされた状態であることを表していると推測される。
それでは、その五色の「光が天に迄達」するという表現に込められた久兵衛の心情について考えたい。天には「天の神。天界の神」(注6)という意味があるため、久兵衛が神に見守られていることに気がつくことによって、久兵衛のまなざしも天にいる仏へと向いて、大いなる存在とのつながりを確認できたのだと推察される。そして、「その光に包まれて」「立ちつく」すのは、久兵衛自身も大いなる存在の恵みを受けており愛されている一人であるため、大いなる存在の加護の範疇に自分もいるのだという実感が持てたため、自分の命そのものも、恵みの光に包まれた状態になったのだと考察される。
これまで久兵衛が巡礼によって大いなる存在のまなざしに気付くという展開について作品の考察を行ったが、その背景にある作者坪田譲治自身の宗教観についても考えてみたい。坪田家の家の宗教は仏教であるため、幼少期は譲治も仏教信仰の土壌の中で育った。しかし、譲治が16歳のときに兄がキリスト教信者となり、17歳のときに兄がアメリカ留学から帰国して家庭内にキリスト教の雰囲気が持ち込まれ、譲治は兄の祈る姿を見るようになる。そして、兄によってもたらされたキリスト教への関心がきっかけとなり、譲治はより寛容さを持つキリスト教の一派であるユニテリアン教会で、22歳のときに洗礼を受ける。このことから、譲治は仏教とキリスト教の垣根を超えた、大いなる存在を重視する価値観を持っていると考えられる。また、譲治は幼いころから魚や鳥といった小さな命を愛しており、柿の木に実がなるなどの自然がもたらす恵みに対する視点も持っていたため、小説「一匹の鮒」は、そのような譲治によって感じられた神や仏という言葉だけでは表すことのできない大いなる存在とのつながりが描かれ、自分を取り巻くものの全てに大いなる存在のはたらきかけとまなざしが存在しているという恵みが表現された一作であったといえるのではないだろうか。
引用文献
(注1) 藪内佐斗司『ほとけさまの図鑑』(小学館 2015年7月5日)
(注2) 速水侑『観音信仰事典』(戎光祥出版 2000年1月25日)
(注3) 中村元『広説佛教語大辞典 縮刷版』(東京書籍 2010年7月8日)
(注4) (注3)に同じ
(注5) (注3)に同じ
(注6) (注3)に同じ
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763