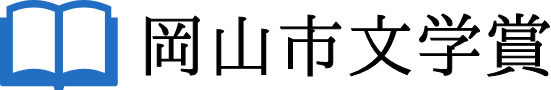「武南倉造」―明治時代の「エンピツ」に注目して―
(初出 雑誌『童話教室』昭和23年3月号)
(収録本 『坪田譲治全集第9巻』 新潮社 『坪田譲治名作選 ビワの実』 小峰書店)
ノートルダム清心女子大学 3年 田中希実
童話「武南倉造」の舞台は、明治34年の岡山県御野郡(現・岡山市北区)にあった御野高等小学校である。まず、あらすじを紹介しておく。主人公「わたし」(丈二)は島田という農村に住んでおり、同高等小学校の1年生である。ある日、丈二は海や山の村に住む友達3人に、家の土蔵にあったエンピツをあげることを伝え、その代わりに、地域の特産物である丹波栗や千本シメジ、ほおじろやタコの子どもをもらうという約束をする。しかし、3人の友達は約束のものをいっこうに持ってこないのだった。そのような状況を知ったクラスメイトの武南倉造は、約束を守らない3人が気に入らず、彼らに手を出してしまう。武南がそこまで躍起になるのには、自分の先祖がだまされて、本来は武南家のものであった山を奪われてしまったという悔しい過去を知ったことにあった。それから武南は人をだます人間を許せないという思いを持つようになったのだということを、丈二は知るのだった。
その小学校生活では、エンピツが登場するのであるが、私は現代では筆記具として当たり前の存在である鉛筆が、この作品で描かれた時代においては子どもたちにとってまだあまり手に入らない製品であったのだと感じられたため、現代と当時との鉛筆に対する捉え方の違いと、エンピツをめぐる子どもたちの心理に大変興味を持った。また、家の蔵にあったエンピツは、おじいさんが語るところによると、「わたし」の父親が試作品として作った鉛筆であるということがわかる。さらにその話では、父親がエンピツを製造し普及させる苦労や、子どもたちの「エンピツ」に対する様々な心理が描かれていることが強く印象に残った。そこで、私は「エンピツ」に着目してこの作品を読み深めたいと思う。そのために、私は日本でのエンピツの普及までの歴史や、岡山県で初めてエンピツが製造されたと思われる年、また、子どもとエンピツとの関わりについて調べることで、さらに「エンピツ」をめぐる子どもたちの思いや関係性について考えてみたい。
まず、「武南倉造」という作品は、坪田譲治自身の子ども時代を反映させた実話に近い話になっているということが以下の2点から分かる。1点目は、作品の舞台である御野高等小学校は譲治が実際一年間通った小学校であるということである。「丈二」という名前も、譲治は自分の名の音に通じることから採用し、自らの経験や思いを丈二に託したと思われる。2点目は、作中に出てくる「わたし」のおとうさんが発明家で、石油ランプの芯をつくっているという記述があるためである。実際、譲治の実家は島田製織所を営んでおり、ランプ芯やろうそく芯をつくっていた。よって、作中のおとうさんとは、譲治の父であり8歳のときにすでに亡くなった父坪田平太郎が反映されているといえる。
そこで、「エンピツ」に注目してみると、まず作中では、丈二のおとうさんが手掛けた製品の数々のなかに「エンピツ」が含まれていることが描かれている。さらに、おとうさんは明治20年ごろにエンピツをつくったが、「しっぱいしたのです」とある。この点からは、鉛筆が当時の岡山県において、エンピツの製造も普及も一般的ではないことが分かる。また、エンピツ製造に関して、おじいさんの言った「いちどになん十本ももってくでないよ。あれでおまえ、おまえのおとうさんが苦心して、つくったものなんだ」「うちの相当あったたんぼも、エンピツ製造のため、半分も売りとばしたのだ」という言葉にも注目したい。
先ほど述べたように、作中では、おとうさんは明治20年ごろにエンピツをつくったことがあったという記述がみられたことから、私は明治20年ごろという年代を手掛かりに資料を調べてみたところ、佐藤秀夫著『ノートや鉛筆が学校を変えた』(1988年、平凡社)のなかに掲載されていた資料から、明治23(1890)年、すなわちちょうど譲治が生まれた年に東京上野公園内で開催された第3回内国勧業博覧会において、エンピツを出品した人のなかに、坪田譲治の父坪田平太郎の名を見出すことができた。つまり、同書では、『第三回内国勧業博覧会出品目録』の内容が紹介され、全国でわずか10人の出品があったなかで、岡山県から出品した一人として、「鉛筆 一件 備前国御野郡石井村 坪田 平太郎」という記述が記載されているのである。しかも、さらに同書に揚げられた次の表では、譲治の父平太郎は、同博覧会の第1回から第5回までの間を見ても、岡山県ではただ一人のエンピツの出品者であり、全国的にもエンピツ製造を試作の時代に着手していた先駆けの存在であったといえる。
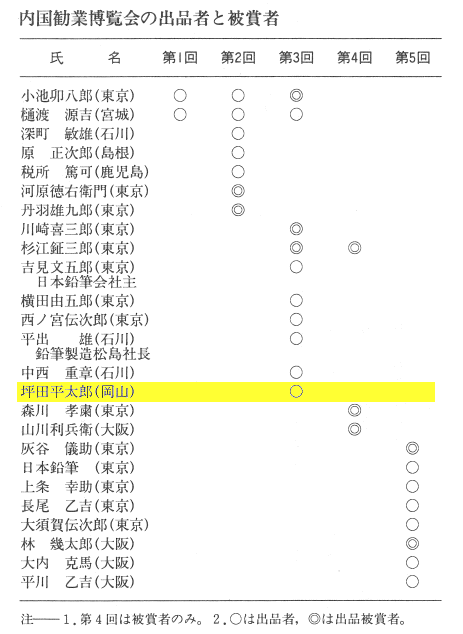
佐藤秀夫著『ノートや鉛筆が学校を変えた』(1988年8月 平凡社)より
ただし、この表では、譲治の父平太郎が出品したのが第3回の明治23年のみであることがわかり、第4回以降の同博覧会には一切参加していないという事実は、作品に書かれている「エンピツもカンヅメもいまはもうやっていません。しっぱいしたのです」という箇所に反映されているといえる。作中にあるおじいさんの言葉では、お父さんがエンピツ製造のためにたんぼの半分を売ったという事実や、「おまえのおとうさんが苦心して、つくったものなんだ。しんはまだたいしたことはなかったんだが、そとがわの木のいいのがなくてねえ。苦心さんたん、北海道のほうまでさがしに行ったんだ」ということが語られており、これから先もそのようなことを続けていくとなると、相当な時間や金額がかかることから、エンピツの需要も少ないことを考えた結果、やむなく製造中止に至ったのではないかと解釈される。また、おじいさんは、そのような経緯を知っているからこそ、エンピツは「わたし」のおとうさんが苦労してつくった力作であるので、簡単に人の手に渡らせたくなく、大切にとっておきたい宝物のように思っていることが分かる。それは、おじいさんが、何百本という数の未完成のままのエンピツを「わたし」の家の土蔵の隅にずっと保管しているという行動からも読み取ることができる。
では、なぜ明治23年当時、鉛筆は人々の生活に定着しなかったのだろうか。その理由を同資料によってみると、当時は最も主流とされていた筆記具が毛筆であったことがわかった。それは、平太郎も出品した第3回内国勧業博覧会における鉛筆の出品数の割合がわずかであることからも明らかである。
もっともそうはいっても、この第三回内国勧業博覧会の第一部第八類の全出品数三〇五〇点に占める鉛筆は三八点、石筆一三点、白墨は二八点といずれもごく少数に過ぎず、残りの二九七一点、約九七・四パーセントは実に伝統的な毛筆であった。鉛筆は辛うじて一・二パーセントを占めるに留まっていた。一八九〇年時点での「教育」用品を含めた筆記具の主流は、まだ圧倒的に毛筆が占めていたのである。
(佐藤秀夫著『ノートや鉛筆が学校を変えた』1988年、平凡社)
このように、第一部八類の全出品数において、毛筆の割合は約97.4%であったのに対し、鉛筆はわずか1.2%という結果だったというのだ。また、日本では子どもの学校の筆記具として長い間毛筆が用いられていたようだ。言うまでもなく、毛筆に最も適しているのは和紙である。同資料によると、資料によると、1912(明治45年)までは、日本における和紙の生産額は洋紙よりも和紙のほうが上回っていたという状況であることから、和紙に書くには適していない鉛筆は筆記具として定着しなかったということもわかる。
さて、こうした「エンピツ」をめぐる当時の状況のなかで、作品中では「エンピツ」は子どもたちにどのように受けとめられ描かれているだろうか。まず、農村に住む「わたし」は、「山の子ども、海の子どもの話をきくと、めずらしいことばかりで、とてもうらやましく、そのもってくるものにしても、ほしいものばかりでした」とあり、海辺や山沿いに住む子どもたちがお弁当に持ってきていた、その土地特有の食材であるカキにハイガイ、栗やきのこ、ワラビやゼンマイやタラの芽などの煮つけなどを特別な思いで見つめているのである。つまり、そのような珍しいものに対して、これなら相手も目を見張るだろうと思い交換に値する価値のものとして「エンピツ」を持ってきているといえよう。実際、作品では、「わたし」が学校の友達にエンピツを見せると、あっという間に友達の手に渡っていったという描写がなされている。こうして、丈二は父のおかげでエンピツを持っていたが、他の子どもたちにとっては、エンピツが普及していないために、珍しいと捉えられたおかげで、丈二がうらやましく思っていた海や山の産物との交換の駆け引きが始まり、子どもなりの心理戦が生き生きと展開される話となっているのだろう。
以上のように、本作品を、「エンピツ」をめぐる当時の事情に着目して読むと、エンピツの珍しさや、普及に至るまでの過渡期においてエンピツ製造の苦労が読み取れた。また、そこから子どもたちにとってのエンピツを手にできることに対する喜びがいかに大きなものであったかということを、感じることができた。新しいものや周りの人が持ち得ないものに好奇心がそそられるという体験は、私にも覚えがあることであり、そのような〝特別感〟は、特に子どもにとって大変うれしいものであろう。私は、「武南倉造」という作品において、その時代には珍しいものや、その地域では手に入りにくいものをめぐって、子どもたちがお互いに微妙な心を働かせあいながら関係を作っていく心理が生き生きと描かれているように感じた。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763