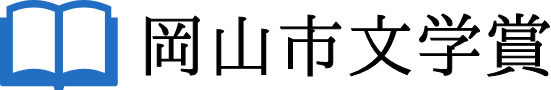大石真を導いた坪田譲治
ノートルダム清心女子大学 4年 近藤加菜
私が初めて大石真(大正14(1925)年-平成2(1990)年)の作品に触れたのは、小学校3年生の時である。担任の先生が帰りの会で毎日読み聞かせてくれたのが、大石真の「チョコレート戦争」だった。この作品は、町で有名な洋菓子屋「金泉堂」のショーウインドーを割った犯人にされた光一と明が、子供だからといって聞く耳を持たない分からず屋の大人たちをぎゃふんと言わせる為、画策するという内容である。子ども同士のやりとりから、ショーウインドーの中のチョコレートの城を盗み出すという計画が生まれたり、学校新聞で金泉堂が明たちの言い分を全く聞かなかったことを記事にしたりと、子どもならではのコミカルな発想が生きており、子どもの等身大の心理が描かれている。読み聞かせるにはそれなりに長い作品であるが、飽きることもなく、毎日光一や明がどのようにして大人たちを見返してやるのだろうかと続きが気になって仕方がなかったことを覚えている。
時が経ち、大学で卒業論文を書くにあたり、何を研究していくかと考えていた時にふと、この「チョコレート戦争」を思い出し、大石真を研究してみたいと思い始めた。それは、大学に入り近代文学の授業を受けるなかで、初めて坪田譲治を知ったことがきっかけだった。譲治は岡山市出身の作家であり、舞台が岡山である作品が多いことや、子どもの死が描かれている作品が複数あるということなどから、私は譲治の作品に興味を持った。さらにその授業で、譲治と大石は師弟関係にあることを知り、この二人のつながりについて具体的に知りたいと考えた。
まず、大石は昭和19(1944)年19歳の時に、第一早稲田高等学院理科に入学し、早大童話会に入会した。これは、早大童話会の顧問として、かつて大石が愛読した『子供の四季』の著者坪田譲治の名が挙がっていたためである。大石は、譲治の作品との出会いについて、次のように語っている。
小学校を卒業して中学に入学したとき、近所の大学生がお祝いに『子供の四季』という本を買ってくれた。普及版の一円だかの本であるが、これが先生の本との最初の出会いである。この本を読んだときの感動は今も忘れ難い。ぼくはそれを読んで、これまで味わったことのない世界に心が誘われるのを覚えた。読み終えると、ふしぎな楽しさで満ちたりた気分になった。
(『坪田譲治童話全集14 坪田譲治童話研究』1986年10月 岩崎書店)
ここから、大石は少年時代に譲治の作品を読み、不思議な読書体験をし、大変感動していることがわかる。この感動を大石は忘れることができず、譲治が早大童話会の顧問であることを知り、入会を決断したのである。この言葉に続けて、大石は『子供の四季』において、印象に残っている場面を細かく語っている。そのなかに、次のような文章がある。
なかでも、奇妙に記憶に残っているのは、父親の病気で、母も看病に病院に行き、善太、三平だけが夜家で寝ているとき、心配して、小野のおばあさんが訪れて来る場面である。夜中に玄関の戸を叩く音がするので、兄弟はそれが何者だろうか、といぶかる。三平は話に聞いた山姥ではないか、と心配する。そして、小野のおばあさんの声であることが分かって、ふたりは大よろこびで玄関にとび出して行く。その次に、作者の文章がカッコ付きではいっていて、(ところで、そこにだれが立っていたろう。実はこの時作者は妖姥の姿を思い浮かべて、ゾッとしたのである。しかし、立っていたのはそんなものではない。善太三平をどうしてそんな不幸に会わせることができよう。父、青山一郎が重態に落ちているのに。)
この文章を読んだとき、十三才のぼくは、見知らぬこの作者に羨望を感じた。この物語世界が作者の考え一つで、どうにでもなるのだと知って、それがまぶしいほどにうらやましかったのである。
こうして、大石は譲治の『子供の四季』を読んだことで、文学創作のおもしろさを感じ、童話を創作したいと考えるようになったといえる。大石は早大童話会入会後、昭和22(1947)年22歳の時に早稲田大学英文科に入学し、23歳の時に譲治の紹介で寺村輝夫と共に小峰書店編集部にアルバイトとして勤めるようになり、昭和25(1950)年25歳の時には大学を卒業し小峰書店の正社員となった。その後、児童文学者協会新人会の機関誌『児童文学研究』第8号(1952年8月)に短編「夏の歌」を、早大童話会20周年記念号(1953年9月)『童苑』に短編「風信器」を発表するなど創作活動を続け、童話に限らず、絵本や翻訳、伝記の執筆なども行った。昭和26(1951)年には早大童話会のOBによる同人誌『びわの実』が創刊され、これに大石も何篇か作品を発表している。このように早大童話会とのつながりは絶えず、昭和38(1963)年大石が38歳の時、譲治が編集発行人を務める童話雑誌『びわの実学校』が創刊された。この『びわの実学校』に大石は、童話「光る草」(読み切り)、「教室二〇五号」(連載)、「テングのいる村」(読み切り)、「眠れない子」(不定期連載)、「桃太郎」(読み切り)、「青い窓」(読み切り)や随筆「私の処女作」、「追悼坪田譲治・思いだすことのいくつか」を発表した。昭和57(1982)年に譲治が逝去した後は、譲治の弟子たちによって『びわの実学校』が引き継がれ、『季刊びわの実学校』として発行が継続されるなか、大石は引き続き編集同人となり、昭和63(1988)年には編集長となっている。なお、大石が『びわの実学校』で連載していた童話「眠れない子」は『季刊びわの実学校』にて完結した。
さて、譲治は、『びわの実学校』において、大石の作品について幾度かコメントしている。ここから譲治の大石の作品への評価のありようや大石への思いが浮かび上がってくるように思われる。そこで、童話雑誌『びわの実学校』での譲治の大石に対する評価の言葉に着目してみたい。
『びわの実学校』第28号の「編集後記」(1968年4月)にて、譲治は大石の作品「風信器」の評価や大石の人柄について次のように述べている。
この作品はいって見れば、大石真の代表作というばかりではありません。今頃の少年小説といわれる作品の代表作です。(中略)
「なるほど、これこそ、近代文学であるところの少年小説だ。」
「風信器」をよめば、そう思わないではおられません。おとなしい大石真からは、この「風信器」について、一言も聞いたことはありません。発表されてから十五年にもあるのに、聞いたことがないのです。然し、「風信器」の前に時代の子供を描いた作品が一つもなく、後に風信器ふうの作品が雲の如く起こったということは忘れてはならないことです。この作品は戦後と云われる昭和時代の影をうつした紀念作として、永く児童文学史に残るものと思います。(中略)
未明先生、大石真、この二人には、語るほどの逸話はありませんが、人の良さは、尾崎さんにおとりません。つまり笑顔の良さは、この心の底までそうかと思われる善人の笑いということでしょう。
この引用文から、譲治は大石の「風信器」を少年小説の代表作であるとし、時代特有の少年の心を描いた作品として非常に高く評価していることがわかる。譲治が「風信器」を「時代の子供を描いた作品」と評価するのは、弘の家庭の事情による苦しさやぼくの弘への思いが少年の視点から描かれており、どうすることもできない社会状況に置かれた子どもの心理をまざまざと浮かび上がらせると共に、二人の仲に芽生えた友情を感じ取ることができる作品となっているからだと思われる。譲治はこれらの点から、「風信器」を近代文学でいう少年小説だと評したのではないだろうか。
また、この引用文中の「未明先生」とは、譲治の小説の先生であった小川未明であり、「尾崎さん」とは、譲治の友人である尾崎士郎である。譲治は、大石の人柄と心の底からあらわれる笑顔の魅力について、自らの師である小川未明と並べて、長年の友人である尾崎士郎の人の良さに劣らず素晴らしいと評価している。このように譲治は、大石の作品を児童文学史にも残る名作と考えていたとともに、人柄も認めていたということがわかる。
さらに、雑誌『びわの実学校』52号の「編集後記」(1972年4月)でも、譲治は「風信器」について、「そこには現代少年の世界があり、少年の体温が感じられ、少年の息づかいが伝って来るのです」と書いており、大石の作品を読むことで、少年の体温や息づかいをまざまざと感じるというリアリティを評価している。
その上、譲治は雑誌『びわの実学校』36号「編集後記」(1969年8月)において、大石の童話「チョコレート戦争」とともに童話「教室二〇五号」について評価し、次のように書いている。
大石君という人は、自分の作品に対して、無類にきびしい人なんです。(中略)第一稿で、作品が完結しても、直ぐにそれを本にしようとは致しません。ジックリ考え込むのです。そしてアッチを直し、コッチを変え、殆ど全部を書き直すくらいにして、本として出版するのでした。(中略)
「なるほど、やっぱり、うまいものだなあ。」と、私はタメ息をついたのです。前に、「チョコレート戦争」という大石作品を読んだ時、私は全く感心して、大石君に旅行先の伊豆の下田から速達を出しました。
「感心しました。これほどウマイと思った作品は、吾国の長編童話中で私にとっては初めてのことです。はるかに脱帽致します。」
そんなことを書いたのですが、今度の二〇五号では、大石君のウデがもう一段上がったように思われます。(中略)
とにかく、現代と言う世相の中の子供を描いて、これほど自然でこれほど人を感動させる作品は、現代中堅作家中、そう沢山はありません。
譲治は、作品が完結しても単行本での出版をする前に、推敲し、書き直すという大石の姿勢を見て、大石を自らの作品に厳しい人物と評し、そのような過程を経て出来上がった作品「教室二〇五号」についても、かなり深い評価を示し、大石の創作の腕が上がったとしている。したがって、譲治は大石の作品を年代ごとに見ていき、その成長ぶりを見守り、作品を読んで素直に感動しているということがわかる。私は、この譲治の言葉を読んで、小学生時代に読んだ、大石の「チョコレート戦争」において、光一が金泉堂の大人たちにショーウインドーのガラスを割った犯人にされたままではいられないため、金泉堂の看板であるショーウインドーのチョコレートの城を盗み出し、大人たちをあっと言わせようという計画を明に話す場面が思い起こされた。私はその場面を読み、子ども心に自分も光一にその計画を告げられている気分になって、胸が高鳴ったことを思い出したのだ。その場面で光一は、重大な話があると言い、明をデパートの屋上に連れ出した。そして、光一は明にチョコレートの城を盗み出す計画を話し、その計画には最低五人が必要だと言う。光一は自信たっぷりにその計画を話すが、明はその計画に驚き、そんなことはできるわけがないと感じていた。
そこで、次に、明が光一にチョコレートの城を盗み出すという計画を聞いた直後の場面を引用する。
ぼくは、いやだ。そんな、ばかげたことにくわわるのは、ぜったいに反対だ!
「名前は、まだ、いえない。でも、その五人にたのめば、みんな、よろこんでやってくれると思うんだよ」
「ぼくも、そのなかに、はいっているのかい?」
おっかなびっくり、明はたずねた。
「きみは、だめだ」
キッパリと、光一は、いってのけた。
「えっ、なんだって?」
「きみは、その仲間には、はいれないよ」
「どうしてだい!」明は、さけんだ。
「なぜ、ぼくをいれないんだい?」
「だって、きみは弱虫だものね」
「弱虫だって……」
いいながら、明は、まっかになった。胸のなかを、すっかり見とおされたようだった。
(『チョコレート戦争』1979年11月 理論社)
この場面は、光一の計画に驚くと同時に無理だと言い、正義感からやりたくないと思いながらも、自分も仲間に加わり、大人たちを見返したいとも感じ、心の中で葛藤している明の心が子どもらしい言い回しで表現されている。前述したように、私がこの場面を読んで、自分も光一に計画を告げられている気分になって、胸が高鳴ったという感情は、この明の揺れ動く気持ちが、子供にも伝わるような簡潔で柔らかい言い回しで、生き生きと表現されていたからであったのだと、譲治の言葉に納得される思いになった。
以上のことから、譲治と大石の関係について考察してきたことをまとめていきたい。譲治と大石の関係は、大石が譲治の作品の、登場人物の心理に寄り添い、子どもの視点に立って作者が物語を進めていくというあり方に感化され、童話創作を志したことから始まった。また、譲治は大石の作品を読み、子供同士のやり取りを通して、子供の繊細な心理がわかりやすく丁寧に表現されていることや、家庭の貧困や両親の離婚、生まれつきの障害などのその時代の社会の中で揺れ動く少年の心が、読む人の心に素直に浮かび上がってくるリアリティ溢れる描写で描かれているということを高く評価していたことがわかった。
今後も大石真論を卒論で展開していく中で、大石が譲治作品や譲治の言葉から導かれた童話創作の要素を確認し、大石の作品に今回考察したような譲治の評価のポイントがいかに描かれているのかを注視して読んでいきたい。
参考文献
・『現代児童文学作家対談4 今西祐行 大石真 前川康男』(1988年12月 偕成社)
・『日本児童文学大事典 第1巻』(1993年10月 大日本図書)
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763