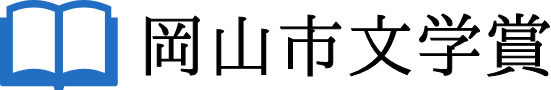桃の実
山の林の中に一本の桃の木がありました。その一つの枝が道の方へずっとさし出ていました。道といっても、そこから二十メートルもありました。その枝に大きな桃の実が五つ、一かたまりになってみのっていました。りっぱな桃、美しい実だったのです。桃の木はそれがじまんで、わざと枝を道の方にさし出しているかと思えるほどでした。しかし花のようにきれいで、赤ちゃんのようにかわゆく見えましたので、誰もこれをとって食べる気はありませんでした。
ある日のこと、道を三人の子どもが通りかかりました。みよ子と四郎と八郎です。三人はきょうだいでした。
「アア桃じゃ。」
八郎が一ばんに見つけました。三人は木の下へかけて行き、しばらくはものも言わずに、じっとその実を見あげました。
「どうして、ここに、こんな桃があるんじゃろう。」
まずみよ子が言いました。
「あの桃、姉さん、食べられんぞな。きっと。」
八郎がゆびさして言いました。すると四郎がいうのでした。
「人間は、えんりょしてとらないけど、山からきつねなんぞ出てきてな、オット、ええ桃があるなんぞいうて、食べてしまやせんじゃろうか。」
と、八郎が言い出しました。
「ウウン、おれ思うな。あの桃、てんぐの桃なんぜ。鼻のたかあい、てんぐがいるだろう。あれが山からとんで来て、これは不老不死の桃であるなんかいうてさ、あれを枝ごと折りとって、遠くの山へとんで行く。そしてそこの岩のてっぺんのてんぐのすの上へ友だちを集めてな、これはうまい、ワッハッハなんて、大笑いしながら食べるんぜ。そんな桃じゃな、この桃、な、そうじゃろう。」
みよ子がいいました。
「だけど、姉さんはちがうな。」
「どうちがうん。」
八郎がききました。
「姉さんはてんぐの桃でも、きつねの桃でも、あの桃ほしいと思うん。」
みよ子がいうと、八郎がいうのでした。
「食べると、鼻がてんぐのように高くなるぞな。」
みよ子がホッホと笑いました。そして、
「食べやせんよ。あのたねをうちの庭にまいて、桃の木をはやすんじゃ。枝でもええわ。他の木につぎ木をするから。そうすると、この桃の木が生えて、こんな桃の実がなろうがな。その下に池をつくるんじゃ。そしてその池にふなやこいをいかすの。そうすると、水の上に枝がつき出て、それにこんな桃がなろうがな。すると、その下にこいやふなが集まって来て、アア、オイシイ、アップ。オオ、ウツクシイ、アップいうてな、水にうつった桃の実をどんなに喜んで食べるじゃろう。きれいじゃなあ。小さい虹なんぞ、その池の上に立ち、その虹の上に小鳥が来てとまりそうにしたりするぞな。」
そんなことをいうのでした。これをきくと、八郎は言いました。
「姉さんのバカ、そんなことをしたら、そのさかなみな鼻が高くなって、てんぐざかなになってしもうて、羽なんぞ生えてきてな、バタバタって、池からとび立ち、みんな山へとんで行ってしまいますぞな。」
これを聞いて、みよ子と四郎は、
「ハッハッハ。」
「ホッホッホ。」
と笑ってしまいました。しかしみよ子はながめればながめるほど美しい桃なんで、上の枝をあかずながめつづけました。
するとこんどは四郎が、
「行こうな、姉さん、みんなてんぐにならんうちに行こうな。鼻が高くなったら大へんじゃないかな。」
と、せきたてました。
「そうじゃ、そうじゃ。きつねが出て来て、おれたちばかしても大へんじゃからな。もう少しばかしかけているかも知れんぞな。」
八郎がいいました。と四郎が、
「そうじゃ。ばかしかけておるんぞな。それでこの桃こんなにきれいに見えるんぞ。きつねの桃じゃ、この桃。ばけ桃じゃ、この桃。そうれ、きつねが出てきたあ――。」
そういってかけ出しました。みよ子も八郎も、これで一ぺんにこわくなり、ころげそうに道へ走り出て、ワッハッいいながら逃げて行きました。
ところで、それから間もなく、道を一人のおじいさんがやって来ました。どこかの帰りでしょう。てんびんぼうを一本、てっぽうのようにかたにかついでおりました。そして、何かブツブツひとりごとをいっていました。
「こんなにヒデリがつづいちゃ、ことしの稲もしんぱいだな。」
そんなことをいっていたのかも知れません。いやいや実は今、おじいさんはたんぼのクロでもぐらもちを見つけたのです。それがクロの中に穴をあけ、そこから新しい土をさかんにかき出していたのです。そこでおじいさん、
「このやろう、そんなことをしては、たんぼの水が出てしまうじゃないか。」
そう大おこりにおこって、てんびんぼうでそのもぐらもちをポーンと遠くにはねとばしました。もぐらもちは遠くの道の上におちましたが、あわててチョロチョロと走り出し、すぐ草かげの穴の中にもぐりこんでしまいました。それでおじいさんはブツブツ小言をいいながら歩いて来たのです。すると桃です。きつねのばけたような、てんぐの食べるような桃がなっていたのです。で、おじいさんは、
「何じゃ。」
そういって、桃の木の下へ近づいて行きました。そして、
「フーン。」
と、ためいきをついてながめいりました。それから
「なるほど。」
と、感心してしまって、桃を見あげたまま、動こうとしませんでした。しばらくそうしていたのち、おじいさんはその桃の木にせなかを向け、枝の下の草の上にドッカリこしをすえました。てんびんぼうはそばに横たえ、立てた両足の間に首をたれ、おじいさんは何かすっかり考えこんでしまったのです。
どうしたのでしょう。
むすこさんのことを思い出したのです。むすこさんは三年前、しょうしゅうされてへいたいに行きました。そして一枚――お父さんどうか元気にやってください。――というハガキをよこしたきり、今にどうしているかわかりません。近頃かえって来た同じ村のふくいんへいの一人の話では、ごうしゅうに近い小スンダ列島という島々の一つに、きっとまだ残ってるだろうということでありました。しかし三年もたよりがないので、生死のほどはまったくわかりませんでした。
ところが、このごろふくいんのへいたいさんが次々と帰って来るものですから、おじいさんはむすこのことが思われてしかたなくなりました。むすこにあいたく、むすこの顔が見たく、その話がききたく、その笑いごえが耳にしたくて、ならないのでした。今もこの美しい桃を見ると、フッとむすこのすがたが目に浮びました。それもむすこが死んでるようには思えなくて、生きてるすがたばかりが目に浮びます。
「スンダ列島というのはあついところというそうじゃが、今ごろどうしていることじゃろう。」
そう思うと、おじいさんが今こうして、両足の間に頭をたれているすがたがむすこのように心に浮かんで来ました。そうだ、むすこは今ごろこんなにてっぽうを草の中にほうり出し、やしの林の中か、コーヒーの木の下に、こんなにして国のことを思っているだろ、そう、そうにちがいない。そう思った時、プーンと、桃のにおいがして来ました。ああ、いいにおいだ。おじいさんはそのにおいを鼻一ぱいにすい込んで、むすこに一目こんな桃を見せてやりたいものだ、そんなことを思いました。
その時です。近くに話しごえがして来ました。顔をあげると、道に三人の青年が立っていました。村の若いしゅうです。一人がせなかに何かおうております。赤くテラテラ光ったものです。三人は立ち止まってこちらを見ております。
「や、桃がなっとるぞ。」
「ウン、キレイな桃じゃなあ。」
三人はそういうとおじいさんの方に歩いて来ました。
「おじいさん、どうしました。」
一人がいいました。その時見ると、せなかにおうているのは、ししまいをする時かぶるあのししがしらでした。そこでおじいさんは、
「ししまいでもやるのかね。」
と、ききました。
「そうです。雨が降らんので、近く雨ごいをやるんじゃそうです。夏祭りをかねてな。それで今からこのけいこをするんです。」
一人がいいました。
「フーン。」
「おじいさんも若いころししまいはずい分うまかったそうですな。」
「ウン、一時それにこってな。方々の村へたのまれて行ったこともあるぞ。」
「へえ。」
そんなことをいいながらも、三人は桃をながめつづけておりました。と、中の一人が、
「オイ、ここで一つ、一おどりやって見ようじゃないか。おじいさんにも見てもらおう。」
そういいました。
「ここでか。こんな山の中でか。」
「いいじゃないか。ちょうど桃なぞもあってな。中々いいけしきだ。ぶたいとしてもってこいだ。」
「じゃ、やっつけよう。おじいさん見とってください。」
そういうと、一人がさっそくそのししがしらをせなかからおろしました。一人はたいこをおろしました。一人は笛をこしからぬきました。
「ピューッ。」
笛が鳴り出しました。
「トントコ、トントコ。」
たいこも鳴り出しました。
ししがしらは頭の毛を一ふりすると、キッとばかりに勇しくみがまえました。それからたいこと笛の音につれて、頭をゆりゆり、あちらに行き、こちらに行き、上をあおぎ、下にうつ向き、パクパク大きな口を開けたりふさいだりして、面白くおどり始めました。桃の木のまわりを歩いたり、桃の実に向いてのびあがったり、大きなその金の目を日にキラキラかがやかせたりいたしました。
おじいさんはわきによけて、やはり草の中にこしをおろしておりましたが、どうしたことか、そのうち、ほおをつとうて、涙を流し始めました。やっぱりむすこのことを考えていたのです。――こんなにくにでは、山の中でも、おししがもうているのに、あいつばかりは何千キロの海の遠くにいて――。そう思わずにはいられなかったのです。
一おどりすむと、ししがしらをかむった人は、それをぬいで桃の木の下に立てかけ、ハアハア大いきをつきました。てぬぐいで汗をふきました。そしておじいさんにききました。
「おじいさん、どうだったろうな。」
「ウン。おもしろかったよ。つい涙が出てしもうたよ。」
おじいさんは鼻をすすりながらいいました。
「じゃ、このへんで帰るとしようか。」
三人は一やすみすると、そういって歩き出しました。
おじいさんも、それでこしをあげました。
この四人が行ってしまうと、あとには道を通る人はなく、この桃の木のあたりがシーンと静かになりました。と、どうでしょう。桃の木に三びきのリスがチョロチョロッとかけよって来ました。そしてみきに両足をかけ、のぼろうか、のぼるまいかと、あたりを見まわしました。すると、あとからイタチが二ひき出て来て、木の下にこしをすえ、ならんで、それを眺めました。と、またそのあとから兎が、そうです、三びきも子兎をつれて出て来て、これもこしをすえて、桃の木とリスをながめました。きっと、これらイタチや兎、リスたちはししまいの笛とたいこの音で森のおくからあつまって来て、遠くから人間のすることをながめていたのです。人間が桃をとりはしないかとしんぱいになったのか、それともししまいがおもしろかったのか、どっちだったかでしょう。
しかしそれから何日かたちました。みよ子、四郎、八郎の三人が又そこを通りかかりました。ところが、その時みると、その美しい五つの桃がもうその枝にありませんでした。その代り、そこには白い三羽の小鳥がとまっていました。桃が鳥になったのでしょうか。もとよりこんなことはありません。で、八郎はいいました。
「なあ、あの桃、きつねがばけとるんじゃと、おれがいうたろうが。やっぱりそうじゃったんだ。じゃからもう一つもありゃせんぜ。あまりきれいじゃったものなあ。気味がわるいくらいじゃった。今、あそこにいる鳥じゃってわかりゃせんぜ。きつねかもしれんぞ。」
そして八郎は、
「ワッワッ。」
と、大声をたててその鳥を追いました。鳥はパッと羽をひろげてとび立ちましたが、又バタバタとはねを立て、あやうく枝にとまりなおしました。きつねにもなりませんでした。
「ハ、やっぱりほんとうの鳥でおりやがらあ。」
八郎はそういい、三人で家の方へ帰って行きました。
「こんど桃がなっとったら、おれどうしてもとって食べるんじゃ。てんぐになってもかまやせんや。」
八郎は歩きながら、まだそう言いつづけておりました。
メデタシ、メデタシ。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763