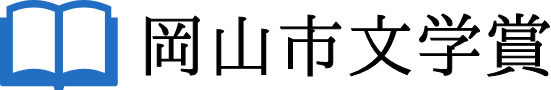城山探検
正太と弟の善太は、長い竹の棒を杖について、谷底の坂道をてくてく上っていきました。正太は双眼鏡を背中につるしています。 左手の山腹にぎっしり生えた小松の青葉には、五月の午後の日があかあかとさしていますが、こちらの坂道は小暗くて陰気です。
二人は昨夜お父さまから聞いた城山へ探険にいくのです。正太たちの家の西北に見える万成山まんなりやまの頂上には昔城があったので、普通に城山とよんでいますが、その城にこもっていた大将のことや、城の陥落した話なぞは昨夜はじめて聞いたのです。
その城は今から三百年も昔の元亀三年という年に、松田左近将監という人が造ったもので、富山城とよばれていたものだそうです。それを、ここから五里ばかり東の沼というところに城をかまえていた宇喜多直家という大将が攻めて来て、はげしい戦争をし、城に火をつけて焼き落したのでした。今でも城あとの地面の下には、そのとき焼けた米麦の炭なぞが埋っているといいます。
「兄ちゃん、あした上ろうか。」と善太が言い出しました。
「よし、上ろう。」
「刀や槍がうまっていたら掘って来ようね。」
「うん。洞穴の中なんかには、よろいや甲かぶとだってあるかもしれないよ。」
「ぼく金のよろいがほしいね。」
「ぼくは甲だけだっていいよ。」
谷のかなり上のところまでのぼりつきますと、ちょっとした池がありました。小さいけれども深いらしく、青い水が無気味によどんでいます。二人は池のふちに杖をとめて休みました。見ると足もとのところに亀が一ぴき四つ足をのばし、くびをのし上げて、ぽかんと浮んでいます。
とてものんきなかっこうです。だれか人が来て、いたずらをしてくれるのを待っているようにさえ見えました。そこで善太は、そこいらの石ころを拾おうとかかりましたが、ふと池の向う岸を見ると、それをやめて、目を見はりました。
「兄ちゃん、あれ、なアに?」
向う岸にはえている樫見たいな大きな大木の一とう下の大枝が、するどい斧で切りつけたように、折れ下っています。きっと雷でも落ちたのでしょう。その枝に、二三まいだけ葉のついた小枝があります。その枝の上に足の長い、まっ白な鳥がとまって、じっと池の上を見下しています。
「白サギかな。」と正太は言いました。二人とも何鳥だとも分らないまま、しずかに見ていますと、鳥はパッと羽根をひろげてとび下りて、池の水をちょいとつつくなり、すいすいと池のぐるりを一まわりして、またもとの枝へとまりました。
「兄ちゃん、城のあとはどこ?」
「このもっと上じゃないかな。」
善太はそれを聞くと、もとはこの池へ白壁の城がうつッていたのじゃないかしらという気がしました。
「兄ちゃん、この池の中には、よろいや甲がしずんでるね。」
「うそだい。この池は近ごろ出来たんだよ。だって、あの石がけ、あんなに新しいじゃないか。」
言われて見ると、水をせきとめた土手の石がけは、なまなましくて、苔もはえてはおりません。
二人は歩き出しました。道はまだ上りになっています。とても急な坂道です。それを上り切ると、山のてっぺんへ出ました。てっぺんは東から西へと、ずっと長い峰つづきになっており、洗い上げたような砂土で、小松がまばらに生えています。峰は西へいくほど高くなっていて、その一とうてっぺんに大きな塔のような岩が二つ、くッつき合って、つッたっています。左の方のが少し低く、ちょうど二人で背くらべをしているように見えます。
正太たちは爪先上りのところを、口をむすんで、杖をつきつき、塔岩へ向ってのぼっていきました。善太は、えらくてえらくてたまらず、途中から兄ちゃんにお尻をおしてもらいました。
やっと塔岩の下まで来ましたが、遠くからは小さく見えたその岩は、見上げるように高くそびえています。ぐるりには、青い羊歯しだがぎっしり茂りのびています。二人は杖をついてしばらく岩を仰いでいました。
「上りたいなア。」と善太が言いました。
「上ろう。」
兄ちゃんは元気よくこう言って、先に立って、杖で羊歯をわけわけ歩きました。
「何かいない?蛇かなんか。」と善太は言いました。
「いるもんか。」と正太は言いました。と、そのとき、黄色っぽいような、どすぐろいようなものが、正太の目のまえへ、ぴょいと、とび出したとおもうと、ぴょこんと左の方へ二間もはねとんで、岩の根もとにそうて、びゅうびゅうとんでにげました。
「兎だッ。」と正太は立ちどまりました。
「あ、またいた。」と善太が言いました。もう一ぴき、あとを追ってびゅうびゅう走っていきます。ちょうど競馬見たいです。
「早いなア、兄ちゃん。」
「兎だもの。」
正太は善太の手を引っぱったりして、苦心をしながら、まず低い方の岩の上へ上りつきました。そこで高い方の岩壁にもたれて腰を下しましたが、ふと、目の下にひろがっている景色を見ると、
「あッ、海だ。」と言って立ち上り、双眼鏡を下してのぞきこみました。
「ほう。」
「兄ちゃん、何見える。よ、こんどはぼくだよ。見せて、見せて。」と、善太は双眼鏡に手をかけました。
「あああ。あああ。」と正太はこんなことを言って、いつまでもはなしません。
「おい、とってもよく見えるよ。海の浪が、ざざあ、ざざあと打ってるよ。白くなってくずれる。ほら。」と双眼鏡をわたしました。
「船は見えない?」
「船はいないよ。漁船も汽船もなんにもいない。ただ海だけだよ。」
「ほう、きれいねえ。すてきねえ。ああ、浪、浪、浪。ずしいん。くずれた。くずれたよ。ほう。」と善太はよろこびました。
「も一度見せろよ。」と正太は眼鏡をとりました。そのうちに二人は、高い方の岩へ移りました。そして北の端のところまでいってのぞきますと、下はとっても深い谷で、ぞくりとするくらいです。
二人とも、しゃがんでしまいました。立ったままでは、こわくて見られはしません。下の方まで青ずんだ色をしています。じき下の岩の間から、羊歯がぎっしり茂って、毛せんをしいたように、ずっと下までつづいています。ときどき風がわたって、さッと白い裏葉をかえします。ときによっては、獣か何かが中を走るように、青葉がザワザワと乱れわれるときもあります。谷底のずっと遠くには浅い川が一すじ流れています。小松の青い葉の間から日に光った水筋が見えます。その川の岸には、ところどころに山藤の花のかたまりが紫の雪のように小松へからみ上っています。
「きれいだねえ。」と正太はさけびました。
「兄ちゃん、この谷で昔戦争をしたんだよ。きっと。チャンチャン、ドンドン。」と善太はこう言って見下していました。と、下の方で、何の鳥だか、クククククと、するどくなきました。すると、それが向うの山へひびいて、またクククククと言いました。
正太は大きな声で、ククククク、クワッとどなって見ました。すると谷の下の方から同じような声で、ククククク、クワッと言いかえしました。
「こだま、こだま。」と善太は言いました。善太には、下の方に、正太や善太のような子供が方々にかくれているような気がしました。
「下りよう。」と正太が言いました。二人はころころと塔岩をかけ下りて、もと来たところを通り、小松の中をくぐって東の峰の方へ出ていきますと、城跡らしい、大きな松ばかり茂った平地へ出ました。一町四方もあるでしょう。
その大きな松の木には、どれにもこれにも幹の根元からツタがからみついています。
長い蔓がぶらぶら風にゆられて下っているのもあります。今まで日の照っていたところから、このうすぐらい松林の中へはいると、へんにさびしく、しいんとした気もちになりました。
「兄ちゃん、お城どこにあったの?」と善太が聞きました。だって石がけののこりも何にもないので、正太にも見当がつきません。
二人は松の間の道もないところをくぐりくぐりして、平地の真中あたりまではいって見ました。すると、象ぐらいの大きさのまるまった岩があったので、それへかけ上りました。善太は先に上るなり、
「ああお城お城、お城が見える。」とさけびました。
「どこに。」と正太はびっくりして見まわしました。善太が指さす松の間を見ると、山の下のずっと遠くに白壁の天守閣が見えました。しかしそれはむろん富山城ではありません。あとでお父さんに聞いたら、富山城を攻め落した宇喜多直家が、沼から移りこもった烏城というお城です。
でも二人は、天守閣が見えたので、とてもうれしくなって、永い間背のびをして見入っていました。見ているうちに正太は、ここに立てこもっていた松田左近将監の家来のような気がして来ました。
「ぼくは左近将監の命令により、これからあの向うの城を攻め落すんだ。」
と、正太は武者絵にかいてあるように、目の上へ手をかざして城を見つめました。
「兄ちゃん、ぼくは?」
「おまいも将監の家来だよ。ぼくと一しょに何でもするんだ。あああ、腹が減った。何か兵糧をもって来ればよかったね。」
「ぼく、キャラメルあるよ、ほら。」
「なんだ。たった二つか。」
二人はキャラメルの紙をはがして口へ入れました。
「すわれよ、善太。少しくたびれたね。」
岩の上にあぐらをかいて、だまってキャラメルをしゃぶっていますと、今まで気がつかないでいた、松をふく風の音がザザア、ザザアと聞えて来ました。それでもって、いよいよここが昔そのままのような気がします。このあたりの松の蔭や岩の後には、よろい甲の軍兵が槍をかかえて、かくれているのではないか、などとおもえて来ました。
と、どこからか、ほう、ころころ、ほう、ころころという、古ぼけたような声が聞えて来ました。二人は顔を見合せました。
「何、あれ。兄ちゃん、ぼく少し恐くなって来た。もう帰ろうよ。兄ちゃん。」
そう言えば正太も何だか急に、うすきみがわるくなって来ました。
二人は岩を下りました。正太は、もうこれで帰るのかとおもうと、なごりおしいような気もして、岩の後へまわって見ました。すると、後がわでは岩が真中から大きく割れていて、間口一間もある深い洞穴が出来ています。
「兄ちゃん、どこ?」と善太も来ました。二人はその洞穴をのぞきこみました。中は真暗です。どれだけ深いか奥はわかりません。善太は変にこわくなって、
「兄ちゃん。」と、正太の袖を引っばりました。
「何だい。」と正太は平気で、いつまでものぞいていました。と、そのとき、頭の上で、クアーという声がしました。二人はびっくりして、とび退りました。何だろうと岩を見上げますと、洞穴の上のところに、ちょっとしたくぼみがあって、小さな蘭のような草がもじゃもじゃ生えているその中に、一羽のふくろがまるい目をあけて、こごまっています。人が来たのでおどろいたのか、首のところの毛を逆立てて、怒ったような顔つきをしています。
正太は、コラッとどなって杖をふり上げました。するとふくろはとても怒って、ばたばたッと、くぼみの横手へとび出して、クワアクワアと、気味のわるい声を立てました。
「兄ちゃん、いこうよ。」と善太は、こわそうにせき立てました。
「おや、あすこにもいるよ。」と正太はさけびました。今ふくろがとび出したくぼみから、右へ三尺ばかりはなれた、もう一つのくぼみの中にも、もっと大きなふくろがいて、大きな目をあけて、草の中から、じっとこっちを見すえています。
「いこう。」と正太も少しこわくなって引きかえしました。
「走ろう。」
「まってよ、靴ん中へ砂がはいったから。」
二人はそれからどんどん走って松林を出ました。外へ出ると黄色い日が一ぱいさしているので、もう、こわいなんて気持はしません。二人は元気にしゃべりしゃべりして、もと来た谷道をどんどん下りました。
「兄ちゃん、あの洞穴ね、あん中に金の甲かなんか、かくしてありゃしない?」と善太はおもい出したように言いました。
二人は家へかえると、お母さんに、かわるがわる城あとの話をしました。善太は妹のあきちゃんにこんな話をこしらえて話しました。昔そのお城に金太郎というつよい子供がいて、それが金の甲をかぶり、金のよろいを着て、むく犬に乗り、家にいる鶏と猫をお供につれて城を乗り出し、沼の城にいる宇喜多直家を退治にいく話です。
あきちゃんはおもしろがって、もう一ど言ってよ、言ってよとねだりました。善太はしまいには、
「その金太郎はこの兄ちゃんだよ。兄ちゃんが金の甲をつけて、むく犬に乗ってね。」と、じぶんが宇喜多直家を退治したように話しました。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763