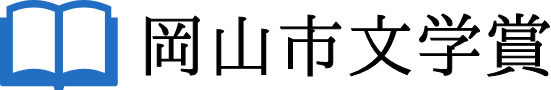柿の木と少年
ボクの家には一本の柿の木がありました。家の西北のすみに立っていました。ミは、何というのでしょう。四角形のようで、先がとがっているのです。大きな実ですよ。おとうさんの茶のみ茶わんくらいもあるのでしょうか。それが、その木に百も二百もなるのです。じつに壮観でした。多く実のついている枝なんか、先の方がしなってさえおりました。柿の名前はボク知りません。しかし惜しいことに、それがシブ柿なんです。それで家では、大シブ大シブって呼んでいました。
で、十九年の秋のことです。十月の中ごろでした。ボクは、その柿が幾つ実っているか、かぞえて見ました。二百四十三なっていたのです。何んでかぞえたかというと、その柿はボクが管理するように、毎年おとうさんからいわれているからですよ。十月二十五日六日は、ボクたちの町のお祭りでした。そのお祭りのごちそうに、毎年その柿の半分をとって、アワセ柿にし、近所や親類へくばり、家でも食べることになっておりました。だからボクはその数をかぞえました。そしておとうさんに、
「ことしはおとうさん、百二十だけとりましょうね。」
そういいました。おとうさんも、それをきくとニコニコして、
「ウン、それがいい、去年は百だったかな、とれたのは。ことしは二十だけ家で多く食べられるな。それとも、達夫と純夫のお友だちにあげるか。」
そんなことをいいました。達夫というのはボクのことで、純夫は弟のことです。で、ボクは、
「どっちでもいいです。」
そういって、木のところに帰り、木の幹に二四三とナイフの先でシルシをつけました。去年の二〇八も、オトトシの一六一もまだシルシが残っていました。ボクは楽しみでした。この木は植えてから十五年だそうですが、年々数がふえるし、形も大きく立派になってゆきます。三年五年とたったら四百も五百もなるようになってゆくかも知れません。そうしたら、二百をお祭りのごちそうにし、二百を干し柿につくり、百をジュクシ―にしてそう考えると、ボクは歌でもうたいたくなるほど、愉快になるのでした。
それに、ものを計算して、ケイカクを立てるということは、とてもキモチのいいものですね。これは学校でおそわり、宿題でも下調べでも、それから家の手つだいでも、みんなボクはそうするようにしてきていました。だから柿だって、その年の数によって、ケイカクを立てました。その年は百二十をお祭りのごちそう、六十を干し柿、六十三をジュクシにして、食べることにきめました。六十というのは、おとうさんおかあさんボクと弟、みんな十五ずつの数であります。ジュクシの六十三は、三つだけカラスがきてつつくのに残してあるのです。だって、どんなに気をつけていても、二つや三つは毎年カラスにつつかれてしまうからですよ。
ところで、お祭りの二日前のことです。きょうは柿をとるというので、楽しみで学校から帰って見ると、家の中にはおとうさんもおかあさんもいなくて、純夫ばかり茶の間でポツンとねころんでいました。
「どうしたんだい。」
と、ボクがきいて見たら、
「おとうさんに召集がきたんだ。それで、おかあさん、その知らせに会社へ行った。」
純夫がいいました。
「フーン。」
ボクは何気なくそういったけれども、これは大変なことになったと思いました。しかし友だちのおとうさんも、それからにいさんなんかもたくさん戦争に行ってることですから、ボクたちの家ばかりではないのですから、ラクタンしたり、ナゲイたりしてはならないと思いました。十月二十四日、おとうさんはボクたちだけに見送られてカゴシマの駅から立ちました。おとうさんは海軍でしたからサセホの海兵団へ入るのだったのです。改札口で、おとうさんはボクと純夫の顔をじっと見つめてそれから悲しそうにニッコリしました。ボクもニッコリしました。すると、おとうさんはちょっとオジギのようなことをして、そのままクルリと後向きになり、ズンズン歩いて行ってしまいました。後から純夫が、
「おとうさん―」
と呼びましたが、もう後にも向きませんでした。おかあさんも手をパチパチ、後に向かせようとたたきましたが、おとうさんはそのままプラットから地下道へおり、見えなくなってしまいました。ボクたちはその後ずい分長くそこに立っていましたが、人がこんできて、もうおとうさんが見えるようにも思えませんでしたので、思いきって、家に帰って来ました。その日、ボクは柿の木に「一九・一〇二四」とコガタナでほりつけました。柿のケイサンなんか、どうでもよくなったのです。それよりは、おとうさんの手紙のきた時とか、おとうさんが家に帰った日とか、そんなボクにとって大切なことを書くようにきめました。
「一九・一〇三〇」これはおとうさんから無事入隊という知らせのきた日です。しかしその後おとうさんから一通のハガキも手紙もきませんでした。
「一九・一一二六」この日ボクは級長になったのです。級長の浅田君が東京の近くへ急に家の人たちと帰って行ったもので、代りにボクが選挙されました。
「一九・一二一五」これは確かおかあさんが近くの村ヘサツマ芋を買い出しに行かれて、帰りが非常におそくなった日のシルシです。おかあさんはその日一時ごろに家を出て、四時頃帰るヨテイだったのです。それが八時になっても、九時になっても帰ってきませんでした。バンにたく米は無く、ボクと純夫はイッショウケンメイおかあさんの帰りを待っていました。そうしたら、九時半ごろになり、おかあさんは青い顔をして、
「あ、あ、あ。」
そんなことをいいいい入ってきました。そして玄関に腰をかけたまま、久しくものもいいません。
「どうしたの?おかあさん。」
ボクがきくと、
「オサツを五貫めもおかあさんはかついでいたんだよ。それをみんな駅でオマワリさんにとりあげられてしまった。ウチで子供たちがゴハンも食べずに待ってるといっても、どうしても返してくれないんだよ。それで、これではならないと、また引き返して行って二貫めだけ買ってきた。ああ、疲れた。あんた方もオナカがすいたでしょう。」
おかあさんはそういいました。ボクは全くオナカがギュウギュウだったので、ホントはそれまでにそんな悲しい日も、そんなハラのたった日もないほどでしたのですが、おかあさんの話をきいたら、おかあさんが気の毒になって、
「ウウン、なんともないや。ねえ、純夫。」
そういってしまいました。純夫も同じキモチか、
「ウン、ボクも平気だった。」
そういったのです。おかあさんは喜んで、一休みすると、それからオイモをふかしにかかり、十時半ごろそれがやっとふけあがりました。しかしその時湯気が立つイモをフウフウふいて食べたおいしさ、今に忘れることが出きません。三人で一貫めも食べてしまったのです。すると純夫は、
「うまいなあ。うまいなあ。」
と、何度もくり返していいました。それでボクとおかあさんはうれしかったりおかしかったりして、ついハッハ笑ってしまいました。とにかく、この十二月十五日という日は悲しい、そして心配な日で、またそれだけにうれしい日だったのであります。しかしその日がボクの、心配でつらい月目の始まりだったかも知れません。
「二〇・一一七」だったでしょうか。それとも一二七だったでしょうか。ボクはもう忘れました。だって、それから後のシルシはみんなカゴシマが空シュウを受けたり、日本軍がイオウ島でまけたり、オキナワへ米軍が上陸したり、そんな日ばかり書きつけているのですから、終戦になって今、ボクは忘れてしまいました。
そうだ、だけどもボクの覚えていることが一つあります。柿のことです。おとうさんが召集で行かれる時二百四十三あった柿を、その後でおかあさんや純夫と日曜日にイッショウケンメイでもぎとって、みんなで干し柿をつくりました。それをおかあさんは買い出しのたびにもって行って、オイモを売って下さる家へ一度に十コ十五コとオミヤゲにしました。しかしボクたちも毎日一ツニツずつくらいはお八ツにもらいました。おかあさんが帰りのおそかった日にも、ボクたちはそれを食べて、オナカのすくのをこらえていたのです。でも、それが二十年の一月二十三日になくなりました。「二〇・一二三」という覚えやすい数字だったから、今もボクはよく覚えております。
「二〇・六一七」これは柿の木に書いてあるのではありません。板切れにエンピツで書いて、フロシキ包みの中に入れてあるのです。だけども、これくらい忘れられない日はないのです。その夜のことです。ボクたち三人は御飯を食べてから間もなく床に入ったのです。雨がふっていて、することもなかったのです。で、純夫が、
「ボクもうねるよ。」
そういうと、おかあさんは三つの床をとられ、それで、パタパタねてしまったのです。すると、十一時ごろのことだったのです。アメリカのB29がやってきたのです。雨のせいで、B29のやってくるのがわからなかったのか、サイレンの音もしないうちに、もうバクダンの音が方々でドーン、ドーンとしはじめました。それは親子ショウイダンというので、直ぐ方々で火の手がもえあがりました。おかあさんはカナキリ声をあげて、ボクたちをおこしました。ボクが起き、純夫が起き、フトンをたたもうとすると、そこへ、台所にショウイダンが落ちてきて、ドンドンもえ始めました。おかあさんはビックリして、
「早くお前たち逃げなさい。先に逃げなさい。」
そういうもので、ボクたちは前の道へ走り出ました。もう方々の家がもえていたのですが、その間の道をたくさんの人がゾロゾロ城山の方へ歩いていました。もえてる横町の中から、煙のもうもう出ている家の中からかけ出て来る人もありました。ボクたちは手をつないでたくさんのその人たちの中にまじって歩いてゆきました。
みんなドンドン走ればいいのにと思っても、先がつかえているのか、火がからだにつきそうで、熱くてならないのに、だれも走りません。ボクはもどかしくてなりませんでした。そのうち、ゴウッといって、大きな風が真黒な砂煙をあげて吹いてきました。みんな、コロゲそうになって、片方にヒョロヒョロしました。その時、丁度ボクたちの前にショウイダンが、三発一度におちてきました。それで、そこにいた人たちはバラバラに、飛び散るように逃げのきました。ボクたちも逃げました。しかしその時ボクは弟の純夫といつの間にか手をはなし、いつの間にか分れ分れになっていました。ボクは炎の中に立ち止り、
「スミオッ、スミオッ。」
と、こん限りの大声で呼びました。だけどもたくさんの人がつぎからつぎへ逃げて来て、ボクをつきとばしそうにするので、スミオの声もきこえなければ、スミオらしい子供を、一生ケンメイ見たのですけれどもどうしても見つかりません。しかたなく、ボクはまたみんなにまじって少し歩きました。しかしスミオも心配だしおかあさんも気がかりなもので、また後に引き返し、家の近くまで、大火事の中を帰って見ました。人はどこから出て来るのか、前とは少しすくなくなっていましたが、みんな飛ぶようにかけていました。そのうち一人、ヤケコゲの防空ズキンをかぶったオジさんが、ボクが道に立って、ウロウロしているのを見て、
「坊や、どこへ行くんだッ。」
と大声できいてくれました。
「スミオがいないんです。」
そういうと、
「ここでウロウロしていると死んでしまうぞッ。」
そういって、ボクの手を引いて走り出しました。ボクはその人に手を引かれ、ころげるようになって、やっと火の中をかけぬけ、城山の下につきました。そこでオジさんが手をはなしたので、みんなの後につき、ゾロゾロ山をのぼりました。家の方が見える所につき、そこから、あの辺がボクの家だと思って見ていました。そこはもう燃えあがり燃えあがりする炎で、いっぱいで、人間なんか一人だって見えませんでした。一人でいると、おかあさんのことがとても心配になってきて、「どうしているのだろう。もう焼け死んでしまったのじゃないかしらん。」とカラダがふるえるような気がしました。
その恐しい夜もあけて、十八日の朝になりました。ボクはさっそく家の方へ行って見ました。そこらあたり一面のヤケアトになっていて、ボクの家はもうありませんでした。ボクはそのヤケアトのそばに何時間も立っていました。おかあさんか、スミオがボクのようにやっぱりそこへ来るかもしれないと思われたからです。しかしいつまでたってもだれもきませんでした。それでボクはシカタなく町をたずねてあるくことにしました。
歩いていたら、カゴシマ航空隊の兵隊さんがカンパンやニギリメシをザルや箱に山のようにつんで町かどでみんなにくれていました。ボクも朝の御飯をたべていなかったので、カンパン二つとニギリメシを二つもらって食べました。とてもおいしかったのです。その後で近くにふき出している水道の水をのみ、ついでに顔も洗いました。
大ぶん元気が出てきたものでそれからまち中をあちらこちらと、おかあさんと弟をさがして歩きました。市中はやけくさくて、胸が悪くなるようでしたが、それでもボクはシンボウして、ずい分たくさん歩きました。しかしその日はどうしてもわからず、その晩は西カゴシマ駅に行って、そこのベンチにとまりました。一晩中、昨夜の恐ろしかったことが目にうつって消えませんでした。それから後、ボクは一月というものカゴシマの市(まち)中を毎日毎日歩きまわり、家のアトなんかは毎日のように行きました。それでもおかあさんも弟も見つからないので、どうしていいかわかりません。
ところが、ある日のこと、駅で、十四になる子供と知り合いになりました。その子供は熊本からきたといっていました。そしてまた、こんなことをいいました。
「熊本へ行かないか。熊本ではみんな親切で、白い御飯をいくらでもくれるんだぞ。」
ボクは初め「いやだ。」といっていましたが、いつまでもおかあさんと弟が見つからず、食べることにも次第に困ってきて、どうしていいかわからなくなっていたもので、
「じゃ、いこう。」
そういって、七月二十日の夜八時三十分の汽車に乗って、カゴシマ駅を出発しました。熊本には二十一日の午前三時につきました。おりてみたら、熊本もやけていて、駅にはボクのような、おとうさんおかあさんを無くした子供らが十人ばかりいました。ボクをつれてきた子供は、その子供らのナカマでして、ボクも直ぐナカマに入れてくれました。それはよかったのですが、そのうちその子供たちの中に、ボクに、人の物をぬすめという子供がいて、ボクはホントに困りました。ぬすまないと、ナカマはずれにされるわけなのです。ボクは昔からそんなことはキライなんです。それでもうそこの子供たちがイヤでたまらなくなり、半月ほどたったある日、友だちにわからぬように、そっとカゴシマ行きの汽車に乗りました。
なつかしかったカゴシマ駅について見て、ボクはおどろきました。半月の間に立派だった駅はやけてしまって、バラック作りのへんな小屋が立っていました。そしてそこに戦災の子供が十五人くらい集っていました。ボクはその中に弟の純夫がいやしないかと、その子供を見た時、ドウキが胸の中でドキドキしました。だけども純夫はやっぱりおりませんでした。みんなに聞いてみましたけれど、やっぱりわかりません。そこでボクは考えました。
「弟もやっぱりボクのように、友だちなんかができて、それといっしょに、あっちこっちの駅をうろついているのじゃないかしらん。」
それで、それから汽車にのって、なるべく多くの駅をまわり歩くことにきめました。大きな駅ではおりて、新聞を二十五銭で買い、それを五十銭で売り、二十五銭ずつもうけ、それで食べものを買いました。ちょうど、カゴシマ県川内駅のことでした。八月十六日です。ボクが買った新聞を見たら、日本が降伏したと書いてありました。ボクはビックリしました。またガッカリもしたのです。しかしどうにもならないのですから、その新聞を売って、売り終ると、ヤミ市でダンゴを買って食べました。それから後はもうヤケになって、ヤタラに九州中を飛びまわりました。宮崎県に行けば、大分県熊本県、そこら中の村から町、町から村、時には山から谷、谷から山とめぐりめぐって行ったのです。一日一日と日はたって行きました。そして大分県の別府で二十一年の正月を迎えました。
丁度その前の日のことです。二十年の年末三十一日です。その別府で門司行きのキップを買ってくれと一人のオジさんにたのまれ、列にならんでキップを買いました。するとオジさんはあくる日の朝元たんの朝です。やってきて、大喜びして、キップを受けとり、もちを二つと、お金を十円くれました。それからボクはまた考えました。
「そうだ。ヒルは新聞を売り、夜はキップを買い、それでお金をもうけよう。そして人にものをもらうことをやめよう。」
そしてボクは方々の駅々を、新聞を売り、キップを買いしてまわり歩きました。熊本、大牟田、博多、門司、小倉、中津、大分、佐伯、延岡、宮崎、都城、恐しかった六月十七日は宮崎県の富吉という所で明かしました。
そうです。そんな間に一度カゴシマに帰りました。家のやけあとに行って見ましたら、やっぱりそこはあのままで、もう草がボウボウはえ茂っていました。もっとも丁度雨が降っていて、かわらや何か雨にぬれていました。ボクはその時、柿の木のことを思い出し、ヤケアトの中にふみこんで、木のあったところへ行って見ました。木はあとかたもなかったのですが、近くのかわらの下にザッキ帳くらいの大きさの一枚の板切れを見つけました。それが、家の何に使ってあったか思い出せませんでしたが、ボクはそれを拾って、持ってたフロシキの中に包んできました。その木のミキに何日何日といろんなことをほりつけたことを思い出したからです。その木の代りに、その後ボクはその板切れに、「七一二」だの、「八二三」だの、たくさんの記念の月日をエンピツで書きつけました。今でも、いろいろのことを覚えているのはそのためですが、ボクはこの板切れを大切にして、大きくなって自分で一人立ちでくらせるようになるまで大切にとっておこうと思っております。またもしおかあさんや純夫にあったり、おとうさんが帰ってこられたりしたら、この板切れを見てもらって、ボクの今までの話をきいてもらおうと考えているのです。だからこのきたない板切れだって、ソマツにできないと、気をつけて、失わないようにしております。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763