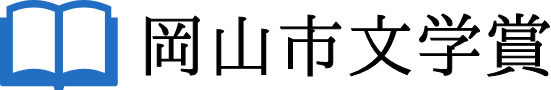トンボのひるね
気がついたら、ぼくはトンボになっていた。そして、一メートルばかりの竹の棒先にとまっていた。あたりは静かだった。日がシーンとてっていた。
「もうヒルが近いな。」
トンボのぼくは思った。ヒルというのは、ヒルゴハンを食べる時間だ。こんなに暑いんだから、その時間にちがいないと、ぼくは考えたんだ。その時、ぼくはどうも少し目をあけすぎてるような感じになった。その辺が、明かるすぎる。少しまぶしい。それはそのハズだ。トンボであるぼくは、ほとんど頭の半分以上が目なんだ。大きなガラスの頭のような目なんだ。それがまぶしいからといって、つぶれない目なんだ。ふさぐことも、かくすこともできない目なんだ。
「こまったねえ。」
そう思うと、ますますまぶしくて、ぼくはその頭と目と口が一しょになってるようなところを、クルクルクルクルふりまわしてやった。しかしちっともまぶしさは変わらないで、かえって目まいがしてくるような気分になった。まわりの世界が、空も地も、そうだよ、太陽も空気も、草も木も、ぼくが首をふるにつれて、クルクルクルクル、まわり出し、それがメチャクチャに入りみだれたり、うずまいたりした。
そのとき、目の前で人間のにぎりこぶしが、これまたグルグルまわり出した。人間のなってるトンボを、人間がとろうとするなんで、なんてふつごうやつだろうと、ハラを立てて、ぼくがその人間の顔を見ると、それが弟の杉夫だ。
「やい、兄ちゃんだぞ。兄ちゃんをとるってことあるかい。」
ぼくは力一ぱい、声をはり上げていってやった。そのうえ、両方のハネをビリビリふるわせてみた。杉夫には聞えたのか、聞えないのか、平気のへいざで、やっぱりこぶしをまわして、その先に立てている指を、ぼくの方に近づけて来る。ぼくはこの時ほど、人の指をおそろしいと思ったことはない。ピストルとか、カタナか、いや、いや、それ以上だ。へびが首を立てて、大口をあけて、追っかけてくるほど恐ろしかった。
そこでぼくは、ウンと気ばって、両肩に力をいれた。すると、からだが宙に浮いてワケなく空中飛行だ。空をとぶなんて、ホントになんでもない。見るまに杉夫の指からも、杉夫のさおからもはなれてしまった。上にあがろうと、下にさがろうと、そう思うだけで、からだがそうなって行くのだから、トンボって便利なものだ。
ところがまもなく、こまったことになってしまった。ぼくはねたくなったのだ。つかれたので、ねたくなったのだが、トンボというものは、横にもなれないし、あおむけにもなれない。それこそハネをひろげて、何かにとまったまま、大目をあけて眠るのである。こまった。こんなつかれているのに。そう思ったところで、ぼくは目がさめた。病気でねている床の中で、ぼくは夢を見ていた。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763