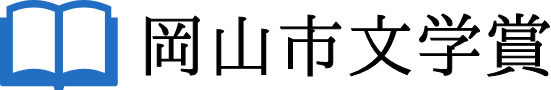甚七南画風景
甚七老人は歳八十で、今は別にしたいこともなかった。食事を楽しむくらいのものであった。それも近年は二度で、その二度にも、あれこれと注文して、おかずを造らせて見るものの、食べて見ると、期待したほどの味もなかった。腹をすかせて、温い飯にヤキノリで食べるのが、まず一番であった。その他の楽しみは方々を見物して廻ることであった。方々と言っても、遠い処ではない。八十年の生涯に記憶に残る近くの石橋であるとか、村端れの一本の柳の木であるとか。――あれはどうなっていたかな――そんなことを思出しては、杖をつきつき訪ねてゆくのであった。死ぬる前に、この世の一木一草にも名残りを惜しもうとするのであろうか。尤も、彼に、意識的にはそれ程の気持はなかった。何とはなしに、見ることと、それに依って、昔を思い出すこととが楽しまれたのである。
「おお、あそこの桜が咲いた頃だ。若い頃、あの桜に馬をつないで、駒が勇めば花が散るなんて唄ったことがある。どれ、一つ見に行って来よう。」
そんな有様であった。今日も縁側に坐って、煙草を吹かせながら庭を眺めていると、ふと、墓参りがしたくなって来た。墓参りというより、墓地から四方の景色が眺めたくなったのである。そこに自分が埋ってから眺めるであろう四方の景色を、今の内に眺めて見ようとするのかも知れない。
「おいおい。」
これは老人がお婆さんを呼ぶ呼び方なのである。
「ハーイ、ハイ。」
少し間のぬけた返事をして、お婆さんがやって来る。
「馬に鞍を置かせてくれ。」
「木馬で御座いますか。」
と言うのは、近年老人は本ものの馬に乗る元気がなくて、木馬を屋敷の隅につくり、それに乗って、僅に乗馬の楽しみを味わっていたからである。然し老人、今日は違っている。
「バカッ、何を言う。木馬になど乗れるか。」
「でも、馬は危う御座いますよ。」
「いい、いいから置かせてくれ。」
「でも、木馬と違って、跳ねたり飛んだり致しますが。」
「いい! いいと言ったらいいんだッ。」
「ハイ、ハイ。」
お婆さんは引込んだが、台所で、下男の作蔵に言ったのである。
「馬に鞍を置けってさ。生きた馬だよ。」
「へえ――、お乗りになるんですか。」
作蔵が言う。
「木馬にも飽きて、ホントの馬に乗りたくなったんだろうが、立場(たてば)につないだまま、また大きな声を出すんだろうよ。ハイヨ――、ハイヨ――。あの声を聞くと、私ゃおかしいやら恥ずかしいやら、全く気の毒になってしまうよ。」
然し作蔵は馬を厩から引出し、立場に首を高く上げて繋いだ。鞍もおき、クツワもはませた。
「大旦那、馬の用意が出来ました。」
作蔵は新しいハッピにモモヒキ、ジカ足袋もはいて、別当の身支度である。
「よし来た。」
老人は黒の乗馬袴に、竹の根の鞭を下げて、外に出て来た。
「どう、どう、どうどう。」
二三間も前から老人は馬に呼びかけ、側にゆくと、首筋をパタリパタリと叩いてやる。アブミの下には、作蔵が気をきかして、二段もある足台の箱を置いている。
「フン、これは乗りいい。」
そんなことを言いながら、老人は台の上で袴のモモダチとって、帯にはさみ、手綱をさばいて、鞍に跨る。馬が二三歩足ぶみをする。と、老人、どうどうどう。そして言うのである。
「今日は墓参りをする。三平を呼んでくれ。」
「ヘイ。」
作蔵は台所に行って呼ぶ。
「坊チャン、お爺さんが馬に乗せたる仰言ってますよ。」
「ウ――ン。」
三平が飛び出して来る。これにつづいて、お婆さんが、老人の山高帽を持ち出して来る。そしてまた老人に言うのである。
「あなたいつかお落ちになったのを、もうお忘れになったんですか。」
が、老人は返事もしない。馬上で反り返っている。
「墓参りは車でなさって、乗馬はその立場でなさったら宜しいじゃありませんか。」
老人はアゴを突き出し、やはりどこ吹く風かと返事もしない。
「元気ばかりで、歳のよったことを知らないんだから。」
お婆さんはひとりごとを言う。でも、その間に、三平は足台から登って、老人の前に跨がる。
「フ、どうだ。馬はいいだろう。」
老人上機嫌である。だからまた言って見る。
「村を出たら走らそうぜ。競馬のように走らそうぜい。」
「フ、走らせも出来ない癖に。」
応酬してお婆さんも言う。然し、作蔵が手綱をとって、馬を門の方へ引出しかけると、
「作蔵さん、自動車に用心して下さいよ。それから墓山の下では、必ず下りて貰って下さいよ。道々もあなた手綱を放さないでね。
お婆さんは言ったのである。然し山高帽の老人と、小学一年の三平とが乗っている姿は、お婆さんならずとも、全く危かしく見えたのである。乗っているのでなく、二人は乗せられているのであった。それでも、心配そうに見送っているお婆さんに聞えよがしに、
「ハイヨ――ッと一つやるかな。ハッハハハ。」
老人はふざけたりした。これを聞いて、後からお婆さんが大声で呼んだ。
「いけませんよッ、お爺さん。」
と、お爺さんは言うのである。
「お婆さん大変なわからず屋だからなあ。お婆さんのいうことなぞ聞いていたら、何一つ出来りゃせんぞ。そうだろう、三平。」
三平に言ってきかせながら、馬にゆられてゆくのであった。村はずれの石橋を渡って、野道にかかると、一面の菜の花畑とゲンゲ田圃の彼方に白い墓の列んだ山が見えた。
「あそこ迄だからなあ。訳はないよ。」
ところで、橋を渡って、小さな川沿いの道を行っていると、ザボッと、水の中に音がした。
「あれッ、今の音は何だ?」
「へ?」
響をとって歩いていた作蔵が、馬をとめて、川の中を覗く。
「あッ、旦那、鯰です。大鯰です。三尺はありますぜ。」
「なに、鯰? フーン、捕れないもんかな。」
「そりゃ、網か釣竿でもなけりゃ、手ぶらじゃ捕れませんよ。」
「そうか。じゃ、まあ一つ、馬から下ろしてくれ。なあ、三平、二人で鯰見ような。」
三平から老人と、順々に作蔵は抱き下ろした。老人は岸から水底の藻の陰を覗き、
「捕りたいもんじゃなあ。」
と、三平に言う。
「ボクも捕りたい。」
「ウ、捕りたいか。ホウ、そうかそうか。」
お爺さん大喜びで、作蔵に言うのである。
「のう、作蔵、直ぐ家へ行って網と釣竿をとって来てくれ。おれ達はここで鯰の番をしている。」
「へいへい。」
「ウン、この馬に乗ってってくれ。」
「ハイハイ。」
作蔵は馬に乗り、駈け足で、村の方に帰ってゆく。お爺さんと三平は川端にしゃがんで、川底を覗きながら、
「逃げんな、逃げんな、逃げんな。」
「寝とれい、寝とれい、大鯰。」
口の内で言いながら、首を延ばしたり、縮めたりしている。五分、十分、二十分。
「作蔵の奴、永いなあ。網が見えんかな。釣竿がわからんかな。まさか、い眠りしている訳でもあるまい。」
そう言いながら、村の方を見たり、鯰の方を見たりするその間に、お爺さんは若い頃のことを思い出す。
「この川でのう、お爺さんは四尺もある鯰をとったことがあるんだぞ。」
「フーン。」
「八月、暑い頃の晩だった。鯰のポカン釣りと言ってねえ、鉤に青蛙をつけて、岸の近くをチョンチョンと、蛙が飛ぶ真似をして見せるんだ。ガグッと来たね。竿が折れそうにしなった。あんな鯰はもう今頃は、この近辺にいなくなった。もう六十年も昔だからなあ。」
言ってるところへ、村から馬上の作蔵の姿が飛び出して来た。
「ホ、来た来たッ。」
馬の蹄の音も高く、作蔵は長い竿を肩にかつぎ、その根元に大きな籠をぶら下げていた。馬が駈けるので、その竿は空の上の方で上下にしなう、籠は籠で激しく躍って、彼の頭を叩いていた。いや、そればかりか、彼は腰に網を刀のようにさしていた。馬賊か何かのような物々しい姿であったが、兎に角、勇敢に馬を飛ばして近づいて来た。然し余り勇敢にやられても、老人は困るのである。鯰が足音で逃げるかも知れない。だから、
「やあ、来た来た。大変な勢だぞ。」
そう言いながらも、老人は鯰の場所から立上り、水底を覗き覗き、五間も十間も作蔵の方へ歩き出した。そこで両手を拡げて、馬を止める形をした。
「御苦労御苦労。」
作蔵は手綱を引き絞って、後に反り返り、やっと老人の前で馬を止めた。フフフ言って、まず馬上から竿を渡し、籠を渡し、網も腰からぬき取った。と、その時である。三平が大声で言った。
「あれッ、鯰が逃げちゃった。」
それはというので、老人と作蔵、三平の処へ駆け寄り、川の中を首を延ばして覗き込んだ。大鯰の影も形もない。三人は呆然としてしまった。施すすべもないのである。が、老人は突然反り返り、大声を上げて笑い出した。
「ハッハハハ、墓参りの途中で、殺生しようというのが間違っていたんだ、逃げられてよかったよ。」
と、作蔵も汗をふきふき言うのであった。
「そのことで実は大奥様からサンザン叱られまして――」
これで老人はまた、ハッハハハと大笑いをしたのである。再び墓参に出発することになったが、竿や網が邪魔である。見廻すと、側はゲンゲと菜の花畑。そこでゲンゲ畑の中にそれら三つのものを隠し、帰りに取ってゆくことにした。老人と三平は馬上に押し上げられ、作蔵が馬の口をとり、ノソリノソリと出発した。馬上で老人は言うのである。
「三平、此度、川の中に鯉がいたらどうする?」
「どうもしないや。竿をとって来たりすると、また逃げてしまうんだもの。」
「だって、五尺もある大鯉だぞ。」
「そんな鯉なんかいませんよッ。」
「そりゃ、解らない。もしかいたらと言うんだよ。」
「いたら言ったって、いないんだから仕方がない。」
「だから、もしもと言っているじゃないか。」
そんなことを言ってる内に、もう道は川から離れ、墓山の近くにやって来ていた。いよいよ坂道にかかる処で、作蔵が言う。
「旦那、どうなさいます? 大奥様は、坂にかかったら下りて貰えと仰言いましたが。少し危う御座いますけれど。」
と、老人は言う。
「何を言う。坂道こそ乗せて貰わなけりゃ。歳よりに坂を登れって、それこそ殺生というものだ。」
「へいへい。では、成るべくユックリ登らせます。」
幾曲りかして、やっと墓地の下についた。そこで馬を下りると、老人は側の林に馬をつながせ、先祖代々の墓場に登って行った。登って行ったが、別に線香を供えるでもない。手を合しもしない。まず言ったことは、
「おう、こりゃ仲々いい眺めだ。」
首を延ばして、四方を眺めやる。
「のう三平、いい景色だろう。」
そんなことも言う。眺めは、東の方に――市の城が見え、南の方に瀬戸内海の白帆が見える。北は山ばかり、西は平野の果に一筋の河が光り、その先に小さな汽車が煙を後に引いて走っている。遠望をほしいままにした後、老人は近くを眺める。その山は北から南の半分へかけて、白や灰色の墓ばかり。これは老人に少し気に入らない。然し南半分が谷になっていて、そこには松林の間に畑があった。西方は林である。その林を見ている内、老人はここで鳥を放して見たくなった。だって、その昔、そうだ、七十年から昔老人の父親が亡くなった時、ここで放鳥というのがせられた。目白や文鳥や、それから鳩などが美しい籠から、空へ向けて放された。すると、それらの鳥は一度に林へ向けてバタバタと飛んでゆき、しばらく其処の枝の上で鳴き交し、また枝から枝へパッパと飛び交した。それから目白や文鳥はどうなったか覚えていないけれども、三羽の白鳩は高い空の上に舞い上り、互に列んで、岡山の町の方をさして飛んでった。幼い子供であった老人は、その鳩が見えなくなる迄見送っていたが、空の蒼さの中で、鳩の白い翼がパッパと見えたり見えなくなったりした。その光景は今も眼底に残っている。それが今、見たくてならなくなった。それで作蔵に言った。
「作蔵。」
「へい?」
「気の毒だがな。町へ行って、鳥を買って来てくれ。」
「へー?」
「ここで放鳥をやって見ようと思うんだ。」
「へー。」
「鳩を二三羽と、小鳥を、何でもいいから五六羽買って来てくれ。」
「へーい。」
「馬に乗ってな、籠と金とは家から貰ってくれ。大急ぎだぞ。一時間くらいしか待てんぞ。」
「へーい。」
然し作蔵は浮かぬ顔をしている。内心少し不賛成なのである。然し林に下り、馬を引き出し、馬に向って、
「この野郎ッ。」
などと舌打ちをしながら、大急ぎで、坂道を下って行った。作蔵が村に向って駈けてゆくのを暫く見送った後、老人は側の三平に気がついた。三平は所在なげに唯だ立っているのである。その三平の姿を見ると、老人はまた自分の幼時を思い出した。ここで、彼は三平くらいの頃、大声を出して、遠くのコダマを呼んだのである。あれを聞くと、何だか山の彼方、谷の彼方に沢山の子供がいるような気がして、俄にそこら中が生き生きと賑かになったものである。それを聞きたいと、近頃思い思いしたのである。殊にこの墓場に来る時が近いことを考えた時、そのコダマを思い起したのであった。で、三平に言う。
「コダマというの知ってるかい。」
「知ってるよ。」
「やってごらん、面白いぞう。」
三平はニッコリし、
「おーい。」
と呼ぶ。
「オーイ。」
「オーイ。」
「だれだーい」
「ダレダーイ。」
「ダレダーイ。」
「面白いねえ。」
そう言っておいて、さて、一つの墓に腰をかけ、煙草を吸い始める。吸いながら、今に作蔵が買ってくるであろう、鳩や小鳥のことを話している。と、あれ、町へ向った筈の作蔵の馬上姿が、村からもうこちらをさして駆けている。
「お爺さん、作蔵、もう帰って来ているよ。」
三平もそれに気がつく。
「ふーん、馬鹿に早いなあ。」
と、間もなく、作蔵は山へ登り始める。その時には、彼が籠一つ下げていないことも分明する。
「お爺さん、鳥なんか持っていないよ。」
「そうさ、どうしたんだろうね。」
林の処に駆けつけると、馬から飛び下り、それをつなぐのもそこそこ、作蔵は墓地に駆けのぼる。
「旦那、いけません。大奥さまが大変御立腹です。」
「ハッハハハ、婆さんのケチンボウめ、ハッハハハ、何か言うとは思っていたが――」
「へい、直ぐお帰り下さい、そう御ことづてで御座いました。」
「ハッハハハ。」
仕方なく、老人、三平は馬に乗り、墓山をソロリソロリと下った。
「あいつ(、、、)なんかに何が解るものか、のう作蔵、女というものは馬鹿なもんだぞ。」
馬上で老人は言いつづけていた。
さて、その夜のことである。老人は夢を見た。夢の中で自分は死んでいた。いや、死んでしまっていた。だから、もうこの世に、この村にこの家にいない筈なのだが、やはりいるのでは理窟に合わない。然しそこが夢なのであろう。彼はまず不思議を覚える。だって、自分が死んでるのに、この世この村この家から姿を消してしまっているのに、何も変った様子が一つもない。そこで、その辺を見て廻ることにする。茶の間へ行って見る。飯台があって、長火鉢があって、鉄ビンがあって、めしびつがある。おひつのフタを取って見ると、中にはやはり御飯がある。
「変ってないなあ。」
そこで此度は村を見て廻ることにする。門を出てゆくと金作に会う。鍬をかついで、田圃にゆくところである。
「金作さん、村は少しも変っていませんね。」
たずねて見る。
「私は死んでるんですがね。」
そこ迄は言いかねる。然し何故言いかねるか解らない。
「へい、変りはありませんよ。」
金作が言う。
「お宅の柿の木、やっぱり実がなってますか。」
「へい、今年は毛虫が沢山つきましてねえ。葉をスッカリ食べられました。」
「ホウ、それで、毛虫はやっぱり刺しますか。」
「ええ、刺しますとも。虎毛の毛虫ですからね。」
と、もう老人は柿の木の下に立っている。柿の木は枝という枝、幹という幹に、虎のように黄色の毛を生やした毛虫が一杯ついている。刺すか、どうか験して見ようかと思うが、見ただけで、もう痛いような感じがする。やはり毛虫は刺すことに変りはないのである。
と、もう、彼は栄次の家の納屋の軒下に立っている。眼の前に五六羽の鶏がいて、コッコココと鳴きながら、土の上に散っている小米をつついている。側の箱にしゃがんでいた一羽の鶏が宙腰で立ったと思うと、敷藁の上に白い卵を生み落した。
「ホウ、鶏はやっぱり卵をうんでいるな。」
老人は感心する。
と、此度は、何処だか知らない、樹の幹を前にしている。その樹の幹には、一匹の蝉がとまって、ジーイ、ジーイと鳴いている。
「やっぱり蝉が鳴いている。」
老人は考える。
と、此度は、やはり何処とも解らない土の上を、ピョンピョンと、一匹のコオロギが飛んで来た。コオロギは老人の眼前でとまり、二本の長い触角を立てたり倒したり、代る代るやりながら、その飛び出してくる黒い眼では、じっと老人を眺めている。いつでも、後に立ててる足で、土を蹴って逃げ出そうと用意している気配である。
「ホウ、やはりコオロギもいるわい。」
変っていないことばかりである。
と、此度は眼の前に一人の子供が現れ出た。白いシャツに白いパンツ、ツバの広い経木の帽子を冠っている。四辺が眼がさめるように明るい。
「ハア、夏だな。」
老人は気がつく。子供は片手に竿をもち、竿の先には糸でくくったヤンマをつけている。ヤンマは空中をクルクル廻っている。黄ろい虎斑(とらふ)の本ヤンである。一方の手には、もう捕った一匹のヤンマを指の間にはさんでいる。それも黄色のシマのあるトラフヤンマ。と見る間に、眼前にあるのは、美しい紅白の花が咲き乱れた一叢の罌(け)粟(し)畑、その上で子供はヤンマの竿を振り廻す。
「ヤン来うい。ヤン来うい。」
子供は呼ぶ。そうだ!その子供は三平である。三平なれば、老人、話しかけなければなるまいに、話しかける気がしないのである。何か、三平を驚かしそうな気がする。だって、自分は死んだものだからである。然し、この光景だけでも、死後、この世の変らないことが解る。老人は何だか、安心と共に、明るい気持になったのである。そしてまだ、石橋の下の石垣の穴にいる鯰を見てゆきたいと考えたのであるが、それは見残して、家の方に帰って来た。家に帰ると、奥の間の重ねタンスの小抽出しを開けた。そこにはいつも金が入っていた。覗いて見ると、少しも変らない。やはり銭入れの小箱がある。その中で五十銭三つ四つが白く光り、幾つかの銅銭の中にねころんでいる。片隅に紙幣が四つに折って置かれている。十円サツ二三枚らしい。
この辺で老人は眼がさめた。不思議な気持は、さめての後も残っていた。いや、それは自分が生きているのか、死んでいるのか解らない気持であった。それで床の上に半起きになり、四辺をキョロキョロ見廻した。まだ真夜中と見えて燈火(あかり)一つない真暗である。
「エヘン。」
老人は咳払いをした。
「エヘン。」
次の間で、お婆さんが咳払いをする。それで老人は初めて生きていて、今眼がさめたことを感覚で知ったのである。
「ハ、夢か。」
そう言って、彼は床の中に再びもぐった。
翌朝のことである。老人は床の上に起きて坐って、昨夜の夢を思い出した。そして不思議な気持がした。その不思議というのは、自分が死んでるのに、後に残ったこの世が少しも変らないことを不思議がるのではなかった。死後、この世が変るように、夢の中ででも考えたことを不思議に思うのであった。変る筈がない――今はそう思えるのである。例えば、何日か学校を欠席すると、その間に学校が変ってしまうように思われる。然し実際は何の変化もないのである。けれども、人はみな考える。欠席して居りながら、学校の有様が解るようぬ、死んで居りながら、この世の有様が解ったら! 老人の夢はそんなものででもあったろうか。
「ハ、ハ。」
老人はそう考えて、一人で笑い棄てた。つまり死ぬるということは、この世の中を欠席するようなものだ。いや、退校か、それとも卒業か。この世の中から消えて無くなることである。そう思うと、永い生涯に考えていたように大変なものとは思われない。が、然し、そう考えると、何とまた、この世の中の美しく思えて来ることであろう。あれもこれもと、見たいものが次々頭に浮んで来た。そこで、食事の時、お婆さんに言った。
「婆さん、おれは久しく虹を見ないように思うがな。」
「そうですか。」
何を言うかとお婆さんは相手にならない。
「近頃虹は立っていないか。」
「立っていますとも。」
「フン、立ったら教えてくれ。」
「直ぐ消えるものですから、教えてあげます間なんかありませんよ。雨が降ったら、外へ出て御覧なさい。」
老人は腹を立てた。そこで暫く黙っていた後、フト他のことを思い浮べた。
「婆さん、何処かに小鳥が巣をかけていないかね。」
「かけてるでしょう。」
「どこにかけてる!」
「そんなもの、気をつけていませんからね。作蔵にでも、おさがさせなさいませ。」
「フン、じゃ、作蔵を呼びなさい。」
作蔵がやって来る。
「小鳥がどこかに巣をかけていないかね。」
「へー、心当たりはありませんが、何でもおとりになるんで?」
「ウウン、覗いて見るばかりなんだ。」
「へー。」
作蔵は納得のゆかない顔をする。老人は幼児に覗いた小鳥の巣、童話にあるような卵を抱いた小鳥の可愛らしさを思出していて、それを見残したくない気持がするのである。小鳥の巣ばかりではない。幼児に高い木の枝に登って、小鳥の巣を覗いた時、そこから村の方々を鳥瞰した。その時の驚嘆、それを再現したい気持なのである。そこで言う。
「そうだ、土蔵の裏の柿の木な、あそこに梯子をかけておいてくれ。」
「へ、何になさいます?」
「ウン、後で登って見る。」
「へ?」
作蔵が驚くと、お婆さんもビックリする。
「何を言ってらっしゃいます? 八十にもなって、まるでイタズラッ子じゃありませんか。三平に笑われますよ。」
「ええ、黙っとれ。婆さんなんかに何が解る。」
「いいえ、解ります。高いところに登って、さも自分が元気だってことを、みんなに自慢したいんでしょうが。そんなことをなさっても、誰一人感心しやしませんよ。笑われるばかりです。作蔵さん、梯子なんかかけちゃいけないよ。」
「へいへい。」
「解らず奴が!」
老人は怒ってしまった。が、全く老人は巣がなければ鳥瞰をほしいままにしたいばかりであった。八つの時か、九つの時か、木の枝の上から下を見たら、空中が霞んでいるように見えたり、そこで空気が渦を巻いているように見えたり、遠い遥かの下の方に玩具の国のような世界があるように思えたりしたのである。死期近い今、是非その感じを再現して見たかった。然しお婆さんが、そんなに言って見れば、今はもう、その企も不可能である。それで、その内一人で梯子を持ち出すことに考えを決めた。お婆さんは老人がまた不機嫌に黙ってるのを見て、機嫌とりに言うのであった。
「高い処へお登りなさりたいなら、何処でも二階に登って窓から外を御覧になれば気がすむでしょう。」
「いいよ。登りたくないよ。三平が笑うからな。ハッハハ。」
皮肉を飛ばすと、此度はお婆さんが怒って立ち上る。用もないのに、奥の間の方へゆくのである。行き行き捨ぜりふを残す。
「口ばかり達者なお爺さん。」
「なにい、口が達者なのは、そっちのことだ。」
この時、永い老人の朝飯はすんだ。彼は縁側で煙草をすった後、杖を持って外に出てゆく。村をもう一度一めぐりしなければならない。もう一度どころか、毎日めぐるのであるが、日が変るごとに、今日のこの日の村の有様を見ておかなければと考えるのである。
老人は杖を引きずって、暖い日の照っている村道をやって来た。ある家の側、そこには大きな柿の木があり、その下に瓦でつくった小さな祠がある。後は長い築地、その築地の屋根には一匹の猫が眠っていた。そこで一人の小娘が赤ん坊をおぶって、身体をゆすりゆすりあちこちしていた。そして子守唄を唄っていた。その子守唄に老人は耳をとめた。久しく聞いたことのない唄である。いやいや、聞いても今迄は耳にとまらなかった。然し、気がついて見ると、これも聞いとかなければならない唄である。
「ねんねん、ころりよう、おころりよう。
ねんねの守りは、どこへいたあ。」
昔ながらの唄である。然し昔ながらのものだけに尚お老人は聞いておきたかった。見ていては、小娘がやめると思って、彼女に背を向けて、道端に立った。杖をついて休んでる振りをする。心持が唄と共に、遠い遠い蒼茫の彼方、七十年も昔の幼年の頃に引張ってゆかれる。ブーン、ブーンという音が聞こえるような気がする。それは老人の母が廻した糸車の音である。その頃は綿から糸をつむぎ出した。その有様が眼に浮んだ。いいことを思い出したと、老人の気持は楽しく満足した。と、その時、五つ六つの子供が築地の彼方から駆けて来た。
「姉チャン、おはなし。」
「おはなし?」
「してくれるって言ったじゃないか。」
「そうだったかしらん。」
「さっき言ったじゃないかッ。」
「じゃ、しよう。だけど、一つだけ。いいかい?」
そして小娘は、後向きの老人に気もとめず、やはり赤ん坊をゆすってあちこち歩きながら、一つの話を話し始めた。老人は、いい処へ来たとニッコリして、煙草を吹かしながら聞き入った。
「昔々、ある処に一つのお山があったとさ。その山の下のところに、一つのお寺があったとさ。そのお寺の境内に、一つのお池があったとさ。その池には蛙が沢山住んでいた。春のお彼岸になった時、蛙達は蓮の葉の上に寄り集って、ガアガアガアガア、お彼岸には何の御馳走して食べようかと、頭を集めて相談を始めた。一匹の蛙の言うことに、彼岸の御馳走はお餅ということに決ってる。すると、他の蛙達も、そうじゃ、そうじゃと賛成した。そこで池の岸に臼ををすえて、ベッタラコウ、ベッタラコウとつき始めた。すると、其処へ山から猿がやって来た。その山猿の言うことに、蛙々、お前達ゃ一体何をしてるんだ。蛙達のいうことに、おれ達ゃ、お彼岸餅をついてるんだ。これを聞いて山猿はへらへら笑い、蛙の癖に、彼岸餅もないもんだ。どれ、頂戴致しましょう。そう言うと、臼ごと餅を引かつぎ、山の方へ逃げてしまった。蛙どもは大勢ガアガア泣き立てたが、一匹の賢い蛙が泣かずに猿について行けと言ったもので、また大勢はピョンピョンピョンピョン、山の方へ跳ねていった。と、どうだろう。山の坂道の途中の処に、餅がころんで落ちていた。これを見つけて、蛙どもは、ゲグゲグゲグゲグ、大喜びして食べ始めた。
ところで、猿は家へ帰って、臼を肩から下ろして見ると、中は空っぽで、餅はない。これはしまったと、引返し、途中まで来ると、大勢の蛙が食べていた。猿が怒って、その餅よこせっ。蛙も怒って、そんならこれでも食うがいい。食べ残しの餅を猿の顔へぶっ付けた。猿はビックリして、大急ぎで、その餅を顔からはぎ取った。ところが、余り急いだもんで、顔の皮も一緒にピリピリはいでしまった。それでお猿の顔は、今のように赤くなった。ね、お猿の顔は今でも毛がなくて真赤でしょう。餅をとった罰だとさ。これで、おしまい。また、こんど。」
この時、老人はそっと後を向き、子供の方を見ると、築地にもたれて、頬を赤くして聞き入っていた。この話はやはり七十年前、彼が母からよく聞かされたものであったが、今迄忘れていて、今、この生涯の終に近く思い出さされた。それを思うと、子供に向って、ほほ笑みかけずに居られなかった。そしてニコニコして、彼の頭を撫でてやった。それから満足の思いで頭を一杯にし、家をさして帰って来た。他に何一つ見なくても、その日はそれでいいように思えたのである。人生は今日、老人にとって、それ程楽しい美しいものと思われた。
翌朝のことである。老人は縁側に相変わらず煙草の煙を立てながら、今日何かいいことはないかと考えていた。と、
「そうだ!」
口に出して言うほど、いいことを思いついた。少し早いが、五月の節句の飾りをやって見たくなった。
「婆さん。」
お婆さんに叱られる癖に、何かというと、彼女を呼ぶのは、永い間の習慣であろう。
「作蔵に言ってな、庭に鯉幟を立てさせてくれ。」
「また、そんなことを。今はまだ四月ですよ。」
「四月でもいいんだい。五月までは待たれないよ。おれは節句の飾りが見たくなった。威勢がいいからな。」
「困りますね。そうでなくても、モウロクとした噂が立っているんですよ。」
「人の噂がなんだ。人の寿命は明日がわからん。この世の御免をこうむる前に、見ときたいものがドッサリあるんだ。」
「へいへい。」
お婆さんが引込むと、久しぶりに老人はお婆さんの後姿にニッコリした。
「フフ。」
一人で笑えて来たのである。彼方ではお婆さんの声が聞こえた。
「作さん、鯉幟を立てるんだとさ。それから、お花や。」
女中を呼んでいる。
「土蔵から武者人形を出して、座敷の床の間に飾っておくれ。」
待つ間もなく、庭では三間の大鯉が空高く風にひるがえった。床の間では、武者人形がその鎧甲を春の光に輝かした。
「ハッハハハ。」
一人で老人は悦に入っていた。そして二時間、三時間も、それらを眺めて、茶をのみ、煙草を吸い、煙草を吸い、茶をのんだ。その内、老人は疲れて、縁に横になり、鼾をかいて眠り始めた。眠りの中で、老人は夢を見ていた。縁の前の庭で獅子舞いの獅子が舞っている。側で太鼓と横笛が鳴らされている。横笛の音は老人が好きなだけに、リュウリョウたる音である。何処から飛んで来るのか、花びらがチラリチラリと、舞う獅子の上に落ちて来る。
眼がさめたら、老人、きっと獅子舞いを見たいというに違いない。然し彼は中々眼をさまさなかった。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763