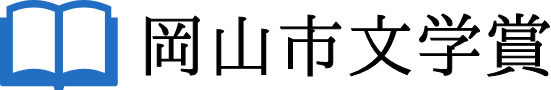おじさんの発明
善太は発明家のおじさんを持っていました。そのおじさんは機械も発明すれば、お薬も発明します。時にはお話なんかも発明して、善太に聞かせます。そこで、ある日、善太はおじさんをたずねてたのみました。
「おじさん、一つ発明して下さい。」
「何を。」
「とってもむずかしいものなんです。おじさんに出来るかしらん。」
「さあ、云って見なさい、聞いて見なければわからん、出来るか、出来ないか。」
「では、言いますよ。」
そう言って、善太は言いましたが、そのお願いの発明というのはつまりお話の箱なんです。蓄音機のように、ハンドルを廻すと、いくらでもお話をしてくれる、それも、いくつでも、いくつでも、変ったお話ばかり、同じ話は決してしない。それにまた、映画のように、お話の絵をうつしてくれる、これもまたいくつでも、いくつでも、変ったお話の絵ばかりで、決して同じ絵は二度とうつさない。そういう機械を発明して下さいというのであります。
「フーン、こりゃむずかしい。蓄音機と映画の機械を一緒にして、これを生きたものにしなけりゃならないようなもんだよ。」
「いえ、生きてなんかいなくていいんです。ただ、同じものばかりだったらあきるでしょう。だから、あきないようなものをお願いするんです。」
「わかった。わかった。一週間ほどたったら来て見なさい。」
「え、一週間でいいんですか。」
「いいとも、明日でもいいけど、まあ、一週間としておこう。」
さて、一週間たちました。善太は姉さんの美代子を誘ってやって来ました。
「おじさん、来ましたよ、出来ましたか。」
「フフフン。」
おじさんは笑って居ります。
「え? 出来てないんでしょう。」
だけども、おじさんの笑い顔には、どうやら大変な自信があります。そして、
「では、まずお目にかけるかな。」
そう言って、一つの部屋に二人をつれて行きました。どんな部屋でしょう。何にも変ったものはありません。応接間のようなところです。真中にテーブルがあって、その上には四角な箱がおいてあります。箱と言っても、外から見たところ、何の仕掛けもありません。ただ、中のゼンマイをまくのですが、ハンドルが一つついて居ります。
「では一つ、蓄音機の方をやって見せよう。しかしだね。まだ発明したばかりで、充分完成されて居るというわけにはゆかないんで、初めは何だかわけのわからない音が出て来るんだよ。それをしんぼうして、ようく聞いていると、次第次第に話になって来る。そこのところをよく聞いていてくれたまえ。君達の実験で、おじさん次第に改良して行くつもりなんだからね。」
そう言うと、おじさんは、その部屋の、重いカーテンを下しました。すると、その部屋が真暗になってしまいました。
「何だか、気味が悪いわね。」
美代子が言いますと、おじさんはスイッチをひねって電燈をつけました。
「いやね、暗くしておかないと、君達の気が散るからね。気が散ると、小さい声だから聞きにくいからね。それにこのカーテン、防音装置の一つなんだよ。では聞いてくれたまえ。おじさんはすぐ隣りの部屋にいるんだから、声をかけてくれさえすれば、すぐやってくるし、それに、実験は二十分なんだから、二十分たったら、声をかけなくてもおじさんの方でやってくる。では―。」
そう言うと、おじさんは箱のハンドルを廻し、電燈のスイッチをひねり、そして外に出て行きました。二人は暗い中で、一生懸命に首をかたむけ、機械から出る音に聞き入りました。ところで、どんな音が聞えたでしょう。初めはゼンマイのとけて行く音でしょうか。ギチギチというような音がしました。ついで、蓄音機のレコードをあの針がすって行くような、シュシュシュ―という音がして来ました。善太も、美代子も、一言も聞き落すまいと、それこそ一生懸命眼をつぶり、一生懸命耳を開いていたのですが、どうしたことでしょう。いつまでたっても、そのシュシュシュ―ばかりなんです。そのシューの奥に、きっと何か言葉がまじってるだろうと、片方の耳をその箱の方に近づけ、もう箱とコッツリする程にしているのですけれども、どうしても、それ以上は聞きとれません。そして長い時間がたちました。と、パッと、ドアが開き、外の光がさし入りました。おじさんが戸口に立って、まだ耳を箱にくっつけるようにしている二人を見ながら、ニヤニヤ笑って居りました。
「どうだったい。お話聞いたかい。」
「だめですよ、おじさん、何にも聞えないの、ボクの耳悪いのかなあ。」
善太が言います。と、姉さんの美代子も言います。
「私もそうなのよ。スースー言う音ばかり、この機械こわれてるんじゃないですか。」
「フーン。」
おじさんは考え込みました。そして、
「では、一つ、今度は映画の方を見てもらおう。これもまだ完成してないんだ。一つでも二つでも何か見えりゃいいとしなけりゃならない。」
と言って、箱の一方を開き、中の機械をいじりますと、そこに電燈がパッとつき、光は部屋の一方のかべを照らしました。そこにはちゃんと用意の白い布がつるされてありました。
「では、見てくれたまえ。」
そう言って、おじさんはまた機械のハンドルを廻し、かべを照らす光が次々に廻転して、異様な姿を映すようにしました。そして部屋の電燈を消して、外の廊下へ出て行きました。それからまた二十分です。善太も美代子も、その白布に映し出されて、次々に移って行く薄暗い影のような光を見つめていました。丁度映画の何もうつらない空あきのような影なんですが、然し何かうつるだろうと、それこそまた一生懸命なんです。今度は耳を忘れて、眼ばかり前へ飛び出させ、いや、顔も前へ突き出していました。が、いつまでたっても、すべって行くのは曇り日の日影のようなうすずみ色の光ばかりです。
「どうだったね。」
またおじさんがやって来ました。
「ダーメ。」
美代子が言いました。
「ダーメ。」
善太も言いました。
「そんな筈はないんだがなあ。」
おじさんは言いました。
「それじゃ、おじさん、私達と一緒に実験して下さらない。そして一々説明して下さいませ。そうすれば、何が何だかわかると思うんだけど。」
「フ、フフ。」
おじさんは笑ってしまいました。
「まあ、もう少し機械を改良してからのことだな。」
さて、それから二十年たちました。月日のたつのって、よほど早いものと思われます。善太も美代子もスッカリおとなになり、いやお父さんや、お母さんになりました。そしておじさんは白髪のお爺さんになりました。その頃になって、善太はフッと、其の時のことを思い出しましたが、機械がお話をしたか、それともしなかったか、したとすれば、どんな話をしたか。それが思い出されません。またその時の映画の機械がどんなお話をうつし出したか、それも思い出されませんでした。それで、姉さんの美代子にあった時、その話を致しました。と、姉さんは言いました。
「そうねえ、そんなことがありましたねえ。考えて、思い出してみましょう。」
一生懸命姉さんは考えました。
「そう、そう。」
やっと姉さんは思い出しました。
「ガマの話よ。」
「え、ガマですって?」
「ええ小さなガマがやしきの隅の土の中に穴を掘ってすんでいました。それはイタズラ好きのガマで、まあイタズラを食べて生きてるというようなガマなんですね。蠅なんかでも、普通に捕って行ったのでは食べません。まず蠅をとると、それを紙袋に入れて、あなたが私のところへ来て、ソーラ蠅だあ、バイキンをうつすぞう。そんなことを言って恐がらせる。と、ガマはその蠅を喜んでパクッと食べる。食べるとからだが少し大きくなる。だもんで、あなたは蜂をとり、トンボを捕り、みんな私や小さい子供にイタズラしてからガマにやりに行く。そのためガマは大きくなる。」
「待って下さい。」
善太が言いました。
「そんなにくわしくおぼえていて、それみなホントウなんですか。」
「ええ、ホントウですとも。今、思い出したばかりなんです。つまりね、ガマは雀を食べ、鶏を食べ、ついにはブタや牛を食べさせられ、もう家のような大ガマになるんです。そして一番しまいに、イタズラ小僧善太君の場面になるんです。」
「へえ、ホントウかなあ、それで、善太がガマを退治るんですか。」
「いいえ、ガマに追っかけられて、イタズラしませんイタズラしません、言いながら泣き泣き逃げて行くって言うんです。」
「ウソでしょう、姉さんの作りばなしでしょう。」
「いいえ、そんなことありますもんか。小さい時、その話をしては二人喧嘩ばかりしたじゃありませんか。」
「どうも少し都合よく出来すぎてるなあ。」
善太はそう言いましたが、そこで、姉さんに映画の方をききました。と、映画の方は、そのお話の通りがうつっていたというのでした。どうしてもホントと思えませんけれども、こちらが忘れているもので、たしかなことが言われません。それで二三日考えて見ることにして、姉さんの家を引きあげました。二三日、全く一生懸命に善太は考えました。と、ハッと眼がさめたように思いました。暗い中で聞いた話の声まで、昨日聞いたように思い出されたのです。
「ようし、負かしてやるぞ。姉さん、おとなになってまで、人をからかったんだな。」
そう言うことで、用もないのに姉さんのところへ出かけました。
「姉さん、思い出しましたよ。」
玄関につくと、もうすぐそう言ってしまいました。
「何を思い出したのです。」
「昔のお話の機械のことですよ。おじさん新発明のあれですよ。あれで聞いた話ですよ。この間はスッカリからかわれちゃって。」
「ウソでしょう。私、ちっともからかやしませんよ。この間の全くホントウの話よ。」
「ダメダメ。」
善太は頭をふって承知しません。そして、自分で思い出した話を始めました。
「まずこうなんです。家に一本の木がありました。幹や葉がどうだったかわかりませんが、花は虹色で、年に四度も咲きそろうというとても美しい花だったんです。それは美しき少女の木と言われてました。」
ここまで聞くと、姉さんはニヤニヤしました。
「巧く作ったわね。」
「冗談じゃない。ホントですよ。作りばなしなんか、ワザワザ報告に来るもんですか。」
そして話しつづけました。
「その頃、姉さんはイタズラもので。」
と、姉さんこらえ切れなくなって、大声あげて笑ってしまいました。
「あまり上手な話なんで笑わないで居られませんよ。」
しかし、善太は話しつづけました。
「まあ、終りまで聞いてらっしゃい。つまり姉さんは大変なイタズラッ子で、その花の枝を惜しげもなくボキボキ折って、友達にやったり、自分の部屋にさしたり、時には、花の散るのが面白いって、木をゆすって、ハラハラと散らしたりしたもんです。それでさすがの名木も次第に弱まり、ある秋の大嵐の晩、根元から折れ、大変な音を立てて、土の上に倒れました。ところが、その折れ口から、ふしぎなことに、白い美しい鳥が大きな羽をひろげて、空の上にたち上り、家の上を二三度まうて、その上悲しげな声で二三度鳴いて、そしてどこともなく飛び去りました。あくる日、嵐の静まった朝、そのむざんな木の姿を見て、姉さんばかりでなく、家のものみんなとても悲しく思いました。どうかして、その残った根元から、元のような木を造り上げようと、それこそ、たんせいしたのですが、ついに昔のような虹の花は咲かなかった。―というのが、まず私のおぼえているお話のあらすじです。」
そして、それに善太はつけ加えて、映画の方も同じ話がうつされたと言いました。どうも変なことになりました。二人ともウソではないというのですもの。で、とうとう二人でおじさんのところに落ち合い、この話を致しました。どちらがホントウでしょうかと、問うたわけであります。と、おじさんの言いましたことは、この話のはじめに書かれている通りです。おじさんは話の機械なんか造らなかったのです。では、この二人の聞いたというお話は何なんでしょう。つまり幼い生活の中から、それを聞きとったのであると、私は申し上げたいのですが、その意味がわかってもらえましょうか。幼い善太君、美代子さん、イタズラをしないように、幼少年少女の時代を大切にして、立派な人におなり下さい。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763