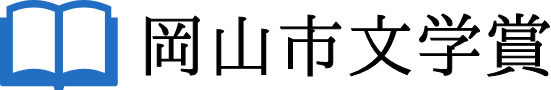夜
ボクたちは討論会を開いた。会場はボクんちのナヤだ。時は土曜日の夜だった。なるべくヒルマやりたいのだが、なかなかみんながそろわない。それで夜ということになった。会員は四人だ。ハチロウ、ヘイゾウ、キンキチ、そしてボクだ。ボクはスギタケシチロウというのだ。
みんなワラを一束ずつもって集まってきた。というのは、ただ討論会だなんていうと、みんなのウチのおとうさんやおじいさんがやかましい。集まって競争でナワをなうんだというと、喜んで許してくれる。もっとも、それだからといって、ウソをつくワケではない。討論会をやりやりナワをない、ナワをないない討論会をやるんだ。一石二鳥、一挙両得というのだ。こういう時代になったら自分の思うことを人に十分、心のこりなくいうということもたいせつだが、ものを生産するということも忘れてはならない。これは学校の先生が言ったことだ。
ナヤの電燈は暗い。五燭光だ。そこはいつもおじいさんがワラゾウリを作るところだ。その電燈をマンナカにして、ボクらは輪になってすわった。まずナワをなう用意をして、ボクが言った。
「じゃ、これから討論会を始めよう。この前は、友だちということについて話しあったね。その前は、家というのが題目だったね。きょうは―。」
いいかけると、ハチロウ君が、いった。
「少し変わった題にしようじゃないか。火とか、風とか。」
すると、ヘイゾウが、
「火はあつい。風は寒いっていうのかい。」
といった。ハチロウはこれをきくと、もう怒りそうになって、
「冷い火だってあるんだぜ。熱い風だってあるそうだぜ。」
「じゃ、その冷い火って、どんな火だい。それをみんなにきかせてくれよう。」
「ホタルの火なんかそうだ。」
「ホタルの火?あれなんか火じゃないや。」
「じゃ、火というのはなんだい。それを説明してくれ、ヘイちゃん。」
もう討論会が始まった。ヘイゾウはちょっと困ったらしく、
「ウーン、火というのはな、ピカピカ光っててね、それから熱くてね、つもり燃えてるもんだな。」
そんなことをいった。すると、キンキチが横から、
「火なんかおもしろくないや。それより夜ということにしないか。おれ、夜について、とてもおもしろい話を思い出したんだ。」
そう、口をとがらせていいだした。キンキチは話す時いつでも口をとがらせるのがクセだ。で、ぼくはすぐさんせいした。夜ならおもしろい話がありそうだ。もしかしたら、ユウレイなんかの話もでてくるかもしれない。理科や社会科の学課にはえん遠い話になるかもしれないけれど、そのほうがこわくっておもしろくなるかもしれない。みんなもそう考えたらしく、
「それがいい。それがいい。」
と口々にサンセイした。そこでキンキチが話しだした。
「この話な、夏おれんちへきていた大学生からきいたんだ。夜についての理科の話ではないんだが。だけどおもしろいんだぞ。いいかい。」
やっぱり、ボクの考えたとおりだ。だから、
「いいとも、いいとも。」
とまたすぐいってやった。そこでキンキチが語りだした。
「つまりな、人間はだれでも夜がこわいだろう。あれはナゼか。そのことなんだ。大学生が読んだ本には、こう書いてあったとさ。人間はなん万年かなん十万年かかかって、アミーバのようなものから進化して、今の人間になったんだってね。それを進化論というのだってさ。で、カエルのような時代もあり、鳥のような時代もあり、サルのようなころもあったとさ。それでね、そんな時はとても夜がこわかったんだって。」
「なんでよ。」
ヘイゾウがまた質問をかけた。
「だってさ、カエルだったらヘビがクラヤミの中をソーッとのみにくるだろう。鳥だと、フクロウもくれば、その他の猛獣もおそってくる。
サルだって同じさ。眠ることもできなかったんだね。それで、そのおそろしさが、今に人間の心の底の方に残っていて、夜になると人間はなんでも
ないのにこわいキモチになるんだとさ。」
「ナゼだい。」
またヘイゾウがいいだした。
「ヘビや猛獣は、ヒルだっておそってくるじゃないか。それがどうしてヒルはこわくないんだい。それにさ、人間進化の途中で、ヘビの時も、猛獣の時もあったんだろう。そうしたら、夜になったら一つカエルをくいに行ってやろうと考えた時もあったんじゃないか。また日がくれたらサルをとって食べてやろうと思った時だってあるだろう。ナゼこわいキモチばかり残っていて、そっちのキモチが残っていないんだい。」
これにはキンキチだいぶよわりこんだ。
「そうだなあ。おれ、大学生にもっとよく聞くんだったな。」
そういって考えこんだ。少し考えてから、
「ウン。」
といって話しだした。
「そうだ。まあヒルのことはわからないさ。しかし夜はだね、人間だって、今ドロボウやったり、ゴウトウになったり、人殺ししたりするだろう。やっぱり猛獣だった時の夜のキモチが残ってんだね。つもり夜になると、それでトラやオオカミのようになるんだね。」
「フーン。」
ヘイゾウはこういって、首をかしげていたが、
「おれにはわかんないな。ナゼ夜ばかりこわく、また夜ばかりオオカミのようになるんだい。ヒルだって、オオカミはオオカミで、サルやウサギをとったろう。それとも、昔、オオカミはヒル人間になっていたのかい。」
こういって、つっこんだ。
「バカッ。」
キンキチはハラを立てた。
「夜は暗くてこわいじゃないか。そのこわさがフツウ以上にこわい。それはナゼかというと、なん万年も昔から、夜くわれたり、殺されたり、こわいことばかりが多かった。そのこわさが、今のように人間の生活が平和な時になってもまだ心の底にのこってる。それを、おれはいっているんだ。いまでも、南方へ行くと、海の上や湖の上にクイを打って、その上に家をたてて住んでる人間の部落があるというんだぞ。それはヒルなら大蛇や猛獣のシュウゲキを受けても、人間は、それを防ぐことができる。夜だと、人間は目が見えないし、またグウグウ眠ってるだろう。だからタヤスク食べられてしまうんだよ。それがこわくて、今はもうそんな大蛇やトラ、オオカミがいなくなっても、まだその習慣がのこっているんだ。それで水の上にすんでる人間の村があるんだ。ヘイちゃん、わかったろ。」
「わからない。」
「わからない?それじゃ、ヘイゾウは夜こわくないのかい。」
「こわい、こわいけど、それは夜のせいじゃないよ。暗いいだよ。暗ければ、ヒルだってこわいさ。」
「そりゃヘイちゃん、まちがってる。」
ハチロウ君がいいだした。
「だって、夜というのは暗いものなんだぜ。暗いから夜なんだぜ。明るければヒルじゃないか。」
「そりゃわかってるよ。しかし暗いというのと、夜というのとはちがうだろう。ヒルだって洞穴の中などは暗いものな、その中へはいれば、ヒルだっておれこわいよ。だから暗いのがこわいんで夜がこわいんではないっていっていいんだ。」
ヘイゾウがこういうと、ハチロウ君もハラを立てていった。
「そりゃヘリクツだ。」
「ヘリクツでもいいや。ホントだもの。」
みんなはだまっていた。ボクもだまっていた。しかしどうもヘイゾウのほうにリクツがあるように思われた。そう思われたけれども、ホントはヘイゾウにサンセイしたくなかった。やっぱりヘリクツだといいたくてならなかった。みんなも、やっぱりそう考えているだろうか。にわかにナワをないだして、あっちでもシュルシュル、こっちでもシュルシュル、忙しそうに音を立てた。外では風が出たらしく、ザワザワいう木のゆれる音がした。たれひとりものをいうものがない。それでヘイゾウは、自分のギロンが勝ったと思ったのであろう。また、こんなことをいいだした。
「夜とかヒルとかいうのは時間なんだろう。時間は目にも見えないし、手でさわることはできない。それがこわいってことはないよ。しかし暗いとか、明るいとかいうのは光りのあるなしだからね。目に見えるものだよ。だから、こわい、こわくないがあるんだ。」
しかしみんなは、これにひとことも返事しなかった。そして一心にナワをないつづけた。ヘイゾウもしかたなくナワをなった。と、トツゼン、パッと電燈がきえた。あたりがシーンとした。ヤミというものは深いキモチのようなものだ。ボクは目が見えなくなったもので、耳のほうに力を入れた。どんな小さな音でもききもらすまいと思ったんだ。すると、自分の耳がヤミの中でピンと立ってきたような気がした。みんなの耳もその時ピンとつき立っていたにちがいない。だって、前よりか風の音がハッキリしてきて、それが吹いては消え、消えてはまた吹いた。ヤミの中の風だから、黒煙のような風のように思われた。この風の音のとだえた時、入り口の大戸がギ、ギといった。誰かきて、戸に手をかけてるように思われた。
「だれですか。」
キンキチがいった。しかし返事はなかった。みんな手をにぎり、ヤミの中に目をこらし、耳を一心にすましているようだった。と、また、ギ、ギ、ギという音がした。
「だれですかッ。」
今度はハチロウ君がきいた。やっぱり返事はなかった。返事はないが、そうきく度、ちょっと音のするのがとまった。しばらくすると、
またギ、ギ、ギと音がする。
「だれ? にいちゃん? おとうさん?」
ボクはきいてみた。声がふるえそうだった。と、ギギがとまって、そこからヤミの中から実になんともいえない、おそろしい声が、
「よ る だ よ う ……。」
と、ふるえ、ふるえ、おしこんできた。ボクは思わず、すわったままカラダをすくめた。一生ケンメイにすくめたので、それこそひとニギリくらいの小さいカラダになったように思われた。それからなん分たったか、なん十分たったかわからなかったが、パッと電燈がついたんだ。みたら、みんな頭をさげて、おじぎしてるようにカラダをすくめていた。今考えればおかしいけれども、ただひとり笑うものはなかった。それからボクは戸のほうを見た。戸はあいていなかった。
「戸があいていないね。」
ボクはそっとトナリのヘイゾウにいった。ヘイゾウはまだ目をパチクリやって、ブルブルふるえていた。そのままボクたちは顔を見合ったまま、久しくフウフウ大息をついていた。いつまでそうしていてもしかたがないので、
「ボクんちへ行こう。」
ボクはいった。それでみんなは、立ちあがった。しかし戸をあけるものがない。それで、ボクが戸のシリのところに手をかけたら、みんな後のほうへのいて、ボクの後のところへかたまってしまった。
「まだ外にいるんじゃないか。」
キンキチ君がいった。それでもボクは思いきって戸をゴロッとあけたやった。それから電燈をとって、外のほうへむけた。ウチの入り口のほうを照らした。入り口まで十メートルとない。それを見ると、ハチロウ君がまずトッととびだして、入り口の戸にぶっつかるほど勢よくとんで行った。キンキチもヘイゾウもつづいた。ボクも電燈をなげすてておいて走った。
戸の中にはいって、ボクたちはやっとフツウに話すことができた。ボクはおとうさんやにいさんに、
「よ る だ よ う。」
と、マネをして話した。おとうさんもにいさんも笑った。そして、
「だれかのイタズラだろう。」
といった。しかしボクたち、ひとりもそうは考えなかった。だって、戸があんなにギイギイいいながら、五センチだってあいてないんだもの。しかも、声は、ヘヤの中でするようにハッキリしていたんだもの。
「オバケだよ。キッと。」
ハチロウ君がいったが、ヘイゾウだって、
「ユウレイの声だと、おれ思ったな。」
といっていた。だけどもフシギなことに、ボクはおばあさんの声のように思ったのに、ヘイゾウはおじいさんの声のようだったというし、ハチロウ君とキンキチ君は、
「よる…………。」
ときこえたという。しかもネコの目のような金色の二つの目が光っていたというのだ。まずそんなことをガヤガヤいった後、三人はにいさんに送られて、それぞれ家へ帰って行った。
ところで、キンキチ君に本の話をした大学生がまた村へやってきた。冬やすみのときだった。それでキンキチが、その夜のオバケの話をした。
すると大学生がいったそうだ。
「ユウレイやオバケというものは、みんな人間の中にいる。人間の心の中に、カラダの中に住んでいる。そしてこれが夜でてくる。いつか、おれが進化論の話をしてやったろう。つまりあれだ。人間のなかには、カエルや鳥も住んでれば、トラやオオカミも住んでいる。オバケだってやはり住んでいるんだ。つもり夜は人間のカラダの中にあるんだな。」
キンキチ君からその話を聞いて、ボクたちは、
「へーえ。」
とあきれかえってしまった。ホントなのか、どうか、今にわからないが、そのウチ先生にきいて見るつもりだ。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763