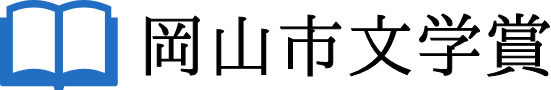子供の猫
青山の家では犬も猫も飼って居りません。三人の子供がいて、上の二人はもう中学生で、末っ子だけが小学生でしたが、その三平が、
「母さん、犬を飼おうよ。」
と言うのでした。けれども、以前に一度犬を飼った処がこれが大変なイタズラ犬で、近所の畑を荒し荒ししたもので、毒でも食べささられたのか、或日突然苦しみ出して、一時間と経たない内に死んでしまいました。それから主人も細君も、もう生きものはコリゴリということになって、
「犬もいいけど、死んだ時に可哀そうで困るからねえ。」
と言うのでありました。
ところが、或日のことでした。赤い首輪をつけた幼い猫がチリチリ鈴を鳴らして、縁側から上って来ました。
「まあ、可愛い猫。」
細君が直ぐに見つけて、
「三平チャン、三平チャン。」
と末の子供を呼ぶのでした。三平は長い帯を持って来て、座敷をソロソロと引張りました。子猫はこれを見ると、一間も離れた処からでも跳んで行って、その端に喰わえつき、それをまた振り廻して、大いに勇ましい処を見せました。三平がその帯を動かさないと、片手でチョンチョンと触って見て、動いたら跳びつこうと身構えたりもしました。これは面白いというので三平ばかりでなく、上の中学生善太まで帯をとって、猫と三四十分も遊び戯れる有様でした。そして、
「おれにやらせろ。」
「ウン、ボクの番じゃないか。」
などと言い合いになったりしました。
「何処の猫だろう。」
細君が言いますと、
「ねえ、母さん、内に飼っちまおうか。」
三平がそんなことを言いました。然し、一時間も経つと、猫も遊び疲れたか、ノソリノソリと縁側の方に歩いて行き、そこから尻を真さかさに、上へ突き立てるような姿勢をして、地面へ飛び下りました。チッチチチチと、みんなが口をそろえて呼びましたが、振返りもしないで、垣根をもぐって、道を越して、行ってしまいました。
「何処の猫だろう。」
またみんなで言ったのですが、それは其後隣家の東弁護士の家の猫だということが解りました。無邪気な猫で、それからは昼過ぎ、子供等が学校から帰る頃となると、ニャーとも言わず唯鈴を鳴らして縁側から入って来ました。天気の日はいいのですが、雨の日も子猫は至って無関心にやって来るので、しかも毎日のこととなったので、一番上の中学生正太君が少し不平を言い出しました。
「猫の奴、跣足でやって来るんでなあ。縁側も座敷もドロンコじゃないか。猫好きの奴、少し何とかしないか。」
そこで小学生三平がゾウキンを持って来て、子猫の足をふいてやることになりました。
「足だけじゃ駄目だぞ。縁側も座敷もふいとけ。」
三平はゾウキンを代えて、縁側座敷をふきました。然しそれ以来猫の係りは三平ということになって、
「おい三平、猫が今台所へ行ったぞ。」
勉強中でも何でも、そう呼び立てられるようになりました。或時など、皿の上の煮肴が少しかじってあったというので、
「三平、この肴、君が喰うんだぞ。」
と、晩めしの時、皿を前にやり込められました。
「そんなことあるかい。」
彼は大憤慨をしたのです。
「じゃ、これからもう猫を家に入れるない。いいかい。入って来たら、おれが追払うぞ。」
正太が言いました。
「そんなことあるかい。」
「じゃこの肴どうする? おれが喰うのかい。」
丁度その皿が正太の前にあったもので、彼も心平かなるを得ずで、そう言って唇を尖らせました。
「おれが喰ってやらあい。」
善太がその皿を引き寄せました。
「やあ、猫肴喰ってやがらあ。汚い奴。」
「あああ、汚い奴さ。おれ、猫の歳なんだからな。」
「じゃ、これから猫の肴ばかり喰え。」
「ああ喰うよ。」
と、此の時三平が黙って、猫のかじったその肴の皿を自分の前に引き寄せました。
「どうしたんだい。」
正太が聞きました。
「ウン、おれが喰うんだ。」
三平が静かに言いました。
「やあ――、みんな猫肴が好きなんだなあ。」
これは正太。
「その代り、これからあの猫おれの猫なんだぞ。誰だって、相手にしちゃいけないよ。」
「あああ、あんな汚い猫、誰が相手にするもんか。」
正太は初めから猫が好きではないのです。
「善チャン相手にしちゃいけないよ。」
「よし、その代り、もう猫のことは三平が一切責任を持つんだよ。」
「ああ、いいとも。」
それで猫は三平の猫となり、以後彼はみんなに猫係りと呼ばれるようになりました。猫係りとなってから、しかし三平は一層猫を可愛がり、猫も非常に彼になつきました。猫の名は「ハナ」というのでしたが、他の誰が名を呼んでも返事をしないのに、三平の呼声ばかりには、ニャーッと言って啼いて見せました。その度三平は、
「ね、どんなもんだい。」
と、みんなに自慢して見せました。そして近所に友達を持っていない彼は、学校から帰ってからの午後、殆ど猫とばかり遊びました。
或時などビワの木の高い枝から綱をぶら下げ、その下にミカン箱を吊し、その中に猫を入れて、綱を引いて上に引き上げました。自分も後から童話の本などを持って登ってゆき、猫を側にして遠く雲などを眺めながら、本を読んで空想の世界を心のなかに打ち拡げるのでありました。猫が下に下りたがると、ポケットからビスケットを出したり、焼イカの一片を出してやったりして機嫌をとって、頭を撫でてやりました。その度猫はニャーオ、ニャーオと甘ったるい声を出して甘えました。
初めの内はそんな有様で、猫係りも猫と遊ぶばかりで、左程猫のために面倒を見ることもありませんでした。即ち猫は三平と遊ぶために午後やって来るばかりで、晩めし頃になると、至極無愛想な表情をして、どんなに呼んでも、サッサと帰って行きました。そして夜は東家の自分の寝場所にねるのでした。寝場所と言っても、それはお婆さんの床でありました。お婆さんはこの猫のハナをとても可愛がり、「ハナはおさしみが好きだ」と言って、毎日さしみを魚屋からとってやり、そして晩はまるで孫のように一つ床に寝かせました。
ところが、そんな有様で月日がたって行きました。猫も幸福なれば三平も仕合せで、何のいうこともありませんでした。すると、半年経ち、十月経ちする内に、いつの間にか子猫のハナが成人の猫になりました。夜など、三平の家の庭の芝生の上で、他の家の猫と気持の悪い声を出して啼き合い、烈しい噛み合いや引掻き合いの喧嘩をするようになりました。その声を聞くと、三平は心配して、夜おそくでも起きてゆき、玄関や縁側を開けて、
「ハナハナ、ハナ。」
と呼ぶのでした。けれども、ハナは余程の喧嘩太郎と見え、そんな場合三平に呼ばれても決して来ることなく、ウーウーフウフウと唸りながら、いつ迄も相手と木の下で睨み合って居りました。でも、まだそんなことはたいしたことではありませんでしたが、ここに猫と猫係りに困ったことが起りました。
或日、春の初めでした。東弁護士の家が、十四五町離れた処ではありましたが、そこへ引越して行ったのです。いよいよ最後の荷物の出る晩方でした。東家の書生さんが、前にオームの飼ってあった籠を下げて、三平の家へやって来ました。
「内のハナが永い間大変御厄介になりました。如何でしょう。やはり参って居りますでしょうか。」
そうして、啼き立てる猫を針金で出来てるその籠の中に入れ、その上を風呂敷で包んで、
「ハナや、ハナ公や。」
そんなことを言いながら、新しい家をさして帰ってゆきました。
「あああ、これでまずホッとした。跣足で上られる心配はなし、肴をかじられることも一寸もなくなったし。」
正太が言うのでした。
「猫係りもらくになったぞ。」
善太も言いました。三平ばかりがつまらなそうな顔をして黙っていました。
ところが、その翌日、まだ薄明りの朝四時頃でした。三平の寝ている枕もと近く、と言っても窓の外ですが、ニャーオ、ニャーオと猫の啼声がするのです。
「ハナ公だ。」
三平は直ぐ眼をさまし、枕もとの窓を開けました。と、ハナは小さい声でニャーと啼きながら窓の敷居に飛上り、それから三平の床の上に行って、さも自分の家に帰ったようにしてうずくまってしまいました。三平が行くと、もうそこで咽喉をゴロゴロ鳴らせていました。つまりハナが東家の新邸にいたのはたった一晩、それも十時間ばかりでした。旧邸と新邸の間には省線電車が通っていて、それこそ間断なく電車が走って居るのでした。それにまた、そこは駅に近いため方々の私設電車が集って居り、これも間断なく走り走りして居りました。その間を、人間なれば踏切があって、難なく通ってゆくことが出来るのですが、猫はそうはゆきません。それに十数町と言っても錯綜している町の路々を、しかも彼女にとっては新知の道をよく訳なくやって来たものであります。
「どうしよう。やっぱり遠くなっても遊びに来るのかしらん。」
そう言っている内に、東家から書生さんが通ってやって来ました。
「ハナ公が参って居りましょうか。」
そしてオームの籠に入れられてつれて行かれました。その翌朝、
「今朝は東さんでも用心してるだろう、ハナが逃げ出さないように。」
そう話していると、ニャーと、ハナ公が縁側の方から入って来ました。
「どうだろう。このまま内に置いておいたら、もう、今度の東さんの家へは帰らないんだろうか。やっぱり来たり帰ったりするんだろうか。」
そう話していると、また迎えの書生さんです。
「どうも御面倒をおかけしまして。」
書生さんは恐縮するのでしたが、青山の家では、その書生さんこそ大変と、大いに気の毒に思いました。その辺まではよかったのですが、猫はつれて行っても、つれて行っても、そして先方でどんなに檻禁しておいても、いつの間にかそこをぬけ出し夜の明けるか明けない頃、必ず三平の床の前の窓の下に来て、ニャーオ、ニャーオと啼き立てました。捨てて置くと、いつ迄でも啼きつづけ、はては家を廻って、窓の明いている処をさがし、終には便所の窓から飛び込む有様となりました。もう彼女は必死の有様なんでしょう。そして夜の明けるか、明けない頃というのは、その頃が、この東京の郊外にとって、一番交通の途絶えている時でありました。そこを狙って猫は脱走して来るのであります。その時以外には決して彼女は来ませんでした。交通の烈しい途中が随分難関だったと思えます。然し直ぐ三平の家へ行く訳ではありません。彼女はまず自分の旧居、とでも言いましょうか、前いた家に入ってゆくのです。そこで台所から茶の間、茶の間から縁側、座敷、玄関と、まず家中を歩き廻って見るのでした。これはその後家主が家に入って見て、猫の足跡の到る処についているので解ったことです。彼女として見れば、動物だけに、新居がどうしても、自分の棲いと思えないで、
「こんな筈はないんだがなあ。」
と、しきりに同じ家の中を何度でも廻り廻っているものと思われました。つまり引越すなんて人為的なことは、猫には納得が行かないのでありましょう。それで尋ね尋ねた末の足が、仕方なくお隣りの三平君の窓の下へ向うのでした。そしてこれが実に三十幾回、書生さんは朝、青山家へ猫を迎えに来るのが一月間毎日の日課となった訳であります。然し一月経つと、書生さんも弱りましたが、東家の御隠居も望みを捨てました。そして菓子折を持って、
「ハナが大変御厄介をおかけ致しますが、どうかお捨て下さいますなり、それとも折々は食物をやって下さいますなり、どうとも御自由になさって下さいませ。」
と、青山家へ挨拶に来たのでした。
これで、どうやら猫ハナ公は青山家で飼わなくてはならないことになって来ました。その晩その話を聞き、その菓子を喰った子供達の内、
「お菓子は旨いがなあ。」
とまず正太が言いました。それについて、
「猫は困るがなあ。」
と善太が真似をしました。
「ノミがいるんでなあ。」
と、また正太か言いました。丁度その頃暑中休暇が近くなっていて、ハナはノミにまみれていました。
「おい、猫係り、休みになったら、毎日猫を持って、東さんへ通え。もし通わないなら、おれが水をぶっかけて追払ってしまうぞ。」
前の頃と違い、毎日毎日暁方に啼声で起されるというので、正太は加速度を以て猫嫌いになってました。それで、それからの毎朝、猫係り三平が猫を風呂敷に包んで、東家へ通うこととなりました。家に来ると直ぐ摑まえて、頭をポンポン叩き、
「こらっ、ここは貴様の家じゃないんだぞ。もう来るな。来たら、承知しないぞ。来るか、来ないか。」
何度も言って聞かせてやるのでした。そうして、東家の門の前まで行って、そこで風呂敷から出してやるのでした。すると、猫はノソノソと東家へ入ってゆくのでした。それを三四回やった後のこと、ふと猫は来なくなりました。
「有難い。猫係りも役目がすんだぞ。その内、猫祝いというのをやるかな。」
正太がそんなことを言ったりして、十日ばかりも経ったでしょうか。雨が降っている午後のことでした。かすかな猫の啼声を聞いて、
「ハナ公だ。」
三平が言いました。
「また来やがったかな。ようし、今日こそ水をぶっかけて追払ってやるぞ。」
正太が言った時でした。台所の方から母親の声がしました。
「三平チャン、一寸来て見なさい。ハナがそれはミジメナ風で、雨にぬれて、可哀想に――。」
みんなが駆けつけて見ると、台所口にうずくまって、そう啼きもせず、みんなの方を眺めている猫、それはハナとも思えないやせ衰えた老猫です。雨にぬれそぼち、骨ばかりが目だつ有様です。
「どうしたんだろう。」
みんなは言うのでしたが、考えて見ると、ここ十日余り、彼女は空屋になっている東家の旧居にきっと飯も食べずに棲んでいたのです。ところが、一昨日、そこに新しい人が借家して入って来ました。それでそこにも居られず、一二日雨の外をうろつき廻り、いよいよ困って、また三平の家を頼って来たものと思われました。それが解ったので、
「おい、猫係り。」
と、また三平の活躍となり、彼はカツオ節をかいたり、御飯を猫皿に入れたり、大至急猫飯の用意をしました。いや、このハナはとてもゼイタクに育っているので、カツオ節位では飯を食いません。そこでその上に残りの牛乳さえかけられました。
「ハナ、そら。」
そう言って、彼女の近くへその皿を出してやりましたが、彼女は近づいて来ようともしません。唯、ニャーニャーと啼くばかりです。近よったら捕えられ、頭をポンと叩かれると考えて居るらしいのです。
「叩きやせんよ。ホラ、食べろ。」
こんな有様で、正太、善太、三平、みんな総出で、この時はハナをいたわってやりました。その末、ここ台所口で、窮迫瀕死の彼女を前に、家族会議が開かれました。もうこんな有様では仕方がないから、彼女を内の猫として飼ってやることにしよう――というのが母親の意見でした。これに真正面からではないのですが、兎に角、幾多家族としての欠点を挙げて、猫を非難するのは正太でした。そこで、最後に名案が三平から提出されました。つまり彼女を犬のように下に飼おうというのです。しかも従前通り、猫係りとして、訓練飼育に絶対責任を負うというのです。
「上にあがったらどうする?」
正太が問いました。
「上ったらおれが叱るさ。」
三平の答えです。
「叱っても上って来たら?」
「ウン、一週間の内におれがそうしつけをする。その間だけは、少しは大目に見ててくれなきゃ。」
「よし、一週間過ぎたら、今度こそ遠くへ持ってって、川ん中へ投げ込んでくるぞ。」
「ああ、いいとも。」
暑中休暇は始まっていました。それで、即座に熱心な三平の犬としての、猫の訓練が始まりました。
まず、猫は昼は殆ど眠っているのですから、寝床をつくってやらなければなりません。丁度それは犬小屋のようなものです。考え考えた末、三平は物置の積み重ねてある箱の上に、もう一つビール箱を置いて、そこに座蒲団を入れて、ハナを寝かしつけました。中腰になって落着かない彼女を、頭をなでたり、咽喉をさすったり、子供を寝つかせるような苦心をするのでした。その間彼は相変らず童話の本など片手に、ポケットからキャラメルなどを出して、退屈をしのぎました。それでもハナは、三平の油断してるのを、寝たふりをしている横目でそっと見ると、ソロソロと尻を立て始めるのでありました。でも漸く一時間ばかりをそこで過すと、今度は彼女に長い二本の綱を結びつけました。首から胴へかけて、タスキに、ずりぬけないように頑丈に結んだのです。片手には蠅叩きを持ちました。これは鞭になる訳です。そうして、物置から芝生の方へ抱え出し、そこで、三平は鞭を振り上げました。
「こらッ、ハナ公。」
彼で見れば、丁度馬を調教する調馬師というものが、馬場の真中に立って、周囲を円く馬を鞭で走らすように、猫を駈足で走らすつもりなんであります。調猫師になったのです。ところが、ハナで見れば、先刻物置で子供のようにあやされて以来、もうスッカリ気持が甘えていてこの家で飼って貰えるか貰えないかの瀬戸際などとは知るよしもなく、直ぐ芝生の上に仰向けにねころがり、ニャー、ニャーところげころげしました。その有様に、
「こらッ、ハナ公。」
調猫師は腹を立てて、蠅叩きの鞭で、ハナの尻をパチンと一打ち打ち叩きました。と、ハナ公は俄にビックリして、飛起きざまに逃げ出そうとしましたが、タスキの綱で逃げもなりません。後退りしても、前二本の足がぬけません、綱が邪魔をしているのです。今度は彼女が腹を立て、この綱に歯ぶしをむいて喰いつき、それを解こうと、頭を乱暴にふりました。
さて、どうでしょう。調猫が成功するでありましょうか。いずれ、その報告は此の後申上げることと致します。さようなら。
お問い合わせ
市民生活局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763