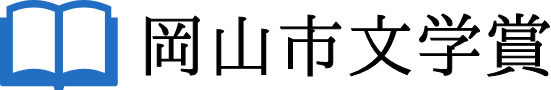善太と三平
それは田圃の片隅である。太い松の木が空高く聳えていた。ガッシリしたその枝には鳥が来てとまったり、鳶が休んでいたりした。頂が高いので、その辺は空気も澄んでいて、きっと温度も低く、息もらくのように思われた。その土地は善太の家のものであったので彼はよく来て、樹の下から高い頂上の方を見上げたのである。
ある日、そこに、高い枝の上に白い鳥がとまっていた。白い鳥は行者か何かを思わせて神秘的な気もするものである。鳩くらいもある白い鳥である、善太は恐ろしい気がした。
然し善太は言ったのである。
「あんなの恐くないやい。」
すると、声が聞えた。
「恐くない?」
「恐くないとも。」
善太は即座に答え、そして耳をすました。
いざとあれば、喧嘩しなければならないし、また場合によっては逃げもしなければならない。然しそれきり声が聞えない。それでもう一度言って見た。
「ああ、恐くないとも! ちょっとも恐くないや。」
そしてまた耳をすましていた。やっぱり声は聞えなかった。すると、相手はどうしたのだろう、もう逃げたか。強くて、もう身辺に迫っているのか。
「ええい、石、ぶっつけてやれい。」
木から三四間離れて、善太は石を拾った。これを以て身構えると、樹の上を見上げて、それから周囲に気を配った。が、やはり何の答えもなかった。そこで善太は樹に二三歩駈け寄り、その勢で上に石を投げた。石が枝にあたって、落ちて来る音を聞きながら、彼は後をも見ずに逃げ出した。白い鳥は身じろぎもしないで、じっとその様子を眺めていた。
善太は勝ったような気もすれば負けたような気もしたのである。然し家に帰って来ると、三平に言って聞かせた。
「三平チャン、今日、とても大変だったんだぜ。あそこの田圃の松の樹のとこね。あそこに大きい白い鳥がいてね。クワア、クワア、クワアって鳴いているんだ。とっても大きな鳥なんだぜ、タカくらい。ウウン、ワシくらい。白い大ワシだ。おれ、石をぶっつけてやった。」
「フーン。」
三平は感心したのである。そして暫らくして言ったのである。
「それでどうした? 死んだ?」
「死なないや。」
「どうして殺さなかったの?」
「殺さないように石ぶっつけたんじゃないか。あんな白い鳥なんか神様の手下なんだぞ、殺したら、それこそ大変だあ、たたられてしまうから。」
「フーン。」
松の樹の下には、根本に小さい祠があった。瓦で出来た玩具のような形をして居た、片手でもさげられるくらいのものである。何が祭ってあるのか、永年そこに立っていて、雨にうたれ、風に吹かれ、そして草の中に埋まっていた。それでも、一年の内の何かの日には善太達のお母さんがそこにお詣りして、その前で何かブツブツ言いながら、火のついた線香をお供えしたのである。
けむりがモウモウと立って、松の樹の幹に沿うて上に昇った。中途で幹の裏へ廻りかけると、そこでスッスッと風に吹き散らされた。然しそれを見ていると、善太にも三平にも、何かもの凄いことが思出された。いつかあった村の火事のことが思出されたり、またいつか村を騒がした気狂い女の髪を振り乱した姿が思出されたりした。煙というものは気味悪いものである。それが一層この田圃の片隅を神秘的なものとした。
兄の善太は白い鳥を見たという処だし、お母さんは線香を立てておがむ処だし、三平も何か不思議なものを見るに違いない。そう思って、恐い処だけれども、ある日三平はそこにやって来た。
「ちょっとも恐くないや。」
家を出るから、彼はそう口に出して言ったのである。
「走ってやれい。」
その証拠には、彼はこう言って走りさえしたのである。そうして樹の下に駆けつけると、樹の周囲をグルリと廻って、上から下まで見上げ見下ろししたのである。それから、祠の前に立って、その瓦の小さいお宮をじっと眺めた。何にもない。鳥もいなければ、声も聞こえない。でも、もっとよく聞いて見なければ、また、もっとよく見て見なければ、何かがあるかも知れないぞ。それで、三平は立ったまま、じっと耳をすましていた。
と、そうだ。チリ、チリ、チリ、虫の声が聞えて来た。
コオロギの声である。声を尋ねて見廻すと、これは祠の中から聞えている。そこでしゃがんで、身体をすくめて覗き込むと、小暗い瓦のお宮の中の片隅に、コオロギはまぶたのない二つの目を開き、長いヒゲを前にさし出し、鳴くのをやめて、三平の方をじっと見ている。祠の中は瓦も土も白く乾いている。
さて、この時三平は思ったのである。
「これが神様かも知れない。」
そこで三平はそのコオロギの前に頭を下げた。自然に目がつぶられ、自然に手が合わされた。次に目をあけて見たが、コオロギはやはり前の通り、まぶたのない二つの目で、三平の方を眺め、長いヒゲを前につき出していた。三平は満足して立上り、ゆっくり家の方に歩いて来た。
「お母さん。」
家に戻ると、彼は言ったのである。
「僕、今日神様見ちゃった。」
「へえ、どんなだった。」
「松の樹んとこでね。」
「松の樹?」
「ウウン、あの田圃の松の樹のとこでよ。」
「ああ、あそこ。」
「ウン、あの松の樹の下にお宮があるでしょう。」
「ああ、ある、ある。」
「あのお宮を覗いたら、いるのさ。」
「何が。」
「神さまさ。」
「フーン。」
「チリチリ、チリチリって鳴いていた。」
「へえ、面白い神様ね。」
「ウン、とても面白いの。僕を見て、ヒゲを動かしたり、ピンピン飛んで見せたりするのさ。」
「へえ、全く面白い神さまね。」
「ウン、そりゃ面白いんだ。ヒゲが長いのさ。足だって、とても長いんだよ。だから跳ねたら、二メートルくらい一飛びさ。」
「へえ――。」
母さんは全く驚いてしまった。
夏のある日、雨が降って雷が鳴った。大きな雷で、空の上で何か大変なものが引き裂かれたりしたような音であった。その一つが松の樹の上に落ちた―と、そう思われた。何しろ金のキラキラする線が松の樹の上の空から、そこの岩のような雲の塊から、下へ向けて地図の国境のような線を引いたのである。
「松の樹だ。きっと松の樹だ。」
みんなが口々に言った。
善太と三平は雷のやむのを待っていた。やんだら直ぐ松の樹の処へ行って見よう。雷はどんなにして落ちているだろう。というより落ちてどんなになっているだろう。土に穴を開けて、中にもぐり込んでしまっているか。それとも! といって見たところでも解らない。雷の正体を知っているものはないのだから。みんなは雷獣ってものがいるというのだし、学校の先生は、雷とは電気の作用であるというのだし、だから、一時も早く雷の落ちたところを見たいものである。そう考えて、善太と三平は二階の窓から松の樹の方を眺め、トントン足踏みをして待っていたのである。
ト、雷がやんで、雨があがった。そして松の樹の上あたりにうっすらと虹が立った。それを見ると、そら行けと、二人は競争で門を駆けだした。道のたまり水を跳ね飛ばして駆けつけて見ると、何のことだろう。虹は遠くの空へ行って、見えるか見えないくらいに、はかなげに消えかかり、松の樹の何処にも雷の跡はない。
道に立ち、樹を見上げて、二人はちょっとぼんやりした。と、その時、三平が善太を肘で小さくこづいた。
「え?」
善太が三平の方に顔を傾けた。三平がそっと指でさし示した。祠の彼方の草の中である。
「お?」
善太は驚いたような表情をする、まだ解らないでいるのである。
「草の中で、魚がはねてるだろう。」
三平が小さい声で知らせてやる。
「ウン? ああ、あれか。何だい。おれァ雷かと思ったあ。」
が、雷でないにしても、これは不思議なことである。雨のあとで水かさが増した田圃のすぐ側であるとは言え、何にしても陸の草の中である。そこで大きな魚がピンピン上に、一尺も二尺も跳ね上っているのである。しかも、雷さまの落ちた後である。
「兄チャン、どうする?」
「とるさあ。」
「とってもいい?」
「いいさあ。」
「雷が怒るよ。」
「馬鹿ッ。」
善太は一人でいる時より、弟といる時の方が大人らしくて、大胆で常識家である。
「じゃ、何でとる?」
三平はまた善太といる時の方が子供らしく小胆である。
「手でとるさ。」
「じゃ、とって御覧。」
「わけないや。」
善太は露にぬれた草を分けて進み入った。
「やあ、大きいぞう。鯛だ。鯛だ。」
わけなく彼は鯉を両手で押さえ付けた。バタバタするのを前に抱て、道の方へ出て来たのである。一尺もある鯉である。何だか、目を白黒させているようである。口をパクパクさせていることは確だ。尻ッぽもパタリパタリするのである。
「ねえ。」
大得意で、善太は三平にそれを示した。それから、
「行こう。」
と善太が帰りを促して行きかかった時、また三平が言ったのである。
「兄チャン。」
振り返ると、おや、また三平は松の下の祠の近くに立ち、何かそこにいるような様子を示しているのである。
近よって見ると、何と、これは一匹の蟹である。しかも、大きな川蟹である。身体に毛の生えているような奴である。
それが祠の上にのっかり、爪を高くさし上げて、じりじりと動こうとしているのである。
「なあんだ。」
善太は言いました。
「どうする?」
また三平は聞くのである。
「ウン。」
と言ったものの、此度は善太も一寸恐ろしい。毛の生えた蟹である。しかも爪を立てている。その上、神さまの祠の上にかまえているのだ。
「どうする?」
三平はまた聞くのである。
「いいや、あんなの、捨てとこう。」
こうなれば、帰りが急かれる二人は道をまた水を跳ね散らかして駆け駆けした。
大分駆けてから、二人が歩き始めた時、三平が言った。
「僕にも持たせてよ。」
「ウン、落とすなよ。」
鯉を持つと、三平は俄におしゃべりになった。
「ねえ、さっきの蟹ね、あれ、きっと雷の家来だよ。」
「馬鹿ッ。」
「どうして?」
「どうしてって、そんなことあるかい。」
「ありますよッ。」
「じゃ、その訳を言って見ろ。その訳を。」
「だって、雷が落ちたろう。そこへ行って見たら、その落ちた処にいたんだろう。それがその訳さ。」
「そんな訳って、あるかい。」
「ありますよッ。」
「じゃア、お母さんに聞いて見よう。」
「ああ、聞いて見よう。もし、雷の家来だったらどうする。」
「どうもしないよ。だってさ。雷の家来なんてありっこないもん。」
「あるさ。あるとも、きっとある。」
「じゃ、もし、なかったら、拳骨だぞ。」
「ああ、あったら、僕の方も拳骨だよ。」
「あああ。」
「あああ。」
二人は大急行で、お母さんのいる家の方へ駆け出した。そして二人は門の前から、
「お母さん―。」
「お母さん―。」
と大声で呼びながら駆け込んで行った。
「拳骨だから―。」
「拳骨だから―。」
二人とも、相手に勝つことばかり考えて、こんなことを言い合いながら、台所の方でお母さんをさがした。
お問い合わせ
市民生活局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763