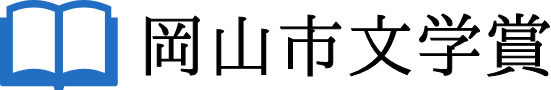第18回坪田譲治文学賞

第18回坪田譲治文学賞受賞作
『麦ふみクーツェ』(理論社刊)
いしいしんじ著
受賞者略歴

いしい しんじ
1966年2月15日大阪府大阪市生まれ。京都大学文学部卒。
株式会社リクルートに5年間勤務後文筆活動に入る。当初は雑誌ライターとして旅行記、絵日記などをさまざまな媒体に寄稿するも、2000年発表の『ぶらんこ乗り』以降、書き下ろし作品の執筆に重点を置き活動している。『麦ふみクーツェ』で第18回坪田譲治文学賞を受賞。現在、神奈川県三浦市三崎に在住。
小説作品に『ぶらんこ乗り』『トリツカレ男』エッセイ・対談に『グレートピープル。ストレンジ。』『アムステルダムの犬』『シーラカンス』『うなぎのダンス』『人生を救え!』(町田康氏との共著)『その辺の問題』(中島らも氏との共著)など。絵本作品に『なきむしヒロコちゃんはかもしれない病かもしれない』『うどんやさん』(絵・矢吹申彦氏)がある。
受賞者コメント
この作品を書くきっかけは、ある朝見た夢のなかの風景でした。
窓から外をみおろすと、黄色い服をきた見知らぬ人物が、黙々と地面を踏んでいます。あ、麦ふみだな、とおもいました。あたりには黄色い光が満ちあふれ、黄色い麦わらを踏む彼の足取りも軽やかで、まるで天上の光景のようです。いいなあ、麦ふみ、よし、次の本は麦ふみの話にしよう。ぼくはそう決めました。ほんとうの麦ふみを見たことさえなかったのに。
その翌週、編集のかたの紹介で、栃木の農家を訪ねました。麦ふみを実地に体験するためです。着いた日の翌朝は血の凍りつくような寒さで、長靴をはいたぼくは泣き顔を浮かべながらご主人に連れられ畑へでました。夢とはずいぶん様子がちがいます。泥まみれの霜、吹きつける北風。泥のなかを横ばいにぼくたちは進んでいきます。長靴の底に、麦苗まじりの冷えた泥がこびりつき、どんどん重たくなっていく。耐えがたい重さです。もうだめだ、そうおもった瞬間、泥はみずからの重みで「ずぼっ」と地に落ち、靴は軽くなりました。また踏む、だんだん重くなる、もうだめだ、ずぼっ。何百回これを繰り返したでしょう。ほんとうの麦ふみは、軽やかな天上の光どころか、泥まみれの地面へ、真下とおちていく、暗い重みをぼくのからだに残しました。
この話は、天上の光と暗い地の底を、いったりきたりするような物語になる。その底流には、泥のついた長靴で麦をふんでいくあのリズムが、たえず鳴っているはずだ。
帰りの電車でぼくはそうおもいあたりました。音楽を題材にすることも、いつのまにか当たり前のように決まっていました。吹奏楽団を舞台にしたのは、管楽器に天上の光を、打楽器に地を打つリズムを託そうというおもいが、どこか胸のなかにあったのかもしれません。ともあれ書きはじめると、物語は自分でもあきれるような展開をみせました。が、あの麦ふみのリズムがからだに残っている限り、まちがったほうにはいっていない、という確信があり、毎日ぼくは地道に話の枝葉を継いでいきました。机の下でときどきとんたたんと足踏みをしながら。
この話にでてくるボクシング、合奏、新聞記事のスクラップなど、どれも実際、熱中した経験のあるものばかりです。そして、自分のこのからだのもっとも深みにあるのは、夢中で本を読みふけった、こどものころの感触なのだとおもいます。あの当時は、からだごとのめりこんで本を読んでいました。ぼくのつくる話が、おとなもこどもも楽しめるものになっているとするなら、それはぼくのからだが、内面の奥のほうでは、あのころと比べさほど変化していないからかもしれません。
この賞をいただけたことは、そんなぼくにとって、光栄の至りです。自分のやってきたことを、このままやっていていい、といっていただいた気がします。当分、机の上下で麦ふみ作業をつづけるつもりでいます。
作品の概要
ぼくたち三人がその港町に移り住んだのは、ぼくが赤ん坊のころだった。数学教師の父と、吹奏楽団のティンパニストの祖父とのささやかな三人の暮らし……。しかし、おだやかな紳士と町の人から慕われる祖父は、こと音楽になると常軌を逸したところがあった。
「猫の声」という楽器がある。こだわりのある打楽器奏者は自分の喉で鳴らすこともある。それがぼくの担当となった。祖父は「ねこや、調子はどうだい」と呼び掛け、幼いぼくが「にゃあ」とこたえる。いつのまにか周りからもねこと呼ばれるようになり、つまり、祖父はぼくを楽器として育てようとしていたのだ。
父も変わり者だった。頑固で無口。家の階段をボールペンでたたきながら、数学の有名な証明問題に取り組んでいた。ふたりとも、死んだ母のことを話すのを嫌がった。やがて街をおそう災難、親しい人の死という出来事の中でも、祖父は何かに取り付かれたようにティンパニをたたきつづけ、父は考えをまとめるように階段の十三段目をこきざみにボールペンでたたいた。
小学校に入った頃だった。ぼくが、家の屋根裏で見かけるようになったのが小人のような大きさの「クーツェ」。はばひろの麦わら帽子、ぶかぶかのズボンとシャツは真っ黄色、靴だけは黒い。うつむいたまま一歩ずつ横ばいに進んでいる。麦ふみをしているのだという。「とん、たたん、とん」という、麦ふみの音はその後ずっとぼくと一緒にあった。ぼくたちの吹奏楽団がコンクールで初めて優勝した前の晩、街にねずみの雨が降り、やみねずみの出現した日、膨大なスクラップ記事の収集家だった用務員さんの事故の直前、音楽を勉強するために故郷を旅立ったあの日も、クーツェの足音がぼくの耳もとでした。
大きな街の音楽学校に入ってからも、ぼくは祖父や父に負けないへんてこな人々と出会うことになる。盲目のボクサーはとびきり耳のいい人だった。雑踏の街なかでも、音を聞き今いる場所の番地まで言い当てることができた。湾曲した背中を持つ天才チェリストは偏屈だけど、売春宿ですばらしい演奏をした。そして、かつて用務員さんのスクラップブックの中で出会った三千年の記憶をすべて持つ「生まれかわり男」とも会うことになる。そして彼の口から、祖父の秘密を知り、母に関する隠された悲劇の匂いをかぐことになる。それは、ぼくが国立音楽ホールで指揮者としてデビューするわずか十日前のことだった。
麦ふみの音が通奏低音になり、へんてこな人々が様々なユニークな音を主人公のまわりで奏で、まるでオーケストラの演奏を聴くように、物語が進んでゆく。そして最後に明かされるクーツェの正体とは……。
選考委員 高井有一氏(小説家)のコメント
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763