「文学の中の岡山」では、公益社団法人全国学校図書館協議会:Japan School Library Association(略称:全国SLA)学校図書館スーパーバイザーであり、岡山市文学賞運営委員会 文学によるまちづくり部会委員の高見 京子さんに、岡山ゆかりの作家、作品などについてご紹介いただきます。
『父のビスコ』平松 洋子(小学館)
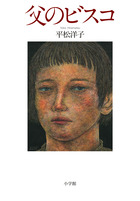
食文化に関するエッセイにおいて、平松洋子氏の右に出る人はいない。歴史や文化を踏まえながら、特筆すべきは、対象である人や食物に対しての観察の鋭さと深さ、そして対象への敬意であるだろう。人間の営みの中に「食」はある。
この本は、食にまつわる家族との思い出を綴ったものである。家族を思い出すとき、その場にあった食事やお菓子を同時に思い出す。また、食べ物と一緒に家族のこと、ともに過ごした地が思い出されるのだ。父は「ビスコ」、母は「金平糖」である。
母が忘れられないと言って話すのが、昭和二十年六月二十九日の岡山空襲である。母の父(平松洋子の祖父)はフィリピンの戦地で、残されたのは、母の母(平松洋子の祖母)と、母を筆頭に四人きょうだいの5人である。「岡山市内からふた駅離れた土地だったから、焼夷弾は投下されるたび、閃光がぱあっと広がる遠景を見た」祖母から母に言い渡された言葉は「ちかちゃんは、いくちゃんと手をつないで逃げなさい。ぜったいに手を離したらいけんよ。~必ずどこかで会えるから」その二年後、父が返ってくる。お土産が金平糖。帰国船での支給でされたものをそのまま父は持ち帰ってくれたのだ。「金平糖と虱が、お父さんのおみやげだった」「金平糖が海を渡り、四人きょうだいが赤い金平糖の取り合いっこする日が来ていなければ、今の自分は存在しない」
本のタイトルにもなった「父のビスコ」は、父親の臨終にまつわる話である。死の直前、看護師さんから聞かされたのが「ビスコが食べたいそうです」。「お父さんはビスコが食べたい、病院から帰りたい。食べて生きたい。」「最期に父が自分の意志で食べたのは、ビスコなのだ」
平松洋子の父は倉敷市出身であり(洋子も倉敷)、母親は岡山市庭瀬の人である。よって、自然と、これらの地が背景として語られる。
倉敷の「民藝ととんかつ」、木村屋のパン。大手饅頭、きび団子、むらすずめ……、郷愁の中に食べ物がある。
平松洋子さんの紹介
1958年岡山県倉敷市生まれ。清心女子中学・高校、東京女子大学卒業。食文化・文芸などを中心に幅広い執筆活動を行っている。岡山県に文学賞である内田百閒文学賞の審査員も務めている。(小川洋子も審査員で「ダブル洋子」として親しまれている)
『父のビスコ』は読売文学賞受賞。『買えない味』でドゥマゴ文学賞受賞、『野蛮な読書』で講談社エッセイ賞受賞を受賞している。他に『ルポ 筋肉と脂肪 アスリートに訊け』『ひとりひとりの味』など。
「文学の中の岡山」執筆にあたり/全国SLA学校図書館スーパーバイザー 高見 京子
2023年10月に、岡山市は「ユネスコ創造都市ネットワーク文学分野」に加盟した。
岡山(市だけでなく県全体で)は、「文学創造都市おかやま」の名に恥じない、数々の実績があるが、私は特に岡山出身(ゆかり)の作家たちが多いことを挙げておきたい。その作家たちを中心に、それぞれの作品の中に岡山の描写が多いこともうれしいことである。
これから、このコーナーでは、読み応えのあるそれらの作品と、岡山がどのように文中で書かれているかを紹介していきたい。作品が一都市だけに向けて書かれていることはもちろんなく、普遍的なものであるのだが、その作品を味わうと同時に、身近な場所が文中にあることで、より岡山に親しみを感じたり、その場所を歩いてみたりしようと思っていただければ幸いである。
「文学」も広くとらえ、ノンフィクションも、映画など他のメディアなども含み、比較的新しい作品を取りあげていきたいと思っている。愛読してくださるとうれしい。
お問い合わせ
岡山市役所スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1054
ファクス: 086-803-1763
