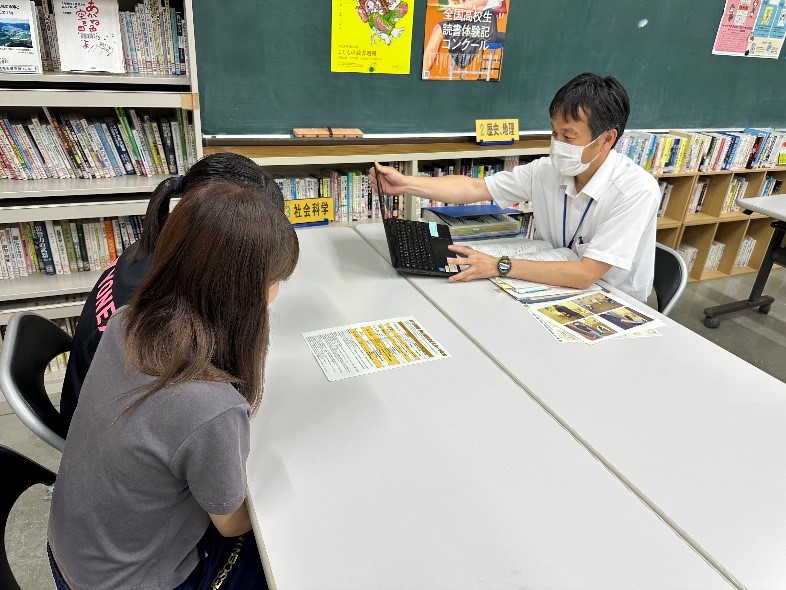- ホーム
- みんなの活動紹介
- 取材記事
- YOUTH CHALLENGE
- YOUTH CHALLENGE その22|車いす利用者が暮らしやすいまちを目指して 【烏城高校 toilet girls(トイレットガールズ)】
[2025年8月14日]
ID:74510
社会のため、未来のために活躍する「若い力」に注目し、そのチャレンジを紹介するコーナー「YOUTH CHALLENGE」。
今回は、烏城高校 toilet girls(トイレットガールズ)についてご紹介します。
なお、内容は取材当時のものです。
toilet girls(トイレットガールズ)って?
烏城高校の「探究活動」という課外活動の一環として2022年に生徒有志が集まり、取り組みがスタートしました。障害のある人に何か役立てる活動が出来ないか調べる中で、実際に障害のある人から「出かけるときに一番困るのはトイレの問題、自分が使えるトイレが近くにあるのか・・・」という話を聞き、多目的トイレについて調べ始めたそうです。トイレの位置や手すりなどの設備状況を調べ、その調査結果をインターネット上の「みんなで作ろう!多目的トイレマップ」というアプリに投稿する等の活動を行っており、2024年11月には岡山県内の高校生ボランティアの活動を顕彰する「第12回岡山高校生ボランティア・アワードNEXT(ネクスト)」で、最高賞の「大賞」に輝きました。
活動について、顧問の三宅浩二教諭(以下、三宅教諭)に聞きました。
どんな活動に取り組んでいる?
(三宅教諭)「活動を始めた2022年は実際にまちを歩いて調べてみると、いろいろと問題がありすぎて何から手をつけてよいかわかりませんでした。その中で、障害のある人から聞いた『多目的トイレ』について調べるようになりました。2022年、2023年と岡山市内の多目的トイレについて調べて、インターネット上の『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』に投稿しました。調べても実際に多目的トイレマップを利用してもらわないと意味がないので、2024年は実際に障害者のスポーツ教室やまち歩きイベントに参加してアプリを紹介する活動にも取り組みました」
「多目的トイレ」の調査について
(三宅教諭)「多目的トイレにもさまざまなタイプがあります。具体的には、手すりの間隔が広すぎて体を持ち上げられない、手すり位置の左右バランスがおかしいなど、障害によって使い勝手が異なることがあります。車いす利用者が少しでも暮らしやすいまちになるように『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』に投稿、PR活動を続けています」
2024年の活動に参加した道久優奈さん、多比良花さんに話を聞きました。
道久さん、多比良さん
道久さん
「先輩の取り組みを引継ごうと思い活動を始めました。元々、福祉に興味があってこれを機会に少しでも福祉について調べることができたら自分の経験にもなるし、人のためにもなると思い参加しました。『toilet girls』の取組を発表する機会があったのですが、スライドや原稿の作成と修正を繰り返すうちにどうすべきか分からなくなり、自分の活動をわかりやすく伝えることの難しさを感じました」
多比良さん
「私は道久さんに声をかけてもらって途中からメンバーに加わりました。初めて参加したのが車いすの人とボッチャを体験するイベントでした。イベントに参加している車いす利用者に『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』について紹介したら『こんなサイトがあるんだ』と興味を示してもらえました。また、車いす利用者と関わりが出来たからこそ気付いたことが沢山ありました。『ボランティア・アワード』では、プレゼン発表後の質疑応答が難しくて、道久さんに助けてもらいましたが、一人で考えてその場で判断して説明することが大変でした」
「第12回岡山高校生ボランティア・アワードNEXT(ネクスト)」で大賞受賞
「活動が始まった2022年頃は活動が広がっていなかったのですが、2024年の発表会で大賞を受賞したとき『2年前に比べて成長している』というコメントをいただきました。
他の高校は廃棄食材を使って調理した食品販売など、食にまつわる内容が多い中で、私たちのトイレマップづくりの取り組みを評価して頂けたことは嬉しかったです」
活動で一番大切にしてきたことは
道久さん
「まち歩きイベントなどで自分たちの活動についてチラシを配りながら説明していますが、車いすは自分一人で動かす人以外に、他の人に介助してもらう人もいます。そのため、利用者本人にアプリを周知するだけでなく、車いす介助者にも認知してもらえるように心がけて活動してきました。車いす利用者だけでなく、周りの人にも『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』について知ってもらうことが大切だと思います」
今後の活動について
(三宅教諭)「『toilet girls』の取り組みは自分たちで調べた多目的トイレの写真などを『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』に投稿する活動です。自分たちだけではなく、私たちの活動を知ってくれたほかの人たちも投稿することができます。活動を始めた2022年は岡山県の登録は400件ほどでしたが、今は600件を超えました。『アプリに投稿する』という方法なので、高校を卒業してからも活動をそれぞれの進学先、就職先などの周辺にある多目的トイレを調べて投稿することができます。そのようにしてどんどん関係者が増えていけばアプリも充実します。車いす利用者が暮らしやすい街になってほしいと思います」
最後に、2人に今後の「toilet girls」の活動について聞きました。
道久さん
「私たちが中心となった活動は終わりますが、車いす利用者の気持ちや障害のある人との接し方など、まだ分からないことも多いです。障害のある人と接することは学ぶことが多いので、後輩たちにも活動を通して様々な立場の人に『向き合う力』を付けてほしいと思います。
『みんなで作ろう!多目的トイレマップ』も烏城高校で10人、15人と活動する人が増えればどんどん発展していくと思うし、イベントに参加する人が増えればアプリについてもっと周知できるようになると思うので、アプリの内容もアプリの存在を知る人もどちらも増えていけば良いと思います」
多比良さん
「車いす利用者や利用者を支えている人にも『みんなで作ろう!多目的トレイマップ』の存在自体が知られていないので、後輩たちに引き継いでもらって車いすのまち巡りなどに積極的に参加してもらって『このアプリ知ってるよ』という人を増やしてもらいたいし、岡山県はアプリに登録されている多目的トイレの数がまだまだ少ないので、卒業後に私たちも増やしていくし、後輩たちにも増やしてもらって誰もが活用しているアプリになってほしいと思います」
関連リンク

車いす利用者や介助者の困っていることの助けになるために、生徒たち自身が行ったトイレの調査結果をアプリに反映させて、さらに後輩にも引き継いで充実させていくって素敵だねっ!
のっぷもトイレの情報を増やすために協力しよっと。
「YOUTH CHALLENGE」では、「取材にきてほしい!!」という若者の取組を募集中です。
希望される方はkyoudouhiroba@city.okayama.lg.jpへ、団体名、活動の内容を添えてご連絡ください!