岡山ゆかりの作家・翻訳家をご紹介します
坪田 譲治(つぼた じょうじ)
明治23年、岡山市北区島田本町で生まれ少年時代を過ごす。坪田譲治の作品は、田園が広がり豊かな自然に囲まれた当時の岡山の風景を描いたものが多い。善太、三平をはじめとする登場する子供たちも、無邪気でやんちゃながら、たくましく生きていく姿勢が描かれ、社会の厳しい現実も描かれている。
代表作『魔法』は、魔法に興味津々な三平が、兄善太に動物に変身する魔法を教えてもらおうとするが…。日常の中の兄弟のやりとりが微笑ましい作品。
あさの あつこ
岡山県英田郡美作町(現美作市)湯郷出身。1991年『ほたる館物語』でデビュー。1997年『バッテリー』で第35回野間児童文芸賞、2005年バッテリーシリーズで小学館児童出版文学賞、2011年『たまゆら』で第18回島清恋愛文学賞、第63回NHK放送文化賞、2024年第13回日本歴史時代作家協会賞を受賞。他に『No.6』シリーズ、弥勒シリーズなど。
内田 百閒(うちだ ひゃっけん)
岡山市古京町に、造り酒屋の一人息子として誕生。県立岡山中学校(現在岡山朝日高校)に入学、第六高等学校(現在岡山大学)卒業の後、東京帝国大学(現東京大学)へ進学する。
不可解な恐怖を夢の光景のように描いた小説や、鉄ヲタのはしりとも言えるようなエッセイ『阿房列車』、ふとしたきっかけで野良猫と暮らすことになり、その別れまで描いた『ノラや』など多くの随筆を執筆し名文家としても知られる。ペンネームの「百閒」は、百間川から。当初は「百間」と表記していたが、後に「百閒」に改めた。
大森 静佳(おおもり しずか)
歌人。1989年岡山市生まれ。京都市在住。岡山朝日高校在学中に現代短歌と出会い、2010年第56回角川短歌賞、2023年『ヘクタール』で第4回塚本邦雄賞、2023年福武教育文化賞、2024年第25回岡山芸術文化賞グランプリを受賞。歌集『てのひらを燃やす』(角川書店)、『カミーユ』(書肆侃侃房)、『ヘクタール』(文藝春秋)。短歌ワークショップ「31文字の私に出会う」など岡山で短歌の魅力を広める活動を行う。
岡崎 隼人(おかざき はやと)
1985年岡山市生まれ。現在も同市に在住。2006年、『少女は踊る暗い腹の中踊る』で第34回講談社メフィスト賞を受賞しデビュー。ほかの著作に『だから殺し屋は小説を書けない。』『書店怪談』がある。また共著に『だから捨ててと言ったのに』(講談社編)。掌編小説、エッセイなども手がける。そのほか、小説講座や創作ワークショップなどでも講師を務めている。
小川 洋子(おがわ ようこ)
小説家。1962年岡山市生まれ。子どもの頃から本を読むのが好きで、自分もお話を作る人になりたいと、ずっと願っていた。1988年に当時の福武書店が刊行していた文芸誌「海燕」の新人賞でデビュー。1990年に『妊娠カレンダー』で芥川賞を受賞。以来、ずっと小説を書き続けている。主な著書は『博士の愛した数式』『ミーナの行進』『猫を抱いて象と泳ぐ』『アンネ・フランクの記憶』など。
金原 瑞人(かねはら みずひと)
1954年岡山市生まれ。翻訳家。法政大学名誉教授。訳書は児童書、ヤングアダルト小説、一般書など約650点。訳書に『不思議を売る男』『青空のむこう』『国のない男』『月と六ペンス』『彼女の思い出/逆さまの森』『何かが道をやってくる』『小さな手ホラー短編集4』など。エッセイ集に『翻訳はめぐる』など。日本の古典の翻案に『雨月物語』など。
木山 捷平(きやま しょうへい)
岡山県小田郡新山村(現在の笠岡市)出身の詩人、小説家。当初は詩人として出発し、のち小説に転じた。
満州で敗戦を迎え、帰国後、『大陸の細道』『長春五馬路』などを発表。その後、『耳学問』を発表し、私小説的な短編小説やエッセイを執筆、ユニークな庶民派作家として活動した。
重松 清(しげまつ きよし)
小説家。早稲田大学教授(任期付き)。1963年岡山県久米郡久米町(現・津山市)生まれ。早稲田大学教育学部卒。出版社勤務をへて著述業に。1999年『ナイフ』で第14回坪田譲治文学賞、2001年『ビタミンF』で第124回直木賞、2014年『ゼツメツ少年』で第68回毎日出版文化賞を受賞。主な著書に『十字架』『流星ワゴン』『とんび』『きみの友だち』『その日のまえに』など。
柴田 錬三郎(しばた れんざぶろう)
岡山県邑久郡鶴山村(現・備前市)生まれ。時代小説だけでなく、現代小説にも多くの作品を残す。『イエスの裔』で直木賞を受賞。週刊新潮で連載した『眠狂四郎』シリーズは剣客ブームを巻き起こした。忍者好きには堪らない『赤い影法師』は伝奇小説の最高傑作。
時実 新子(ときざね しんこ)
岡山県上道郡九蟠村(現岡山市東区西大寺)出身。戦後の混乱期、17歳で兵庫県の商家に嫁入りするが、傷痍軍人だった夫の暴力に苦しむ生活の中、新聞の投稿欄で川柳と出会う。昭和62年に出版した句集『有夫恋(ゆうふれん)』が、女性の情念を表現した作品として話題を呼び、川柳の世界に新しい風を吹き込んだ。
時代を越えて女性の本音を表現する作家として支持され、平成7年の阪神淡路大震災では自らの被災体験を詠む一方、句集『悲苦を越えて』を出版するなど多くの被災者を勇気づけた。
谷崎 潤一郎(たにざき じゅんいちろう)
谷崎潤一郎は、1945年、岡山県津山市、岡山県真庭郡勝山町に疎開し、代表作『細雪』を執筆しながら、終戦まで過ごす。
初期は耽美主義の一派とされ、スキャンダラスな文脈で語られることも多いが、端麗な文章、作品ごとに異なる巧みな語り口が特徴。主な作品は『春琴抄』『細雪』『陰翳礼讃』など。
天川 栄人(てんかわ えいと)
小説家。1991年岡山市生まれ。京都大学在学中『ノベルダムと本の虫』で第13回角川ビーンズ小説大賞審査員特別賞を受賞し、デビュー。現在は児童書やYA小説をメインに活動中。2022年『おにのまつり』で第9回児童ペン賞少年小説賞、2024年『セントエルモの光』『アンドロメダの涙』で第48回日本児童文芸家協会賞受賞。2025年『わたしは食べるのが下手』が第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選定された。
永瀬 清子(ながせ きよこ)
岡山県赤磐郡豊田村熊山(現赤磐市)出身。家族の転勤で金沢、名古屋、東京で暮らしていたが、昭和20年、戦火を逃れ赤磐市の生家へ戻る。田畑を耕し、子育てをし、世間の人であり続けながら詩作を続けた。宮沢賢治の手帳の中から「雨ニモマケズ」を見つけ出したことも有名だが、ハンセン病患者が住む長島へ通い、長く患者たちに詩作の指導も続けた。
詩集『あけがたにくる人よ』は、老いを見つめ、生を瑞々しく描き出した代表作。
夏目 漱石(なつめ そうせき)
1892年の夏、当時既に亡くなっていた次兄栄之助の元妻小勝の実家片岡家を訪問するため、岡山に滞在し、夏休みを楽しんだ。その近辺が「漱石ロード(岡山市東区)」と名付けられ、現在も親しまれている。夏目漱石は、帝国大学を卒業後、教師となり、1900年にイギリスに留学。帰国後の1905年に処女小説『吾輩は猫である』を発表。1907年に新聞社に入社し、以降作家として活躍した。代表作に『坊ちゃん』『三四郎』『こゝろ』『明暗』などがある。
乗代 雄介(のりしろ ゆうすけ)
作家。1986年北海道生まれ。2015年『十七八より』で第58回群像新人賞を受賞し、デビュー。2018年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞、2021年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞、第37回坪田譲治文学賞、2023年『それは誠』で第40回織田作之助賞、第74回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。2023年から「おかやまライター・イン・レジデンス」に伴うワークショップの講師を務める。
原田 マハ(はらだ まは)
東京都小平市生まれ。小学6年生から高校卒業まで岡山県岡山市で暮らした。2003年から執筆活動を開始し、キュレーターとして経験を生かした著作も多い。代表作は『カフーを待ちわびて』『楽園のカンヴァス』『キネマの神様』など。
平松 洋子(ひらまつ ようこ)
岡山県倉敷市出身。アジアを中心として世界各地を取材し、食文化と暮らし、文芸と作家をテーマに執筆活動を行う。代表作は『買えない味』『野蛮な読書』など。自伝的小説『父のビスコ』には故郷の倉敷とともに家族の思い出が語られている。最新刊は『ルポ 筋肉と脂肪 アスリートに訊け』。
岡山ゆかりの作家たち イラスト
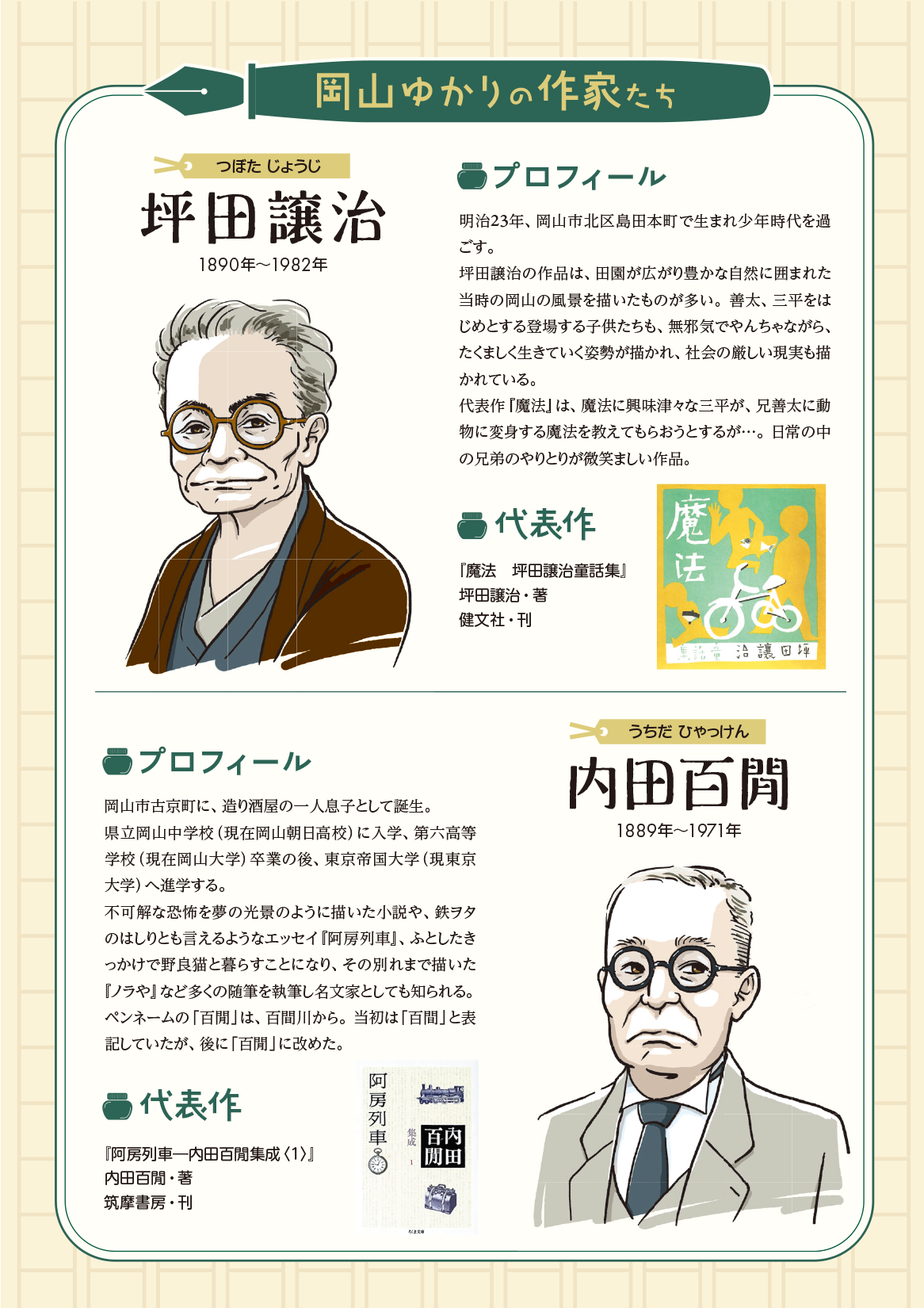
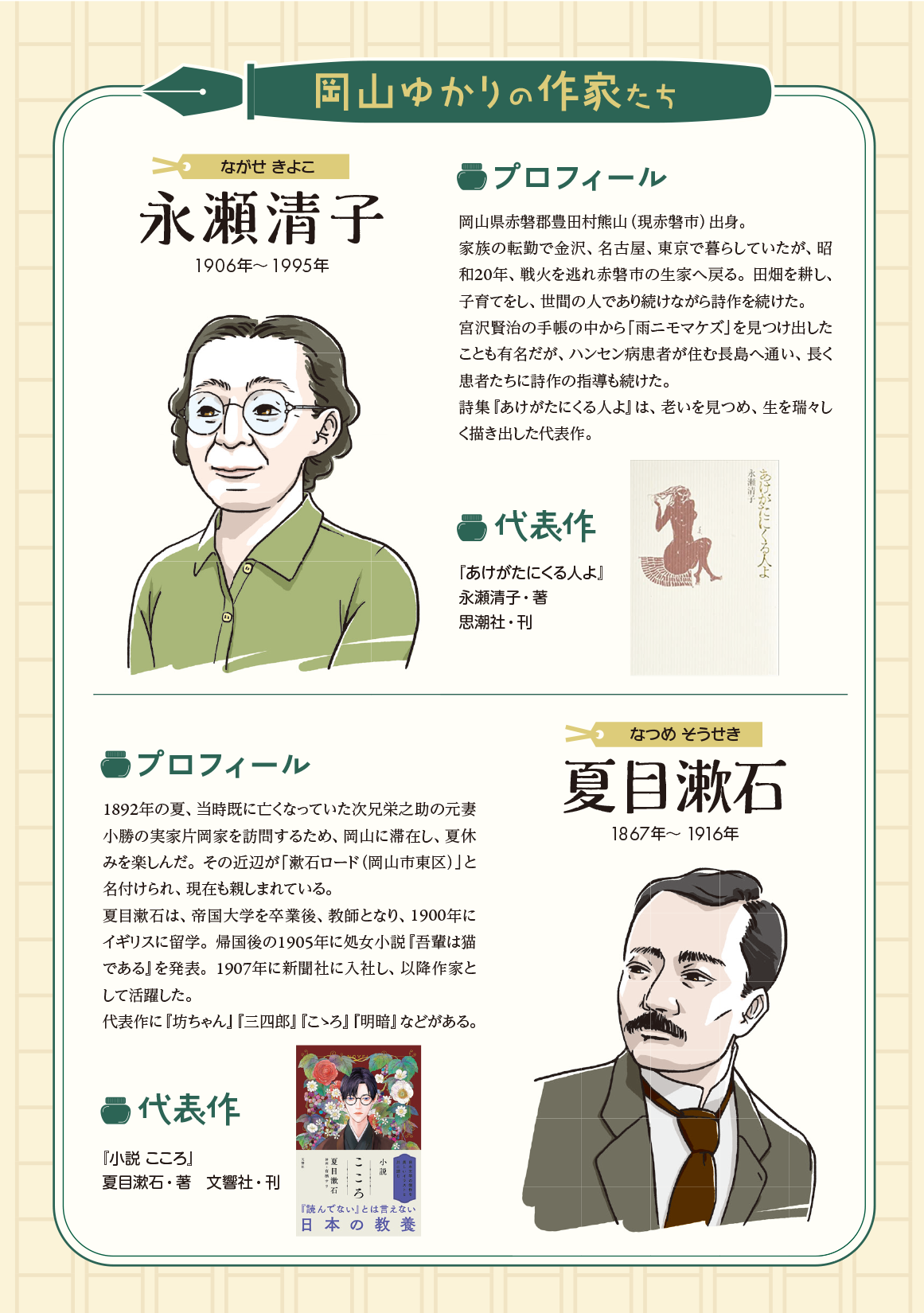
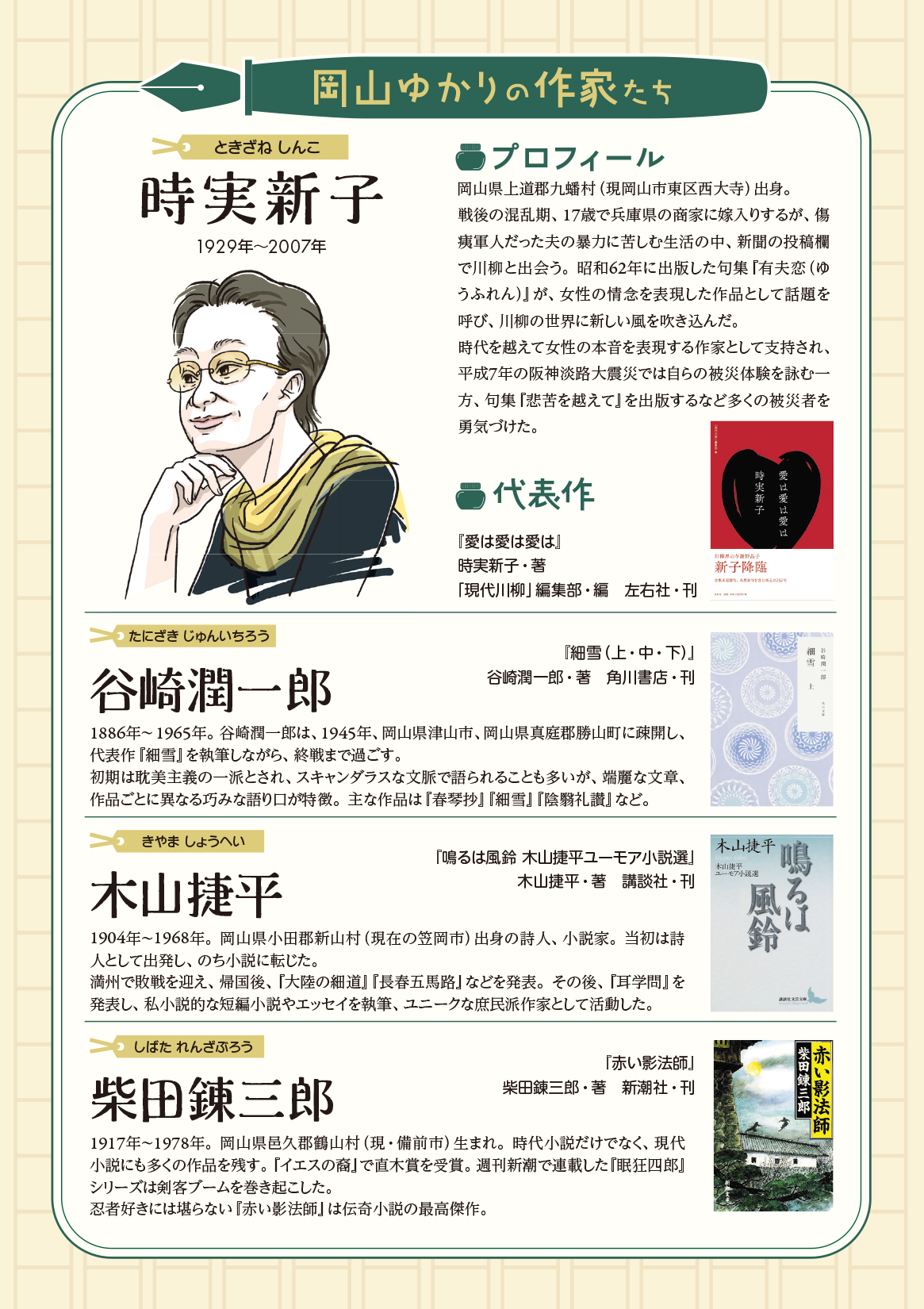
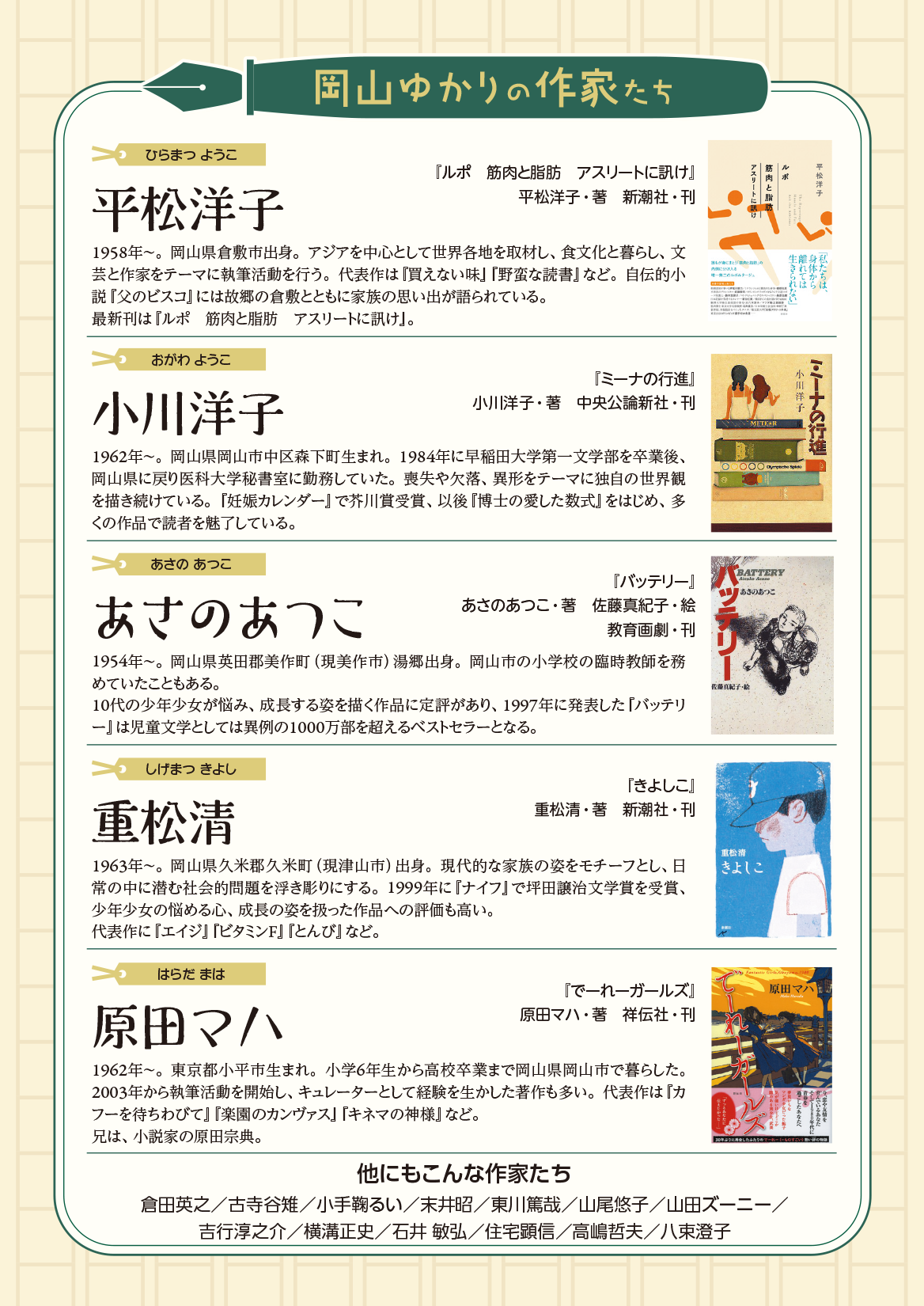
似顔絵:スタジオ貝 デザイン:中原企画立案事務所
テキスト:451ブックス 根木慶太郎
お問い合わせ
岡山市役所スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1054
ファクス: 086-803-1763
