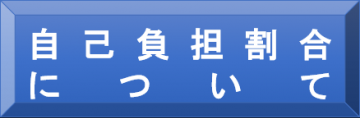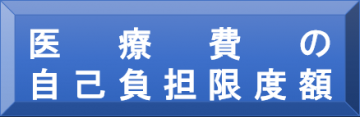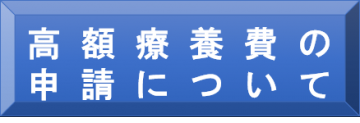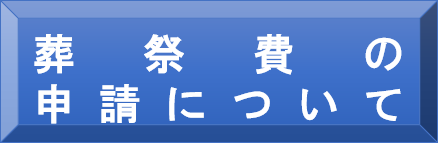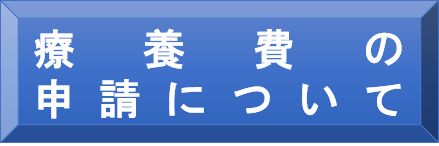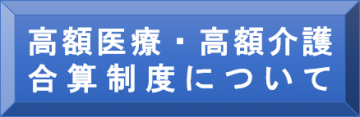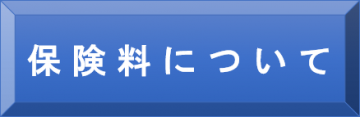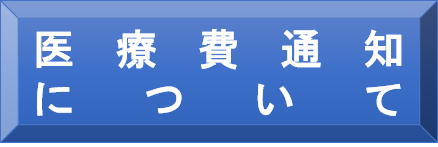メニュー
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、岡山県すべての市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合が運営全般を行います。
各種申請書は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードできます。(岡山市への郵送での申請が可能です。送付先はページ最下部のお問い合わせ先となります。)
後期高齢者医療制度の事務のうち、市は次のような窓口業務を行います。
- 保険料の徴収
- 各種申請・届け出の受付
- 資格確認書の引き渡しなど
- 後期高齢者医療に関するよくある質問はこちら
対象者(被保険者)
75歳以上の方全員と、一定の障害がある方で加入を希望し認定された65歳から74歳までの方が対象となります。
- 75歳以上の方
適用開始時期:75歳の誕生日当日から。なお転入の場合は転入日から - 65歳から74歳で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方(注釈1)
適用開始時期:広域連合の認定日から
(注釈1)一定の障害とは
- 国民年金法等における障害年金1・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部(4級の一部は音声、言語に関する障害、下肢に関する障害の一部)
- 療育手帳A(重度)
上記のような障害があり、認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための身体障害者手帳等と資格確認書等および来庁者の本人確認書類を持って、各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所へ申請してください。
自己負担割合
お医者さんにかかる時の自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。
所得区分は、前年(1月から7月までは前々年)の所得により、毎年判定します
※令和4年10月1日から、一定以上の収入がある75歳以上の高齢者の医療について、窓口負担割合が1割から2割に引き上げとなりました。
| 所得区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(注釈1) ただし、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が次の金額未満の場合、申請により1割または2割負担となります。 ・同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合 1.被保険者本人の収入額が383万円 または、 2.世帯の70歳から74歳の方(後期高齢者医療の被保険者を除く。)を含めた収入額が520万円 ・同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合は520万円 |
| 一般2 | 2割 | 現役並み所得者以外で、 1.世帯の被保険者が1人の場合 住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者 2.世帯の被保険者が2人以上の場合 世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者 |
| 一般1 | 1割 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人 |
| 低所得者2 | 1割 | 世帯員全員が住民税非課税の方 |
| 低所得者1 | 1割 | 世帯員全員が住民税非課税で、かつ、世帯員全員の所得(年金の所得控除額は806,700円として計算)が0円となる方 |
(注釈1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
医療費の自己負担限度額
| 所得区分 | 自己負担割合 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | 入院時食事負担(療養病床を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者(3) (課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) | 1食 510円 |
| 現役並み所得者 (2) (課税所得380万円以上) | 3割 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) | 1食 510円 |
| 現役並み所得者 (1) (課税所得145万円以上) | 3割 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) | 1食 510円 |
| 一般2 | 2割 | 18,000円 年間限度額144,000円 (注釈2) | 57,600円 【44,400円】(注釈1) | 1食 510円 |
| 一般1 | 1割 | 18,000円 年間限度額144,000円 (注釈2) | 57,600円 【44,400円】(注釈1) | 1食 510円 |
| 低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | (90日までの入院)1食 240円 (90日を超える入院)1食 190円 |
| 低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 1食 110円 |
(注釈1)過去12ヶ月以内に世帯単位で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
(注釈2)毎年8月~翌年7月が対象となります。
高額な診療を受ける場合の窓口でのお支払い
マイナ保険証を提示することにより、ひと月あたりの同一保険医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。マイナ保険証をお持ちでない場合、以下のものをご提示ください。
- 所得区分が「現役並み所得者3」「一般1」「一般2」の方
「資格確認書」の提示 - 所得区分が「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「低所得者2」「低所得者1」の方
限度区分が併記された「資格確認書」の提示
限度区分が併記された「資格確認書」の交付には事前の申請が必要です。
資格確認書・来庁者の本人確認書類をお持ちになって、各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所へ申請してください。
・マイナ保険証についてはこちら別ウィンドウで開く
低所得者1・2の方へ(入院時食事負担の減額)
入院時の食事負担を安くするためには限度区分が併記された「資格確認書」が必要となります。(マイナ保険証をお持ちの方は不要)
資格確認書等・来庁者の本人確認書類をお持ちになって、各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所へ申請してください。
また、区分2(低所得者2)の認定を受けている方で、過去1年間の区分2(低所得者2)の認定期間内に90日を超える入院日数がある方は、届出により入院時の食事代がさらに減額される場合がありますので、入院日数が確認できる領収書と限度区分が併記された「資格確認書」、および来庁者の本人確認書類を持参し、改めて届出してください。
高額療養費の申請について
1か月の医療費が限度額を超えた場合には、自己負担限度額を超えた部分が後から払い戻されます。高額療養費の支給対象となり、振込口座のご登録がない方には、岡山県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が送付されます。申請方法は下記のとおりです。
一度申請していただくと、次回からは申請された口座に自動的に振り込まれます。申請状況を確認したい場合は、被保険者証/資格確認書など、被保険者番号がわかるものをご準備のうえ、医療助成課(086-803-1217)までお問い合わせください。振込口座の変更をご希望の場合も、下記の方法により申請してください。
申請場所
各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所、医療助成課
申請に必要なもの
- 被保険者証(資格確認書)等
- 本人確認書類(被保険者以外の方がお越しの場合)
- 通帳等振込口座がわかるもの
※被保険者以外の口座に振込をする場合は、被保険者・口座名義人それぞれに記入・押印が必要です。
郵送で申請する場合
同封するもの
- 高額療養費支給申請書または給付費振込口座変更依頼書
- 通帳等振込口座がわかるもののコピー
※申請書の様式は、岡山県後期高齢者医療広域連合から送付されたものをお使いいただくか、こちらの岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。申請書の郵送をご希望の場合は、医療助成課(086-803-1217)までご連絡ください。
※通帳等のコピーが困難な場合は、口座番号等に不備がないか必ず確認し送付してください。
※成年後見人/保佐人/補助人が申請する場合は、委任等代理権の確認ができるもののコピーを同封してください。
郵送先
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市役所医療助成課
葬祭費の申請について
後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意ください。
(支給金額)5万円
申請場所
各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所、医療助成課
申請に必要なもの
- 葬祭執行者(喪主)の本人確認書類
- 葬祭執行者(喪主)の通帳等振込口座がわかるもの ※葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込をする場合は、葬祭執行者(喪主)・口座名義人それぞれに記入・押印が必要です。
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)等(未返却の場合)
郵送で申請する場合
同封するもの
- 葬祭費支給申請書
- 通帳等振込口座がわかるもののコピー
※申請書の様式はこちらの岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。申請書の郵送をご希望の場合は、医療助成課(086-803-1217)までご連絡ください。
※通帳等のコピーが困難な場合は、口座番号等に不備がないか必ず確認し送付してください。
※葬祭執行者の成年後見人/保佐人/補助人が申請する場合は、委任等代理権の確認ができるもののコピーを同封してください。
郵送先
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市役所医療助成課
療養費の申請について
次のような場合は、申請により給付が認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代
- 旅行先などでの急な病気やけがなどで、やむを得ず被保険者証(資格確認書)を持たずに診療を受け、全額自己負担した場合
- 海外で医療を受けた場合 など
申請場所
各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所、医療助成課
申請に必要なもの
- 被保険者証(資格確認書)等
- 本人確認書類(被保険者以外の方がお越しの場合)
- 通帳等振込口座がわかるもの
- 領収書など
郵送で申請する場合
同封するもの
- 療養費申請書
- 通帳等振込口座がわかるもののコピー
- 領収書など
※申請書の様式はこちらの岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。申請書の郵送をご希望の場合は、医療助成課(086-803-1217)までご連絡ください。
※通帳等のコピーが困難な場合は、口座番号等に不備がないか必ず確認し送付してください。
※成年後見人/保佐人/補助人が申請する場合は、委任等代理権の確認ができるもののコピーを同封してください。
郵送先
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市役所医療助成課
高額医療・高額介護合算制度について
医療と介護の両方の保険給付を受け、その自己負担額の合計が高額になる世帯の負担軽減を図る制度です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合には、その超えた分が支給されます。
該当の支給が発生した場合、岡山県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が届きます(2月上旬~中旬頃)。
申請方法など詳細については、広域連合から送付されるお知らせをご確認ください。
保険料
後期高齢者医療では、被保険者一人ひとりが保険料を負担することになります。
みなさんが病院などにかかったときの医療費は、被保険者が窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されます。
この医療給付費のうち、約1割がみなさんの保険料でまかなわれます。
保険料の決まり方(令和7年度)
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
- 一人当たりの年間保険料=
均等割額 50,200円
※限度額 80万円
- 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
※賦課のもととなる所得金額
前年の総所得金額等から基礎控除額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を控除した額
ただし雑損失の繰越控除額は控除しません。
※賦課期日
年度当初の4月1日、年度の途中で資格を取得した場合はその取得日。
保険料の軽減(令和7年度)
軽減にあたっては、あらためて手続きする必要はありません。
1.均等割額の軽減
所得の少ない世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
| 均等割軽減内容 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
|---|---|
| 7割軽減 15,060円/年 | 【43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯 |
| 5割軽減 25,100円/年 | 【43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数】以下の世帯 |
| 2割軽減 40,160円/年 | 【43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数】以下の世帯 |
- 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人です。
- 基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります。
- 軽減の判定は賦課期日現在で行われます。
- 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から最大15万円を控除し判定します。
※ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
※ 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
2.被用者保険の被扶養者であった場合
後期高齢者医療制度加入の日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、制度加入時から2年間、均等割額が5割軽減され、25,100円(年額)となります。なお、所得割額の負担はありません。
※均等割額「7割軽減」に該当する方は、そちらの軽減措置が適用されます。
※国民健康保険及び国民健康保険組合は該当しません。
保険料の納め方
1.保険料額決定通知書の送付時期(おおよその目安です)
- 75歳になった方…お誕生月の2か月後(ただし4月誕生月の方は7月に送付)
その他の理由で加入された方(岡山市への転入等)…加入後、約1、2か月後(ただし、4月に転入した方は7月に送付)
2.納付方法について
保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替・納付書払い)があります。後期高齢者医療制度に加入した方は、しばらくの間普通徴収(口座振替・納付書払い)となり、その後、原則として特別徴収(年金天引き)となります。
(1)特別徴収(年金天引き)
保険料の納付方法は、原則として介護保険の保険料が引かれている公的年金(注1)から、年6回の年金受給時に天引きとなります。特別徴収が可能と判断された場合、自動的に切り替わります(被保険者の方によるお手続きは不要です)。また、4・6・8月は保険料決定前の仮徴収期間といい、2月に特別徴収を行った人のみ、同額で天引きします。
納付方法
年6回の年金受給時に年金から天引きされます。
特別徴収(年金天引き)にならない方
- 年金天引きの対象となる公的年金(介護保険料が年金天引きされている年金)※が、年額18万円未満の方
- 年金天引きされる予定の1回当たりの後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金天引きの対象となる公的年金の1回あたりの受給額の2分の1を超える方
- 岡山市の介護保険料が年金天引きになっていない方
- 後期高齢者医療制度に加入したばかりの方
- 年度の途中で他の市町村から転入されたばかりの方
- 岡山市内の住所地特例施設への転入で、介護保険は前住所地の自治体で資格を継続する方
- 年金担保貸付を返済中の方
- 納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収への変更)を提出した方(下記(3)納付方法の選択 を参照)
※年金天引きの対象となる公的年金について
・受給されている年金のうち、優先順位の高い一つの年金だけが年金天引きの対象になります。対象となる年金の優先順位は法令で定められており、老齢基礎年金が最も優先されます。
・年金受給額が18万円以上の年金を複数受給している場合は、優先順位が最も上位の年金で特別徴収の可否が判定されます。
(2)普通徴収
対象者
・特別徴収の条件に当てはまらない方
・納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収への変更)を提出した方 (下記(3)納付方法の選択 を参照)
納付方法
納付書もしくは口座振替により、7月から翌年3月の期間(9期)で納付
注:納付方法変更申出書の提出により普通徴収になった場合は、口座振替による納付のみとなり、納付書での納付はできません。
(3)特別徴収と普通徴収の両方
| 対象者 | 納付方法 |
|---|---|
| 年度の途中で保険料が減額になった方 | 現在の特別徴収を中止し、残りの金額を普通徴収で納付。 |
| 年度の途中で保険料が増額になった方 | 増額前の保険料は特別徴収でそのまま納付し、増額分のみを普通徴収で納付。 |
| 10月から特別徴収が開始される方 | 特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納付。 |
| 特別徴収の要件に該当しなくなったため、特別徴収を中止された方 | 中止以降は普通徴収で納付。 |
(4)納付の手続きなど(料金課ホームページへ)
- 納付書による納付(納付場所、コンビニ収納・スマホ決済)について
- 口座振替について
- 納付金額確認書について…確定申告や市民税申告などで保険料の納付金額の確認が必要な時にご請求ください。
3.納付方法の選択
年金からの天引きで保険料を納める方でも、届出により、保険料の納め方を口座振替に変更することができます。
「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」の提出が必要です。
変更をご希望される場合は、医療助成課までご連絡ください。手続きには約3か月かかります。
- 口座振替以外の方法には変更できません。
- 口座振替依頼書だけでは、年金天引きを中止できません。
- 滞納がある場合は、別途相談となる場合があります。
保険料の納付相談について
保険料の納付が困難な場合には、納付相談を行っています。滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
相談窓口:料金課(電話086-803-1641・1642・1643)
滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部又は一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。また、滞納処分の対象となり、場合によっては財産などが差し押さえられることがありますので、保険料は期限内に収めるようにしましょう。
災害など特別な事情により、保険料の納付や病院窓口での自己負担金の支払いが困難となった場合には、申請により保険料もしくは一部負担金が減免される場合があります。
詳しくは医療助成課までご相談ください。
健康診査(健診)について
75歳からの健診(※)は「後期高齢者健康診査」となります。
受診券等での個別案内はいたしませんが、ご自身の健康管理のためご利用ください。
(※)障害を事由に後期高齢者医療制度に加入している方も含みます。
詳しくは、健康診査(健診)についてのページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の払い戻しを装った振り込め詐欺にご注意ください
本市職員などを装って「医療費の払い戻しや、保険料の還付があります」などと電話をかけてきて、金融機関のATM(現金自動預け入れ払い機)を操作するよう誘導し、現金を振り込ませようとする「振り込め詐欺」が発生しています。
岡山市では、保険料や医療費の還付金などの受け取りのために金融機関などのATMの操作を求めることや、連絡先にフリーダイヤルを指定することはありません。決して電話をしないでください。
また、お支払する還付金のお知らせは、すべて文書で行なっています。電話のみで行なうことはありません。
不審な電話があった場合は、その場で対応せずに、相手の所属・氏名・連絡先を確認し、一度電話を切って、医療助成課(電話:086-803-1217)または岡山県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉局保健福祉部医療助成課 長寿医療係
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1217 ファクス: 086-803-1751