はじめてづくしの現場で…
まだまだ埋蔵文化財センターができるかなり前の調査です。1990年6月から8月の2か月間、中国銀行本店の建て替えに伴う岡山城二の丸跡の発掘調査がありました。私にとっては岡山市教育委員会に入ってはじめての担当した発掘現場、はじめての民間開発に伴う記録保存の発掘調査でした。しかも、はじめての近世の遺跡の調査、はじめての真夏の炎天下での調査です。
あの時は

発掘調査は現在の中国銀行本店ビルのうち旧本社建物部分を除く約1,500平方メートル。民間の建設計画に伴う発掘調査ということもあり、調査期間も十分に確保されていません。同時期に実施していた西祖橋本遺跡が500平方メートルで6か月間、原尾島遺跡が3,000平方メートルで20か月間と比べるとどれだけ過酷な日程かわかります。
今では考えられませんが、夏場で遅い時間まで明るいこともあり、現場には照明が設置され夜7時過ぎまで連日調査作業が行われました。私は大学を卒業したてだったこともあり、そのあと大学に通い学生時代に調査した古墳の出土物整理、発掘調査報告書の作成作業をしていたのが思い出されます。当時流行した「24時間戦えますか!」ではありませんが、若かったなとつくづく思います。
猛暑が続く現在ほどではないのでしょうが、夏場の炎天下での作業も酷でした。市街地の発掘現場、建設工事現場なので周囲は高い防音、防塵シートの仮囲に囲まれています。ビルに囲まれた中、風も全く通り抜けません。
重層的な遺跡と歴史史料
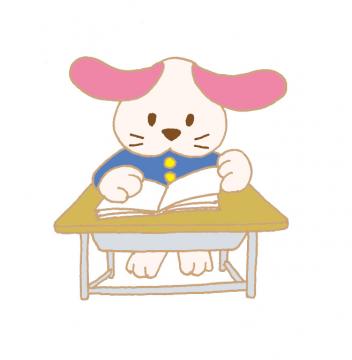
私にとってはじめて尽くしの発掘調査でしたが、その後の仕事に大きな影響を与えた調査でもありました。
重層的な遺跡の調査と歴史史料との対比などです。岡山城は江戸時代の城下町などの絵図類が豊富です。岡山大学の池田家文庫所蔵の各時期の絵図と対比すると、調査地点がおおむねどの屋敷地に対応するか判明します。調査で検出した遺構もその中での位置づけが可能なのです。また、調査範囲内ではありませんでしたが、近くに「鍵屋の辻の仇討ち」事件で有名な石川数馬の屋敷があったことなども知りました。
調査序盤、大型の石組み井戸が検出されました。幕末ごろの井戸だと思い調査を進めていましたが、井戸の底から大量の注射器とプレパラートが出てきました。調べると明治期、調査地点周辺は岡山大学医学部の前身となる岡山医学専門学校があったことがわかります。ちょっと怖いですが、医療廃棄物です。それより下層には洪水砂層があり、その上下の出土物などから、百間川開発のきっかけともなった承応3年(1654)の洪水とみられることもわかりました。
さらに調査が進むと、宇喜多・小早川時代とみられる層、遺構が現れます。このころの城下を知る史料はほとんどありません。そんななか金箔貼りの鬼面の鬼瓦が出土しました。岡山城は安土城や秀吉の大阪城のように瓦に金箔を貼っていたことで有名ですが、城下町の武家屋敷まで金箔瓦が使われるとは考えられません。江戸時代にはない城郭施設―櫓や門が付近にあったに違いありません。その後、岡山県庁内の調査などもで古い堀が検出されるなどしており、どうやら宇喜多時代の城下は江戸時代と違っていたようです。
金箔押し鬼瓦
今から400年前ほど前、宇喜多秀家が岡山城を築いた頃のものです。頬や額、下顎など、周囲は欠けていますが、目は大きく、歯をむき出していることがわかります。
金箔押し鬼瓦の側面
金箔おし瓦は本丸の発掘調査でも出土し、秀家の岡山城の豪華絢爛ぶりがうかがえます。
さらに発掘調査後、建築工事が進むと、地下掘削部分を見せていただく機会がありました。地下15mほどの深さの部分です。岡山平野のそんな深さでボーリング調査ではなく土層を直接見ることができることは、今考えても非常に稀有な機会といえます。そこには、粘質で有機質の強い湿地状の堆積物に挟まれて、20cmほどの厚さで鮮やかな黄色の火山灰層がありました。学生時代、恩原高原の発掘調査でよく目にした姶良(At)火山灰です。姶良(At)火山灰は今から約2万2千年前に今の鹿児島県南部、姶良カルデラが大爆発した際に噴出した広域火山灰です。関東や東北地方までも到達している火山灰で、岡山平野でもこの厚さに降灰しているとは、いったいどれだけの大噴火だったのか恐ろしくなります。
旧中国銀行本店
さて、この建て替えで取り壊された旧本店ビルは昭和2年(1927)に第一合同銀行本店として建てられた建物で、設計は総社市出身の建築家・薬師寺主計です。調査開始時にはまだ残っていましたが、スクラッチタイルとアールデコ調の装飾の美しい建物でした。当時、まだまだ自分もほとんど知識がありませんでしたが、非常に残念な思いがありました。私はその後、2003年の岡山県近代化遺産総合調査、2011年の岡山県近代和風建築総合調査などもあり近現代の建築や土木遺産に興味を抱きますが、最初のきっかけはここにあったのかもしれません。
この調査は、発掘調査報告書が刊行できていない調査の一つです。当時の体制や調査スケジュールを見ると無理もないことではあるのですが、われわれ埋蔵文化財センター職員に残された課題の一つといえます。
中国銀行本店入口の写真です。
旧中国銀行の入口のみが今でも残されています。
お問い合わせ
教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化財センター
所在地: 〒703-8284 岡山市中区網浜834-1 [所在地の地図]
電話: 086-270-5066 ファクス: 086-270-5067
